noteの記事です。
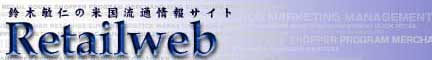 |
|
|
オンデマンド型短時間宅配のプロバイダー、インスタカートがストアピックアップの代行もはじめたのが6ヶ月前でしたが、現在すでに30州以上、小売企業25社へ拡大していることを明らかにしました。
11月から全米展開を開始するとしています。
インスタカートをストアピックアップのプロバイダーとして利用している企業としてあげられているのは、アルバートソンズ、パブリックス、フードライオン、スプラウツ、ゲルソンズ、シュナック、トップス等々、これからはじめるのがウェッグマンズ等々。
インスタカートは買物代行で、代行するショッパーが店頭で買い物をするわけですから、これの保管場所があれば、ストアピックアップに対応できるわけです。
商品をお客へ届けるよりも、お客に店に来てもらうストアピックアップの方が、来店してもらうという意味で重要です。
両方を選択肢として用意した上で、後者を強化するのが、小売企業のEC戦略として正しい、が私の持論。
ここで、ウォルマートやターゲットのように自社でやる、またはインスタカートのような会社に委託する、という選択肢がアメリカ小売企業にはあり、日本には委託するという選択肢が限られている、が現状ということになるわけです。
日本のライフがアマゾンのプライムナウを使って宅配を開始するというニュースを聞きましたが、インスタカートのような企業がいればアマゾン経済圏に取り込まれる必要は無いのです。
3月にやめたジェレミー・キングCTO(Chief Technology Officer)の後任として、スレシュ・クマールという人が就任するというリリースが発表されました。
経歴はグーグル、マイクロソフト、アマゾン、IBM、と今をときめく有名なテクノロジー企業を斜め上にキャリアアップしながらウォルマートまでやってきた、という人です。
取り上げた理由は2つ。
1つめは、ウォルマートのCTOは組織図上CEOのダグ・マクミロン直下にいるということです。
Eコマースとは横並びで別個に存在している。
もともとCTOはECのマーク・ロリーの下だったのですが、ポジションが変わった模様。
職務内容を確認したわけではないので確実ではないですが、例えば店頭で動く自走ロボットなどEC以外にもテクノロジーは必要ですから、そういう組織構造になるんだろうなと。
ちなみにCIOはまた別個に存在し、こちらはCFO管轄です。
サイバーセキュリティや総務系の情報テクノロジーを統括している。
日本は今もCIOを技術系のトップとして扱いますが、ウォルマートは昔から組織の考え方は柔軟で業界標準には従わない企業です。
2つめはクマールが小売畑の人ではないと言うことです。
マーク・ロリーがECを掌握してから急速に同社のデジタル戦略が進み始めて、やっぱり小売業界の外にいるデジタルな人じゃないと無理なんだねえを実感。
デジタル系部門のトップを社内人材で埋めている日本の小売企業のデジタル変革は、やっぱりなかなか進んでいかないだろうなあ、と思うわけです。
ループというスタートアップ企業がクローガーとウォルグリーンと組んで興味深い試みをはじめました。
百聞は一見しかず。
パッケージ(入れ物)は借りもので、中身を詰め替えて、専用の持ち運び用の入れ物(トート)で、届き、消費し、返す、という仕組みです。
これをグルグル回すのでループという名称なのでしょう。
詰め替えをさらに進化させた手法と考えるとわかりやすいでしょうか。
日本では詰め替えはよくある当たり前の手法となっていますが、アメリカでは普及していません。
日本型を経由せず、一足飛びにもう一つ先へ向かう試み、といったところかなと思います。
小売店舗は受け渡し用のハブとして機能させたいようです。
なので小売にどういうメリットがあるのか分からないのですが、手数料が入るようなスキームかもしれません。
現時点で参加しているブランド数は41、アイテム数は81、地域は東海岸の2都市限定となっています。
ゴミが減るという点がカギ、サステナビリティ意識に訴求しそうで、非常に興味深い試みだと思います。
成否のカギは利益を出せるクリティカルマスに達することができるかどうか。
今後に注目です。
フォードが二足歩行宅配ロボットの実験を始めると発表しました。
どういうことなのか、まずはビデオを見てください。
自動運転車が宅配場所まで行き、ロボットがボックスを家まで運ぶ。
この二足歩行ロボットが解決するのは段差や障害物ですね。
アマゾンやFedExが実験を始めている小型ロボットは車輪で動くため、階段や障害物があるとそこから先に行けないというハードルがありまます。
なので一定の場所までお客が出て行かなければならない。
これがラスト50フィートの課題。
このハードルをこの二足歩行宅配ロボットが解決するというわけです。
フォードは2021年の実用化を目指すと言っています。
まだ先の話だろうと思っていた二足歩行のロボットが、もうここまで来ているのかと知って驚いたのでした。
ターゲットのメンズ衣料PBグッドフェローがメンズグルーミングに商品を拡大しました。
店舗導入は5/19と発表されているので、すでに店頭に並んでいます。
投入カテゴリーは、ひげ剃り、フェースケア、ボディケア、フレグランス、アクセサリー、価格は3.99~16.99ドルで類似のプレミアムブランドよりも20%安いとしています。
ターゲットはPBを刷新して成果を上げているのですが、勢いはまったく止まらず、どんどん増えてます。
怒濤のPB強化、という感じ。
ターゲットの強さはPBにあったので、完全復活という印象を私は持っています。
アパレル専門店チェーンのH&Mがロイヤルティプログラムを導入すると発表しました。
いま入会するとドライバーのディスカウント券がもらえるという販促やってます。
・・・ドライバー=Dry Barです。ゴルフじゃないですよ。
いわゆる日本で言うところの会員カード、またはID-POSをはじめるというわけなのですが、このプログラムの本質は販促でして、ちゃんと集客できている企業には不必要なものであります。
業績に行き詰まり感があるとか、落ちてきたとか、差別化するなにかがなくなってしまったときに始めるものです。
データ獲得に必要だということを言う人が出てきそうですが、買い物客とバスケットを紐付けなければ分析はできないというわけではありません。
ウォルマートはロイヤルティプログラムにまったく興味が無い企業ですが、各アイテムに相当数のDNAをつけて、バスケット分析を長いことやってます。
ということで、H&Mもそういうところに来たのかな、ということをこの一件でうかがい知ることができるというわけです。
リドルがネット販売のボックストと組んでオンデマンド型宅配を実験を来月から開始します。
6ヶ月の期限つきです。
どういうスキームなのか公表されていないようなのですが、ボックストがシステムと短時間宅配を提供するということを書いているメディアがあります。
リドルのウェブサイトで完結するのか、それともボックストのサイトの中にリドルのページが組み込まれるのか。
企業規模からするとおそらく前者だろうと思うのですが、具体的に始まってみないとわかりません。
ボックストはコストコタイプのバルク販売で、アソートを絞りきるマーチャンダイジングですから、同じくアソートを絞る業態のリドルと相性が良いと言うことになります。
さてそうすると、この組み合わせの成否如何によっては、ボックストはイオンと資本関係がありますから、イオン傘下のビッグエーでボックストのEC技術が使えるのでは、ということを夢想したり。
日本は基幹システムがレガシー化しているので簡単にはいきません、がオチかもしれませんが。
ベッドバス&ビヨンドのスティーブン・テメアズの辞任が発表されました。
後任は決まっておらず見つかるまで現CFOが暫定CEOとなるそうです。
ベッドバス&ビヨンドはここ数年業績を悪化させていたのですが、改革がまったく進んでいませんでした。
ここに目を付けたのがアクティビスト型投資企業で、経営陣と取締役会のリストラを要求していました。
経営陣に向けてプレゼンをしていて、この内容が公開されているのですが、相当厳しいものだったようです。
スライド枚数は168枚、ひたすらダメ出しを繰り返したらしい。
まず取締役だった創業者2人がやめて、次が今回のCEOの辞任です。
あっさりとやめたということは、改革が進んでいないということを自覚していたのかもしれません。
ひっかかるのは後任不在でやめたことです。
次を育てていなかった可能性が高い。
フォーマットのバージョンアップもやってないですし、テメアズの責任は軽くないようです。
米国労働省が4月の雇用統計を発表しました。
倉庫業界が先月一ヶ月間で増やした新規雇用者数は5,400で、4月連続の増加、過去12ヶ月では70,000増えたそうです。
増えている最大の理由はEC、フルフィルメントセンターの増加にあるようです。
とくに大都市周辺で急速に増えていて人手不足が起きている模様。
アマゾンが8億ドルを投じて無料宅配を2日から1日へと短縮しますが、これが競合に影響を与えて宅配サプライチェーンの再"最適化"が必要となり、倉庫業界の成長に拍車をかけるだろうという話も出ています。
ちなみにトラックなどの輸送業界の方もここ数年雇用を増やしづけてきたのですが、どうやら一息ついた感があるようですね。
H&Mが先月末をもってカタログの配布をやめました。
資料によるとメールオーダー企業を1980年に買収して、それからカタログを配布してきたそうです。
理由は、環境負荷軽減と、カタログショッピングは今の時代の買い物に沿っていないから、と説明しています。
カタログをやめてしまった企業としては、ビクトリアズシークレットやイケアが有名です。
一方、デジタルネイティブなのにカタログ配布を始めたのがアマゾン。
ウォルマート傘下のジェット・コムは紙クーポンを発行しています。
カタログをどうするかはなかなか難しい課題で答えは一つではありません。
リアルな販促媒体は過去5年間に増えているという調査結果もあり、どちらかというとリアルの方が増えていたりします。
理由はいくつかあるのですが、ここでは1つだけ。
代わりにEメール広告を使うということになるわけですが、増えすぎてしまっていて消費者が見なくなってしまっているということが指摘されています。
オーバーフローですね。
例えば私の場合、特定ブランドに興味を持つとニュースレターに登録することが多いのですが、しばらくすると飽きて登録を解除してしまいます。
オーバーフローの中で飽きられずに見てもらうというのは、簡単なことではありません。
ということで、H&Mがやめたので、紙の媒体は古いんだ、と理解してしまうのは間違いで、どうするかは各企業の戦略的判断しだいということになるのです。
マクドナルドがドライブスルーで表示するメニューにAIを使い、時間、トレンド、気候、混み具合などを勘案して表示を変えるシステムを700店舗に導入すると発表しました。
3月末に買収したイスラエルに本社を置くDynamic Yield社がシステムを提供しています。
Dynamic Yield社のシステムは、specializes in personalization and decision logic technology、と説明されています。
パーソナライゼーションと、決断に至るロジック、のテクノロジーに特化した企業、ということになりますね
セフォラやイケアなど300社と契約して仕組みを提供していて、マック傘下に入った後も今まで通り営業は続けるとしています。
競合してる外食企業がいないのかもしれません。
ちなみに買収額は公的に発表されていないようですが、メディアは3億ドルと伝えていて、マックの過去20年間で最大だそうです。
レストランのメニューは、とくにファストフード業界はどんどんデジタル端末化しています。
ここに表示される内容をダイナミックに変えるという取り組みは、なかなか興味深い。
またテーブルレストランのメニューもタブレットを使う企業が出てきていますが、これも今のところ固定された表示が普通ですが、AI使って特定顧客に合わせてダイナミックに変えることが可能ですね。
厨房内の什器がすべてネットにつながるスマートキッチンの波も来てます。
外食業界もデジタル化の時代です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |


最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS