ウォルグリーンがビューティをテーマとした雑誌を発行して自店で販売を開始するそうです。
名称はDiscover Beauty Within、売価は1.99ドル、もちろん目的はコスメの売上アップですが、ビューティ売場担当者(名称はビューティアドバイザー)の営業支援という意味合いもあるようです。たぶん、雑誌を見せながら売る、といったことでしょうね。
ウォルグリーンもCVSも強化しているとは言うものの、ドラッグストアのビューティケア売場はやはり限界があります。
ウォルグリーンはこれを突破しようと模索していますよね。
ビューティにはマーケティング活動(または店舗イメージでも良い)は不可欠で、このマーケティング活動に雑誌などのメディアは不可欠です。
そういう意味で、このニュースからウォルグリーンの本気度を伺えます。
ただしこれが成功するのかどうかは別問題ですが。
売れずにいつの間にか消えてなるというのは良くある話です。
ちなみにおそらくメーカーから協賛もらうでしょうから、失敗してもあまり痛くはないでしょうね。
ウォルマートがクレジットカードのVISAカードを提訴しました。
VISAとマスターカードの二社による独占によって競争が阻害されて設定されている決済手数料が不当に高い、セキュリティが低い磁気ストライプ方式を今だに使用しICチップ式や非接触型へ転換する努力を怠っているとし、補償額として50億ドルの支払いを求めています。
この対クレジットカード企業訴訟はいまに始まったことではなく、ここ数年何度も起こっています。
カード大手が小売企業による集団訴訟で和解
ここでいったん和解しているのですが、ウォルマートやターゲットといった大手企業は和解に賛同していません。
その結果が単独訴訟というわけです。
この2012年の記事で、「今回の結果が決済システムを進化させる転換点になるのかどうか」と書いているのですが、転換の契機にはまったくなりませんでした。
その結果がターゲットでのデータ漏洩事件につながった。
ウォルマートは自分で銀行を持って自分で決済をやろうとしたことがあるのですが、金融業界による強力なロビー活動でつぶされました。
ウォルマートは再びこの聖地に訴訟で挑もうとしています。
ターゲットのデータ漏洩問題については複数の経済誌がしっかりした取材記事をすでに掲載しているのですが、上院の特別委員会に提出された調査レポートが昨日公開され、ターゲットが漏洩のサインをいくつも見逃したことがその中で指摘されていると昨日のニュースで報じられています。
細かい内容は省きますが、セキュリティシステムが何度か警告を発したにもかかわらず、その警告を担当部署が見逃したという趣旨です。
経済誌が報じている内容はこれをさらに深掘りしたもので言っていることは同じです。
アメリカの決済システムは旧態依然としていてハックされやすいのは事実なのですが、それに対する対応策はシステム的にちゃんと打たれている。
そのシステムが発した警戒信号をターゲットの担当者が見逃したという内容で、つまり職務怠慢が一因だったというわけです。
なぜ見逃すことになったのか、実はこれがまだわかっておらず経済誌もこの点について明確に書いていません。
たぶんこれから明らかになっていくことでしょう。
ちなみにターゲットのCIOはすでに引責辞任しています。
ウォルグリーンの調剤売場で患者のプライバシーが守られていないという理由で連邦当局が調査を開始したとメディアが報じました。
ウォルグリーンの最近のプロトタイプはいくつかありまして、そのうちの一つが薬剤師による患者のプライベートコンサルテーションを可能とするプライベートルームを、調剤カウンターの横に設置するものです。
ここで、規定のプライベート環境が維持できていない、というわけです。
例えば患者のメディカルレコードが衆人の目に付くところに置きっ放しになっていたとか、調剤が無人のまましばらく放置されていたとか、そういった細かいチェック項目があるようです。
おもしろいのは、当局にクレームしたのがChange to Win Retail Initiativesという民間団体で、その結果としてお上が動き始めたのですが、資料によるとこの団体に対して労働組合が資金を拠出しているんです。
ウォルグリーンはアメリカの非食品系チェーンストアによくある組合が存在しない企業でして、つまり組合によるアンチウォルグリーン活動の一環としてこういうことが行われているというわけです。
アンチウォルマートのプロパガンダと根っこのところは一緒ということになります。
アメリカではこういうところでも労働組合が活動しているんですね。
フェデックスが第3四半期の業績を発表したのですが利益を落とし、CEOのフレッド・スミスがその原因として悪天候とクリスマスシーズンの宅配トラブルを挙げました。さらに宅配トラブルを起こした原因の一つは小売企業が抱えている問題に根ざしていると指摘しています。
要するに悪いのは自分たちだけじゃないということを言いたいわけですね。
これがそのときの記事。
クリスマスまでに届かなかったクリスマスプレゼント
小売企業が持つフルフィルメントの技術力は通常高くありません。
まだ始めたばかりですからノウハウが積み上がっていない。
だから取り扱いボリュームが前年を大きく超えるとパンクしてしまうわけですね。
一方のアメリカの宅配企業も似たようなものです。
日本のように競合企業が林立するような環境ではないため技術を進化させるというモチベーションが低く、そのためネットワークに緻密さがないですし、価格が高い。
双方ともに小口物流に対する技術が低く、どんどん成長しているネット販売に対応できていないということです。
これ、同じようなトラブルがこれから頻発しつつ、トライアル&エラーで改善されてゆくのでしょうね。
私が注目しているのは、自社宅配にしてしまう小売企業がこれから出てくるのかどうかです。
アマゾンは確実に導入するとして、ウォルマートがどうするかですね。
ウォルマートが中古ゲームソフトの買い取りと販売を開始することを発表しました。
3/16から取り扱いを開始、対価はウォルマートのギフトカードで支払われます。
当然単独では無理で、CExchangeという専門企業とのジョイントです。
コンセなのか、技術供与なのか、といった詳細は不明。
ウォルマートは2009年に中古ゲーム買い取りの実験をしています。
中古ゲーム市場にキオスクで参入
ベストバイとほぼ同時に導入したのですが、これは結局うまくいかなたかった。
今回はつまり再挑戦ということになりますね。
中古ゲームソフトはベストバイやアマゾンが取り扱っているのですが、大きな収益源にはなっていないようで、理由はゲームストップの存在でしょうね。
中古商品の取り扱いには高度な専門知識が要求され、熟練店員を多く雇っているゲームストップを支持するゲーマーが多いのだそうです。
中古は難しいですがが儲かります。
だからウォルマートはやりたい。
成否は分かりませんが、とりあえず挑戦するのがウォルマートです。
ところで昨年、いつだったかは覚えていませんがウォルマートがベントンビル周辺でコンビニの実験用に土地を確保したというニュースが流れました。これが本当だったようで、3/15にソフトオープンさせたようですね。
名称はウォルマート・トゥ・ゴー、フレッシュカテゴリーのネット販売と同じ名前を使っているところが興味深い。ガソリンスタンド併設タイプの模様です。
かねてから噂のあったランズエンドのスピンオフですが、取締役会が承認し、4月4日よりNASDAQに上場させることが明らかとなりました。
資料によるとランズエンドの昨年度の年商は156億ドルで最終利益高が789億ドル。
シアーズ店内のショップはリース契約に切り替えて今後も営業は継続されます。
シアーズはランズエンドを2002年に19億ドルで買収しています。
上場でどのぐらいの資金を調達できるのかは資料に書かれていないので現時点では不明です。
これで切り売りできる小売事業はなくなったんじゃないでしょうか。
残りはケンモア、クラフツマン、ダイハードのプライベートブランドですが...。
ダラーゼネラルが第4四半期と通期の決算を発表しました。
増収増益も予想を若干下回ったのですが、それはさておき、今年度の出店予定数が700で、相変わらずの増殖ぶりに目を見張りるものがあります。
昨年度の650から50店舗増加。
1日あたりにすると1.9店舗です。
機械のように出店する仕組みができあがっているんでしょうね。
それともう一つ重要なことは撤退の時期を測る尺度です。
キャッシュフローが一定ラインを下回ったら何らかの手を打ち、一定期間経っても変わらなかったら有無を言わさず閉店する。
たぶんこの企業はそういう仕組みも持っていると思います。
昨年度末の時点で11,132店舗。
どこまで増えるんでしょうね。
アマゾン自身が公言していたプライム年会費の値上げが公式に発表されました。
79ドルから99ドルへ。
これがこれからアマゾンの収益にどう影響を与えるのか、興味津々ですね。
アマゾンはプライムに含まれるサービスを増やそうとしています。
典型例が音楽のストリーミング、現在実現に向けて関係企業と調整中と報じられています。
また配送コストも上昇していて、コストを吸収できなくなりつつある。
そのため値上げする必要が生じてきた。
一方最近の調査では、値上げしたら更新しないと答える人がけっこういる。
プライムに含まれるサービスと、年会費と、お値打ち感をどう消費者が判断するのか。
ちなみにアマゾンはプライムの会員数を公表していないのですが、グローバルで2,000万人程度だろうと見積もられています。
現在研修のコーディネートでダラスにいます。
ウォルマートでまたすごい陳列を見つけてしまいました。
ちょっと見えづらいかもしれませんが、ハンガーなんです。
右サイドの通路にハンガー売場があって、これをアウト展開しているわけですが、何が凄いって、陳列用の什器というか骨組みを手作業で作っているんですよね、これ。
やっぱりウォルマートは面白いです。
投資企業のサーベラスによるセイフウェイの買収が決まりました。
総額は90億ドルの予定。
アルバートソンズと合併することになるのですが、両方合わせると年商は600億ドル近い。
久しぶりに目の覚めるようなディールですね。
ラジオシャックが第4四半期に赤字を計上、再建策の一環として大幅な店舗閉鎖を発表しました。
閉鎖するのは1,100店舗で、これは4,000店舗の27.5%にあたります。
逆に言うとこれだけの不採算店舗を抱えているということなんですね。
ラジオシャックに買いに行く理由が見つからない。
これがこの企業の問題でしょう。
小商圏型の家電ストアがどう生き残れるのか。
ハードルは高そうです。
シアーズが昨年度の決算を発表しました。売上高は9.2%減、最終利益高は13億65万ドルの赤字、既存店成長率は3.8%減でした。
現時点でのリリースにキャッシュフロー表がないのでお金がちゃんと流れているのかどうかが分からないのですが、EBITDA表が代わりに表記されていて、3億3,700万ドルの赤字でした。
数値はぜんぜん良くなってないですよね。
ご存知の通り、店舗の切り売りで運転資金をまかなっている現状です。
でもランパートは相変わらず強気です。
株主あての公式レターで、「我々の方向性は間違っておらず、それだけではなく我々がいまいるところへ業界が向かっている」と言ってます。
方向性とはEコマースとロイヤルティマーケティングの強化で、店舗は二の次とするものですね。
シアーズとKマートの店舗はとにかく劣化が激しいのですが、"飾りや什器に投資しろという外部識者のコメントは間違っている"と断じてまして、それでいいのだと胸を張ってます。
もう彼の頭の中には店舗が無いのかもしれません。
それで本当にいいのだろうかといつも思うのですが、どうなんでしょう。
投資家ランパートの考えていることはやはり分かりません。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
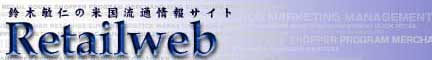



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS