ウォルグリーンがライトエイド買収プランのデッドラインを7月31日まで延長すると発表しました。
当初の期限だった1月27日から半年延長したことになります。
理由はFTCからの認可がなかなか下りないことにあります。
また買収額を下げたのですが、売却または閉鎖する店舗数が増えたため企業価値が縮小したことが理由です。
ライトエイドの株価も落ちてます。
実はトランプ政権が発足するとFTCの責任者も替わるため、それまでに決まるだろうとみられていました。
また認可されるだろうというのが大方の見方でした。
ただ、売りに出される店舗をフレッズが買収することですでに合意しているのですが、どうやらこれが本当に可能なのかどうかという懸念もあるようですね。
そのためサーベラスが絡んでくるのではないかという話が出ています。
資本調達をバックアップするのか、それともサーベラスも店舗を取得するのか、このあたりは分かりません。
ドラッグストアは競合状況をどこで測るか、なかなか難しいところがあります。
売上の7割近くを占める調剤は、ウォルマートやコストコといった他業態とも競合しているし、メールオーダーでPBMとも競合していている。
とくにメールオーダーはけっこう強い。
これをFTCがどう捉えるのかです。
ステープルズによるオフィスデポ買収プランで、Eコマースとの競合をFTCが重視せず認可しなかったのと同じような状況と言えば分かりやすいでしょうか。
ちなみにCEOのペッシーナは強気で、買収できなかった場合のセカンドプランというものは考えたこともないと言ってますね。
成功するまではあきらめない、あきらめないから成功するんだという、創業CEOならではの発言じゃないでしょうか。
アマゾンが配給権を持つManchester by the Seaがオスカーの作品賞にノミネートされました。
昨年の1月にサンダンス映画祭で上映されて、アマゾン・スタジオズが1000万ドルを投じて配給権を購入していたものです。
トータルノミネート数は6つなので、作品賞だけではありません。
過去アマゾンオリジナルとしては、TV'シリーズでTransparentがゴールデングローブの作品賞と主演男優賞を受賞しています。
まだノミネート段階ではありますが、オスカーははじめてとなります。
いつも通りアマゾンは詳細を公開していませんが、2014年の1年間でビデオストリーミングに13億ドルを投じたという数字が出ていて、相当が金額をこの分野に投資しており、これがようやく実りはじめているという印象です。
もちろんプライムの価値を高めることが目的なのですが、こういう分野で有名な賞を取ったりノミネートされたりするとアマゾン自体のイメージも相当良くなりますよね。
消費者の頭の中に占める比率がどんどん高くなっていってしまいます。
アマゾンの多角化戦略は小売とは異質で、そして異質な理由は置いている軸足にあるわけです。
その軸足というものを今日はいろいろ考えているところです。
ウォルマートが今月末に本社人員の1,000人を解雇します。
組織編成の見直し、つまりリストラクチャリングの一環ですね。
対象となっているのはサプライチェーン、人事、Eコマースなど。
同社は年内に1万人を雇用する予定であることを発表し、トランプが感謝のツィートをして注目されました。
これがけっこうメディアに取り上げられたのですが、実はもともと予定していた雇用計画で、トランプにプッシュされたから増やしたと言うわけではありません。
アマゾンも今後1年半で10万人を雇用すると発表していますが、これもたぶんもともと予定していたものを宣伝効果が高そうだからあえていまの時期に出したものだろうと思っています。
そしてウォルマートはちゃんと解雇もする。
ただしこの解雇については当然のことながら表だってリリースしているわけではなく、メディアが情報を得て書いているものです。
本社の人員整理は恒例のことでして、思い出すのも難しいほど昔からウォルマートは定期的にやっています。
本社人員の総数、最後の解雇の時から今までどのぐらい増えたのか(つまりネットの増減)、このあたりが分からないので1,000人が多いのか少ないのかは分かりません。
ただ組織というものは放っておくと自然に増えていくもので、これを定期的にスリム化するのは正しい。
店舗に対して襟元をただすという、そういうポーズになることも動機の背景にあると思っています。
BCBGマックス・アズリア・グループが店舗の縮小を計画していることを明らかにしました。
BCBGは著名なデザイナーであるマックス・アズリアによって創業されたアパレル専門店チェーンで、アメリカに175店舗、グローバルで570店舗を展開しています。
店舗を縮小する代わりにEコマースに注力するとしているのですが、このあたりは破綻したリミテッドと同じです。
ECとの競合に負けたのか、単純に飽きられてしまったのか、または両方なのか、は分かりませが、経営が傾いて、ECで生き残りをかけるというパターンがアパレル業界に増えてきましたね。
店舗をすべて閉鎖していたリミテッドですが、けっきょく連邦破産法11条を申請して破綻しました。
営業していたネット販売サイトも昨日の時点で閉鎖しました。
昨年から売却先を探していて、興味を示す会社はいくつかあったようなのですが最終合意に至らなかった。
それと相手が興味を示すのは知的財産(つまりブランド)とネット販売のみだった。
ということだったようです。
だから運転資金がショートし始めてまず店舗を閉めてしまったのですが、ネット販売の閉鎖も最初から想定していたのかもしれません。
そういうことで、これから清算処理が始まるわけですが、ブランド名とネット販売は高い確率で残りそうです。
アップルのリリースによると、昨年1年間のアップストアにおけるデベロッパーの売上高が200億ドルを超えたそうです。
アップルの手数料は30%、デベロッパーの収入は70%なので、アップストアの実質売上高は280億ドルを超えたと見積もられています。
今年もこの数値を元に回転差資金を計算してみましょう。
ネットで調べた限りでは、支払いサイトは末締めの45日後払いとなっています。
とすると、最長75日後、最短45日後で、真ん中を取って60日後としてみると、こうなります。
280億ドル/365×60日=46億ドル
1ドル110円換算で5,060億円。
これが無利子の運転資金となるわけですね。
アマゾンとグーグルも同様の金融スキームを持っています。
3社が強い理由の一つなのですが、分かっている人がけっこう少ないように思ってます。
NRF(全米小売連盟)が歳末商戦の結果を発表しました。
11月と12月を合算した売上高は対前年比4%増の6,583億ドルで、予想の3.6%を上回る結果でした。
またネット販売を中心としたノンストア売上高は12.6%増の1,229億ドルでした。
数値は米商務省のデータを元にして、自動車、ガソリンスタンド、レストランを除いたものです。
すべてを含む売上高の伸びは4.4%増でした。
ということで、アメリカの消費は相変わらず堅調です。
ただしカテゴリーや業態によって濃淡があります。
マイナス成長を拾うと、カテゴリー別ではゼネラルマーチャンダイズ(雑貨)、家電、スポーツ用品、業態別ではデパートメントストアが落ちています。
マクロな数値もデパートメントストアの不調を物語っているというわけです。
ウォルグリーンがFedExと提携し、店頭で宅配パッケージの受け渡しを開始すると発表しました。
8,000を超えるウォルグリーンの全店舗で来年の秋までに受け取りと引き渡しを可能とするそうです。
引き渡しは梱包とラベルが貼ってあるものだけとなっているので、店頭で料金を払うことはできないようですね。
FedExはEC市場の拡大で増加する宅配パッケージに対応するためにインフラ投資を増やしていて、そのため増収減益となっています。
儲からない企業との契約をやめるなど顧客を選別するに至っており、けっこう大変なようです。
ウォルグリーンとの提携は高まる負荷を減らすためということになるのでしょう。
ウォルグリーンにとっては集客要素になるわけですが、取扱手数料をFedExから徴収するのかどうかは不明です。
このニュース、アメリカのドラッグストアがコンビニ的な機能を果たしていることがよく分かりますね。
アメリカのコンビニはそうとう昔に業態としてのピークを越えているのですが、スーパーマーケットだけではなくドラッグストアもコンビニエンス(利便性)というニーズを埋めてシェアを奪ってきたのです。
アパレル専門店チェーンのリミテッドが先週末に全店舗の閉鎖をホームページ上で告知したのですが、どうやら予定レベルではなくて、ネットで見た限りにおいてはすでに閉鎖してしまったようです。
ただしネット販売は存続していて、現在も営業は継続されています。
昨年度末に運転資金がショートしていて年明け早々には破綻するのではないかという噂が流れたのですが、その通りになりました。
今後の興味は、ネット販売企業として生き残るのか、それともクリアランスしてネットも店じまいしてしまうのか、ですね。
リミテッドはレスリー・ワクスナーによる創業フォーマットで、彼はこれを土台としてたくさんのフォーマットを新たに開発、または買収して育て、結局そちらの方に乗り移り、一方リミテッドは劣化していって2010年に投資会社に売却したのでした。
当時ワクスナーは思い入れのあるリミテッドの売却を渋ったようで、周囲の説得で売却を決断したと言われています。
社会の変化に合わせて業態を変化させ、箱を乗り換えてゆく、という方法論において、リミテッドほど分かりやすい実例はないでしょう。
時代の変遷というものを感じるニュースでした。
昨年末のネット販売市場はやはりアマゾンが一人勝ちだったという調査結果が出ています。
11月1日から12月16日までのネット販売総市場の37%をアマゾンが占めたそう。
また12月17日を最終日とする一週間では45.5%に増えた。
Slice Intelligenceという調査会社が170万枚のレシートを集めて分析した結果です。
2位以下は、ベストバイが3.9%、ターゲットが2.7%、ウォルマートが2.7%、メイシーズが2.5%。
アマゾンが圧勝です。
リアル小売企業はなす術もないという状況になってきた感じがしますね。
歳末商戦は景気の状況を占う指標の一つです。
アメリカでは毎年のことのように思うのですが、最初は悲観的な見方が多く、でも最後はほぼ予想通りのプラスに終わります。
昨年末は大統領選が意外な結果となってそれが買い物にネガティブに影響を与えるのではという見方が多かったのですが、しかし蓋を開けるとアメリカ人は例年通りに買い物をしたようです。
マスターカードSpendingPulseによるチェーンストアへの調査によると、11/1~12/24の期間の売上は前年比で4%増でした。
ちなみに予測数値としては、NRFの3.6%増があります。
前年同時期の3.2%増よりも高い数値ですね。
最終的な数値結果はもう少ししないと出てきませんが、その他のコンサルタント企業や調査企業のy予測数値を眺めるに、おおよそ3~4%程度の伸びで終わるように思います。
アメリカ人はしっかりと消費しているんです。
労働者の賃金の平均値は2.5%増。
失業率は最低レベル。
住宅価格は上がっていてリーマンショックで落ち込む前のレベルまで戻し住宅市場は活況を呈している。
と、いろいろなマクロ数値を並べると、アメリカ経済は決して悪くないんですよね。
だから、アメリカ経済はダメになったという主張で当選したトランプの言っている意味が私には依然としてどうも理解できない。
それとそれに乗っかってかアメリカ経済は悪いというようなことを言っているメディアが日本にもアメリカにも少なくないのですが、どうも腑に落ちない。
実はアメリカ社会が抱える本当の問題は富の偏在で、トランプに代表されるような急速に増えたスーパーリッチをどうするかという点にあると私は考えているのですが、これは話すと長くなるので今日はここまでとします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
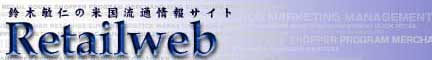



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS