ウォルマートが寝装カテゴリーに高価格帯のデジタルブランドを投入しました。
名称はオールズウェル(Allswell)、独立サイトを作り今のところウォルマート・コムとは切り離して運営されています。
目的はもちろん市場の拡大なのですが、ネットからスタートするプライベートブランドである点がカギです。
こういうのを"デジタルネイティブ"と言いますね。
デジタルの世界に主軸を置くブランド(またはリテーラー)でないと、これからの時代は負ける、という考え方が背景にあります。
デジタルネイティブで、しかも高価格帯という、ウォルマートにとっては非常に新しいところに挑戦しているわけで、これをどうマーケティングしていくのかが今後の見どころとなります。
NY州に本拠を置くトップスマーケットが連邦破産法11条の適用を申請して破綻しました。
トップスの年商は25億ドル、店舗数は170店舗、昨年度の赤字は8,000万ドルでした。
アホールド、投資企業、そしてMBOと、資本が移るに従って借入金が増えていって、この借金体質が破綻の直接的な要因なのですが、店頭のエクセキューションレベルがずっと低く、本質的な理由はマネジメント力にあると思っています。
店頭を見る限りこのままだとダメだろうなと思っていたので、やっぱり破綻か、が正直な感想です。
借入金を整理して再建、ということなのですが、経営層を入れ替えない限り完全復活は難しいでしょう。
ちなみにトップス破綻の理由としてメディアはアマゾンを挙げていませんでした。
なんでもアマゾンに帰する風潮が日米ともにあって少々食傷気味なのですが、今回は記述がなくて、まっとうな記事でした。
アルバートソンズがライトエイドを買収すると発表しました。
買収総額は明らかになっていません。
統合後の年収は830億ドルだそうです。
ライトエイドはウォルグリーンに店舗を売却し、負債が軽くなっていました。
元々丸ごと売ろうとしていた会社ですから、売りやすくなって、サーベラスが手を上げたということですね。
どうやらサーベラスにとってはこれが出口につながるみたいです。
金融スキームはよくわかりませんが、上場しているライトエイドを買うことが、アルバートソンズの上場をしやすくすると言うことのようです。
買収の理由をアマゾンとする論調を見ますが、競合というよりも、取引上のバランスゲームでしょう。
ライトエイドは会社が分解されて、取引上のパワーが弱くなってしまい、でもドラッグストア同士がくっついて大きくなるという選択肢は上位寡占が行き着くところまで行ってしまったアメリカではもはや難しい。
とすると、調剤を持っていて、同じようにスケールを求めているスーパーマーケットと統合するという選択肢が出てくるというわけです。
サーベラスがライトエイドを買収すると言う話は、アナリストが可能性としてだいぶ前から指摘してきたことなので、驚くようなことではないんです。
そもそもアメリカでは、オスコーやセブオンのように、ドラッグストアがスーパーマーケットに買収されるというディールは昔からあって、珍しいことでもありません。
アマゾンが理由とあえて言うならば、アマゾンに買われてしまう前に...、はあったのかもしれません。
福井に続いて博多でもセミナーを開催します。
皆さまのご参加をお待ちします。
『世界で同時進行するデジタル化の波、アマゾンはなぜ成長し続けるのか?』
デジタル化が世界中で同時進行し、グーグル、アマゾン、フェースブック等々と、海外のデジタル企業がグローバルに成長を続けています。なぜ彼らの成長は止まらないのでしょうか。小売業界はどう対処すれば良いのでしょうか。今回のグローバル流通最新トレンドセミナーは、アマゾンを主軸に据えてアメリカやヨーロッパの事例を解説し、皆さまのデジタル戦略の一助となる内容を提供します。
【日時】2018年4月20日 13:30開演(16:50終了予定)
【会場】アクロス福岡
福岡市中央区天神1丁目1番1号
092-725-9113
【講演者】S.M.R.Inc代表 鈴木敏仁
PwCコンサルティング合同会社 矢矧 晴彦
【受講料】12,000円(税込み)
【定員】40名
【申込締切】2018年3月20日【主催】株式会社R2リンク
【協力】株式会社未来創造学
詳細、お申し込みはこちらへ。
「グローバル流通最新トレンド」2018福岡
以下のスケジュールでセミナーを開催します。
ふるってご参加下さい。
『デジタルが変える経済社会、グローバルな変化をローカルに考える』
デジタル化が世界中で同時進行し、グーグル、アマゾン、フェースブック等々と、海外のデジタル企業がグローバルに成⻑を続けています。しかしながら消費者の嗜好は逆にローカライズ化を強めており、ローカル企業にはチャンス到来と見ることもできます。本セミナーでは、グローバルなトピックを取り上げながら、ローカル企業の取り組み課題について考えてみます。
日時:2018 年4 月17 日 13:30 開演(17:00 終了予定)
会場:福井商工会議所 地下1F コンベンションホール
福井市⻄⽊⽥2丁目8−1
講演者:S.M.R.Inc代表 鈴木敏仁
PwCコンサルティング合同会社 矢矧 晴彦
上坂会計グループ代表 上坂朋宏
受講料:1名様 20,000 円(税込み)
定員:100名
申込終了日:2018 年4 月17 日 09:00
主催:上坂会計グループ
詳細、お申し込みはこちらへ。
「グローバル流通最新トレンド」2018福井
アマゾンプライム責任者のグレッグ・グリーリーがホールフーズで費やす時間を増やしているとメディアが報じています。
グリーリーによる本来の仕事のほとんどをワールドワイドマーケティング担当のニール・リンゼイと言う人が代わりにカバーしており、アマゾンの本腰度が分かるという内容です。
プライムナウがホールフーズの商品を運び始めました。
日本のメディアは買収当初から今に至るまで宅配ネタに偏ってますが、アマゾンによる買収の本当の果実はデータの統合からもたらされるので、このプライムに関するニュースの方が重要だと考えます。
私の予測としては、アマゾンゴー的なホールフーズ専用アプリをプライム会員用に開発するのではないかなと。
その上でプライム会員に値引きを提供するわけです。
ホールフーズに効果はすぐに出るでしょうが、アマゾンにとっても得るものは非常に大きいと思います。
POSデータはもう全部アマゾンに行ってることでしょう。
ホールフーズのすべてのデータをアマゾンが獲得し、そのデータを元にして彼らが何をするのかが、今回の買収のキモなんです。
ウォルマートが大手消費財メーカーを集めての政策説明会で、EC向けには最低5ドル、できれば10ドル以上の商品を強化したいので協力して欲しいと要請したようです。
メディアが報じました。
単純に低価格の商品単体だと儲からないからですね。
細かいニュアンスが伝わってきていないのでどういう意図なのかははっきり分かりませんが、考え方としては2つあるでしょう。
1つめは高価格帯の商品を増やし、低価格帯の商品は絞る。ウォルマートのECは店舗と違って品揃えをロングテールまで拡大していく方針を採ってますから、高価格帯の商品を増やすことは戦略として当然です。
2つめはバンドル売り、例えば3ドルの商品は単体で売らず4つまとめて売る。この3ドルはユニットプライス比較でアマゾンよりも安ければ良いわけです。出荷段階でそういう商品形態にするようメーカーに要請したのかもしれません。
アマゾンによるシェア拡大を最優先した赤字戦略と一線を画す方向へ向かいはじめたように感じますね。
アマゾンゴーについてメディアにいろんな記事が載ってますが、勘違いが多いなあと感じていて、大切なことをちょっとだけこっそり書いておきます。
2つあります。
1つめは、レジがないことに焦点を当てている記事ばかりなのですが、このフォーマーットの革新性はゼロレジじゃないということ。
ウォルマートやクローガーはもうやってますし、中国でももうかなり一般化しはじめてます。
スマホでスキャンしアプリで決済すれば良いので、新しい技術ではありますが、とんでもなく難しいことでもありません。
恐ろしいのは実はノースキャンです。
天井に張り巡らされたカメラとセンサーと、棚に取り付けられたセンサーと重量計で、人と商品の動きを正確に追跡する。
これはかなり難しい。
できているのはいまのところアマゾンだけです。
ノースキャン+ゼロレジがアマゾンゴーの革新性なんです。
2つめは、エラーはゼロにはできないということです。
商品を持って出たんだけどカウントされなかったという話をSNSやブログで面白がって書いている人がいます。
一般の人ならいいですが、少なくとも業界人は思考が浅薄だということがバレますからやめておきましょう。
不明ロスは必ず起きます。
ゼロにするのは不可能です。
例えば納品率は96~97%ぐらいが最も効率が良く、日本のコンビニのように100%を求めると、サプライヤーが在庫を積み増さざるを得なくなって廃棄ロスが増大してコストがアップし全体効率は悪化します。
この場合、サプライヤーは取引価格にコストを転嫁しますから、最終的にそのコストを支払っているのは消費者と言うことになりますね。
つまり100%を求めることは必ずしも高効率というわけではないということです。
工業経営的な考えではしごく当たり前のことかなと。
アマゾンはエラー率をモニターしているはずです、絶対に。
単に技術だけを見た場合、このフォーマットのKPIはエラー率ですから。
このエラー率が、業界平均の不明ロス率近くになったか、または何らかの基準値に達したから、店舗を公開したのだろうと私は考えています。
私が責任者ならそうします。
そしてこのエラー率をゼロにしようとは思っていないはず。
非効率だからです。
目標にはするでしょうけど。
万引きをしようとしてこの店に入っても、万引きはできません。
でも、悪意のお客にも、善意のお客にも、等しい比率でエラーが起きて、ただで商品を提供してしまうことがある。
善意のお客はそういう意図がありませんから、偶然女神が降臨してエラーが起きて、ただで商品を手にしてしまうと、こりゃ面白いとなってSNSやブログで書くので目立ってしまう。
ということです。
店舗というものに不明ロスはつきもので、アマゾンゴーの認識技術にもエラーはついているのです。
ここで、「エラーが起きて商品がただで手に入った!」、と面白がっていてはしょうがないわけで、我々が興味を持つべきはエラー率がどのぐらいなのかということなのですが、最重要社外秘でしょうから残念ながらそう簡単に分かるはずがない。
どこからか情報が漏れ出てくるのを待つことにしましょう。
ウォルマートがバーチャルリアリティのプラットフォームとコンテンツを開発している企業を買収しました。
企業名はスペイシアランド、実際に買ったのはウォルマート傘下のストアNo8、ストアNo8はマーク・ロリー肝いりでスタートした新技術をR&Dする組織です。
ロリーは、VRがかなり近い将来買物で使われるようになる、そうなると買物環境が大きく変わる、とかねてから発言してまして、それを自社に取り込んでしまって研究を続けようというわけです。
専用のゴーグルをつけて、店内をバーチャルに歩き、気になる商品を手に取る。
ボタンを一つクリックすると、それを実際に使えるシーンにワープする。
例えばそれがペンキだったとして、バーチャルな世界で壁にペンキを塗って色合いを確認できる。
といったことが、夢ではなくてもうすぐそこまで来ていて、ウォルマートは自身で種をまきはじめたというわけです。
メイシーズが共通ポイントサービスのプレンティからの脱退を発表しました。
おそらくプレンティは業界をまたいだ共通ポイントサービスとしてはアメリカ唯一ではないかと思います。
プレンティは2015年にアメックスが核になって発足したものですが、今年の初頭までにHulu、ネイションワイド、エンタープライズ、アラモ、エクスペディア、AT&Tが抜け、サイトを見る限り残るは7社だけとなり、存続に黄信号がともりました。
日本では共通ポイントが流行ってますが、アメリカではそもそもポイントシステムそのものが販促の主流になっていません。
なので、共通ポイントシステムが広く普及する土壌がありません。
ポイントを溜めるのは日本人の習性のようです。
たぶん戦後から行動経済成長時にかけて国を挙げて貯蓄を奨励して、それが文化になってしまったからなんでしょうね。
ちなみにポイントシステム=ロイヤルティプログラムと理解する人が少なくないですが、双方は別物です。
ポイントシステムは販促の一手法に過ぎません。
このあたりは書くと長くなるので、また別の機会に。
アマゾンが第4四半期と通期の決算を発表しました。
最近は日本でもアマゾンの注目度が上がっているので報道されることが多くなり、ご存知の方ばかりかと思いますが、とりあえずエントリーしておきます。
売上高は1779億ドルで前年比31%増、営業利益高は41億ドルで2%減、最終利益高は30億ドルで28%増。
増収増益ですね。
特にこの企業の規模になって依然増収率31%は凄まじい。
まもなく連結でCVSヘルスを抜いて単独2位となり、ウォルマートに肉薄する段階に入っていきます。
ところで、メディアがアマゾンもとうとう増収増益が続いて儲かる会社になった、なんて内容を中心にして書いてますが、実は違います。
営業利益は落ちてまして、増益の理由はたぶん税制改革でしょう。
納税充当金が半分ぐらいに減ってます。
これがなければたぶん減益。
このあたりは公的な決算報告書が提出されればはっきりわかるでしょう。
何度かあちこちで書いていることですが、ジェフ・ベゾスは損益上に利益を出すか出さないかは戦略で決めると言ってます。
いまは意図的に利益を出す時期にあるだけで、いつかまた出さない財務戦略に転換するかもしれない。
これをいつ転換するかは、社外秘だから投資家にも言わない、と言ってますから。
今回のリリースを見てあらためて思ったのは、ベゾスは相変わらずキャッシュフロー重視なんだなということです。
リリースのトップに出てくる文言が、「営業キャッシュフローは7%増の184億ドルで・・・フリーキャッシュフローは84億ドルに減り・・・」で、まずキャッシュフローです。
ジェフ・ベゾスはキャッシュフローが強ければ損益上赤字でも問題なしと考える人です。
上場企業でこういう考えを長く変えずに維持し続けているのはアマゾンだけなんじゃないでしょうかね。
つまり、ベゾスにとっては損益上の黒字か赤字かは、あまり問題ではないのです。
メディアの皆さんは損益ばかり記事にしてますが、当のアマゾンが重視しているのはキャッシュフローだという、意識の乖離が存在します。
メディアも結局損益でしか企業を見ていないということです。
ちなみにフリーキャッシュフローが減った理由は投資が増えたことで、端的におそらくホールフーズでしょう。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
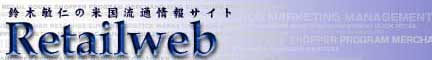



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS