ウォルマートが全店舗のレジ周りから雑誌のコスモポリタンを撤去すると報じられました。
昨今問題化しているセクハラ問題や#MeTooムーブメントの影響だろうとみられています。
ただし完全撤去ではなく売場の変更としていて、おそらく店の中央にある雑誌売場には置かれるのでしょう。
みんなが目にするレジ周りには置かないということのようです。
ウォルマート広報は、「そういう問題があることは知っているが、今回の決定は単純にビジネスからだ」と答えていて、セクハラ等々が理由ではないと説明しています。
デジタル化で紙の雑誌市場そのものが縮小していますし、そうすると店頭からまず落ちるのはこういうジャンルということなのでしょう。
ちなみに日本のコンビニにはエロ本が堂々と置かれてますが、あれはそろそろなんとかしたほうがいいですよ。
デパートメントストアのメイシーズが年末までを目途にして、全店舗にモバイル決済を導入すると発表しました。
お客はアプリで商品タグのコードをスキャンし、アプリ内で決済し、モバイル決済用のカウンターに行って買物を承認してもらい、タグを外してもらったり紙袋をもらったりして、終わり、というプロセスです。
最後に店員からの承認が必要となる点はウォルマートと同じ、店員とのコンタクトゼロで買物が終わるわけではないですが、アメリカはこれが今のところ限界ですね。中国のように顔認証でセキュリティを担保するということは、プライバシーの観点からいまのところアメリカでは不可能です。
日本のデパートメントストアがこういう技術をいつ導入することができるのか、ということを考えると、メイシーズはやはり早いですね。
ちなみに、「自分で商品をスキャンし、決済し、承認してもらう」というプロセス全体に要する時間と、「レジで並んで決済する」というプロセスに要する時間は、ひょとするとあまりかわらないかもしれませんね。
お客が能動的に自分でやることと、レジで受動的に待たされる感を持つことと、比較すると前者の方がお客は不満を持ちづらい、という点にこのモバイル決済の価値があるのかなと言う気がしています。
昨年に引き続き今年もアメリカ視察を実施します。
詳細は以下の通り。
アメリカ視察ツアー2018 ヒューストン
今回はデジタルな変革に焦点をあてています。
ウォルマート、ターゲット、HEBといった大手企業が中心ですが、リージョナルやローカルレベルの企業が何をしているのかも今回のテーマです。
小売企業だけではなく、小売企業と取引をしているメーカー、卸、その他のサプライヤーの皆さんにとっても、アメリカの流通業界を勉強する良い機会になると思います。
表面的なニュースレベルの話や、ただ店を見て歩くだけではなく、その裏側には何があるのか、取引、物流、システムなど、広範囲な知識をご提供いたします。
皆さまのご参加をお待ち申し上げます。
フィイブビロウが昨年度の決算を発表、売上高は12億8,000億ドルで27.8%増、最終利益高は41.5%増、既存店成長率は6.5%増で、絶好調でした。
今年の新店数は125店舗を予定。
この企業の特徴は対象をローティーンに絞り、全品5ドル以下で提供するというマーチャンダイジングの面白さにあります。
もうずいぶん前の成長を始める前に店を見て、そのユニークさに驚いて記事にしたことがありました。
当時はけっこう荒削りな店作りだったのですが、あるとき急に洗練されて、それから急速に店を増やし始め今に至っています。
まだまだ伸びそうですね。
トイザらスの破綻に代表されるようにどうしてもネガティブなニュースばかりを取り上げがちなのですが、しかし世の中悪い話ばかりではなくて、当然のことながら業績の良い企業もいるということを書いて、バランスを取っておこうと思い今日はあえてこの企業を取り上げました。
2月23日に2回目のライブトークを放映し、録画したものをYouTubeに掲載してあります。
株式会社ビッグ・エーの三浦弘社長をお迎えし、ディスカウントストアについて熱い議論を交わしました。
ぜひご覧下さい!
ちなみにライブはFBのタイムラインで流しています。
第3弾も考えていますので、ご興味のあるかたは私のタイムラインにご注目下さい。
ウォルマートが店舗発の宅配を本格的に開始すると発表しました。
店員が商品をピックアップし、宅配業者に渡して配達してもらう、というプロセスです。
宅配業者は買物代行企業や中小の宅配企業を利用、年末までに100都市、店舗数だと約800店舗での展開が目標。
これで全米人口の40%をカバーするとしています。
またNYでは同日宅配も開始するとしているのですが、買物代行企業を使うエリアでは2時間宅配も可能になるんじゃないでしょうか。
インストアピックアップ可能店舗が年内に2,100店舗になると昨年発表していました。
インストアピックアップを可能にするということはつまり店舗のフルフィルメントセンター化を意味します。
今回の発表の背景は、FC化店舗が過半数を超え、発送デポとして機能させる準備が整った、ということです。
2,100店舗とすると発表した昨年の時点でたぶん今年中に店舗発宅配を開始するだろうと予測し、セミナーや記事でそういうことを言ってきましたが、ヨミ通りとなりました。
マーク・ロリーは「アマゾンよりも我々の方が有利だ」と常々言い続けているのですが、その根拠がこれです。
ウォルマートは国内にすでに5,000を超える店舗をもっており、この店舗を発送デポとすると、新規投資してセンターを増やしていかねばならないアマゾンよりも低コストで宅配が可能になるというわけです。
とりわけ生鮮食品を含むコモディティにおいてウォルマートの方が有利になる可能性があると思っています。
先週中にも破綻するだろうと言われていたクレアーズが周囲の予測通りに連邦破産法11条の適用を申請しました。
負債の総額は19億ドル、そのうちの一部が3月15日に返済日を迎え、これを返す目処が立たないため破綻すると見られていたものです。
店舗数は米国内で1,440、グローバルでは3,000店舗を超えています。
日本ではイオンがライセンス契約で展開しているので、ご存知方も少なくないでしょう。
米国内の99%がモール内出店で、業績悪化の理由をモールの集客力低下に求めているのですが、資料を見るにマーチャンダイジングやプライシングに魅力が薄れてきているようで、原因は外部だけというわけでは無さそうです。
直接的なな理由はトイザらスとまったく一緒、投資企業アポロ・マネジメントによる2007年のバイアウトで借入金が膨れあがり、業績が落ちて利払いができなくなってしまったことにあります。
イオンはこれで、日本でパートナーを組んだ米小売企業として、スポーツオーソリティに次いで二社目の破綻ということになりました。
セミナー@博多、まもなく締切です。
お申し込み、お忘れなきよう。
『世界で同時進行するデジタル化の波、アマゾンはなぜ成長し続けるのか?』
デジタル化が世界中で同時進行し、グーグル、アマゾン、フェースブック等々と、海外のデジタル企業がグローバルに成長を続けています。なぜ彼らの成長は止まらないのでしょうか。小売業界はどう対処すれば良いのでしょうか。今回のグローバル流通最新トレンドセミナーは、アマゾンを主軸に据えてアメリカやヨーロッパの事例を解説し、皆さまのデジタル戦略の一助となる内容を提供します。
【日時】2018年4月20日 13:30開演(16:50終了予定)
【会場】アクロス福岡
福岡市中央区天神1丁目1番1号
092-725-9113
【講演者】S.M.R.Inc代表 鈴木敏仁
PwCコンサルティング合同会社 矢矧 晴彦
【受講料】12,000円(税込み)
【定員】40名
【申込締切】2018年3月20日【主催】株式会社R2リンク
【協力】株式会社未来創造学
詳細、お申し込みはこちらへ。
グローバル流通最新トレンド2018@福岡
アクセサリーのクレアーズの破綻が近いという噂が流れていたのですが、先に2社がバタバタと倒れました。
米トイザらスは日本でも報じられているのでご存知の通り、裁判所の管轄下で再建の道を模索してきましたが、債権者と折り合わず米国内資産をすべて清算だそうです。
しばしば指摘してきましたが、トイザらスの息の根を止めたのはアマゾンではなくて、バイアウトによる過剰な負債にあります。
アマゾンはウォルマートやターゲットといった競合の一社に過ぎません。
もう一つはサウスイースタングローサーズで、こちらは再建プランをあらかじめ策定しての連邦破産法11条の適用申請なので、トイザらスのように全店閉鎖ではありません。
ウィンディキシー45店舗、ハーヴェイズ26店舗、バイロー22店舗、フレスコ・イ・マス1店舗、を閉店して、残りの582店舗で存続するそうです。
法的処理で、リースを踏み倒すか、または条件を強制的に修正するんでしょうね。
こちらもけっこう前から破綻が囁かれていたので、サプライズというわけではありません。
破綻の理由はアマゾン・・・ではなくて、パブリックスやハリスティーターといった正面からぶつかる競合に負け、スプラウツやアルディという新種の競合が売上を伸ばし、とリアルで勝てていないことなのですが、こちらもまたトイザらス同様長いこと負け続けて弱った会社の集合体なので、今回負債を減らし再出発と言ってもそう簡単に復活というわけにはいかないでしょう。
毎年のことながら、アメリカは年初に破綻が多いです。
ちなみにダラーゼネラルが今年900店舗を新規出店すると発表しています。
トイザらスとサウスイースタングローサーズ両社合わせると800店舗強が閉店しますが、それを上回る店舗をダラーゼネラル一社がオープンさせるので、単純に店舗数でカウントすると実はプラスということになるんです。
靴のチェーンストア、DSWが2年前に買収で手に入れたEバイズ社を清算すると発表しました。
買収したのは2016年で総額は6,250万ドル、昨年度の決算ですでに7,270万ドルを減損処理しているそうです。
経営陣を入れ替えて立て直しを図った、と書いてあるので、旧経営陣をオリジナルのポジションに数年の間しばる条件をつけていなかったのかもしれませんね。
または何らかの事情で条件をクリアした上で去ってしまった。
普通は3年間はやめないでそのまま会社を運営することを条件にします。
でないと、大金を手にした創業経営陣がすぐにやめてしまって、会社が動かなくなってしまいますから。
買収してからわずか2年で廃業というのは、スピード感があって素晴らしいと言えば良いのか。
小売業のECは自前と買収の二軸戦略が基本なのですが、こういう大失敗例もあるという話でした。
健康保険大手のシグナがエクスプレス・スクリプツを買収すると先週半ばに発表しました。
総額は670億ドルで、CVSヘルスによるエトナ買収提案690億ドルに肉薄しています。
これはもう明らかに、CVSによる買収ディールに対するカウンターパンチです。
その昔、ウォルグリーンがエクスプレス・スクリプツと取引条件で折り合わず取引停止したときに、エクスプレス・スクリプツのCEOが極めて強気で上から目線のコメントをしていて、パワーバランスがPBM側に傾いていることを感じたものなのですが、そのエクスプレス・スクリプツが買収される道を選んだわけで、CVSによるディールはそれぐらいインパクトがあるということになります。
ちなみにCVSヘルスによる買収ディールは、ドラッグストアのCVSが健康保険会社のエトナを買収するとみると分かりづらいですが、CVS傘下のPBM企業のケアマークがエトナを買収すると理解すると分かりやすいでしょう。
ケアマーク(PBM)→エトナ(健康保険)=PBM/健康保険
シグナ(健康保険)→エクスプレス・スクリプツ(PBM)=健康保険/PBM
右と左が入れ替わっているだけです。
CVSもシグナも買収目的はヘルスケアのコストダウンとしているのですが、競争減でたぶん逆方向に向かうだろうなと私は思っています。
アマゾンになんとかしてもらうしかないですね・・・(笑
以下のスケジュールでセミナーを開催します。
ふるってご参加下さい。
『デジタルが変える経済社会、グローバルな変化をローカルに考える』
デジタル化が世界中で同時進行し、グーグル、アマゾン、フェースブック等々と、海外のデジタル企業がグローバルに成⻑を続けています。しかしながら消費者の嗜好は逆にローカライズ化を強めており、ローカル企業にはチャンス到来と見ることもできます。本セミナーでは、グローバルなトピックを取り上げながら、ローカル企業の取り組み課題について考えてみます。
日時:2018 年4 月17 日 13:30 開演(17:00 終了予定)
会場:福井商工会議所 地下1F コンベンションホール
福井市⻄⽊⽥2丁目8−1
講演者:S.M.R.Inc代表 鈴木敏仁
PwCコンサルティング合同会社 矢矧 晴彦
上坂会計グループ代表 上坂朋宏
受講料:1名様 20,000 円(税込み)
定員:100名
申込終了日:2018 年4 月17 日 09:00
主催:上坂会計グループ
詳細、お申し込みはこちらへ。
「グローバル流通最新トレンド」2018福井
ウォルマートは昨年末からネット上でミールキットを売り始めましたが、店舗での販売も開始すると発表しました。
250店舗からスタートし、年内に2,000店舗へと拡大する予定。
ネットで実験し、店頭へ拡大というわけです。
ネットは店頭展開に比較するとコストが安いですし、データが取れますから、小売だけでなくメーカーも実験場として利用していますね。
クローガーがすでに店頭販売を開始していますが、トレンドの最先端には乗らないディスカウントストアのウォルマートが参入したことで、この市場がけっこう大きくなってきていることを示唆しています。
ブルーエプロンやハローフレッシュといったネット企業がミールキット市場を顕在化したわけですが、店頭でも十分に売れる商材でしょうから、これからリアルがネットから奪っていくという図式となりそうです。
コンビニと提携すると言っていたコールズですが、アルディと組んで実験すると発表しました。
コールズはすでにアマゾンストアをインストア展開しています。
衣料の売上が厳しくなってきて売場に余剰が生まれ、これを有効活用するために他社にスペースを貸してしまうという戦略をコールズが取り始めていて、最初に組んだのがアマゾンで、次がアルディということになります。
衣料を売るコールズの店内にアルディが存在するという絵がなかなか頭に浮かびません。
ハードを売っているアマゾンと違い回転数の多い食品を売るアルディの場合は一定規模のバックルームも必要になるでしょうし、ゾーニング上どこにはめ込むのかという非常に素朴な興味が湧いてきますね。
見に行きやすいところで実験してくれるといいんですが。
ちなみに実験は10店舗だそうです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
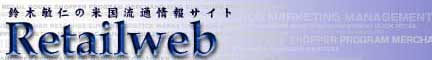



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS