スタインヘイフェルの突然の解雇の後、次のCEOを探していたターゲットが、ペプシのブライアン・コーネルに白羽の矢を当てました。
ダラーツリーのファミリダラー買収もそうでしたが、ああなるほどこういう人がいたのかと。
マーケティング畑の人なのでターゲットの戦略性に確かにマッチします。
コーネルの現職はペプシ北米食品事業の責任者ですが、その前がサムズのCEOでした。
[ウォルマート] ブライアン・コーネルがサムズのトップに
[ウォルマート] サムズCEOのブライアン・コーネルが退任
ペプシ→セイフウェイ→マイケルズ→サムズ→ペプシ→ターゲット
典型的なジョブホップ型のキャリアを持った人です。
果たしてターゲットで長続きするかどうか・・・
ダラーツリーがファミリーダラーを買収することを発表しました。
買収総額は85億ドルの予定。
アクティビスト型投資家のカール・アイカーンがファミリーダラー大株主となったのが5月、先月には資本の売却を公的に迫り、ファミリーダラー側は対抗策としてポイズンピルを導入するなど、ここ数ヶ月ファミリーダラーは株主とつばぜり合いを繰り広げていました。
アイカーンはダラーゼネラルかまたは投資企業への売却を考えていたようなのですが、ダラーゼネラルが興味を示しておらず、アイカーンが次にどういう手を打ってくるのかという段階だったのですが、逆にファミリーダラーの方が大きく動いて攻撃をかわした、というのがストーリーとなります。
ダラーツリーはシングルプライス型でマルチプライスのファミリーダラーとはビジネスが異なるので、私自身も想定していなかったディールで、正直驚きました。
両社合わせると店舗数は1万3,000超、売上高は180億ドル・・・ダラーゼネラルの1万1,000超、175億ドルを超えます。
おそらくFTCが介入してきて店舗の売却もあると思うので、売上と店舗数は拮抗する、というところでしょうか。
買収後も店舗名はそのまま、ファミリーダラーCEOのハワード・レビンがダラーツリーCEOボブ・サッサーの下につき、レビンは取締役に加わる、が新たな組織構成のようなので、ファミリーダラーはとりあえず独立組織として動くようです。
興味深いのはバイイングパワー、具体的にはプライベートブランドですね。
ファミリーダラ-にダラーツリーのPBが入ってくる可能性は高く、いまでも強いダラーツリーの商品力や調達力がさらにてこ入れされることになるのでしょう。
けっこうインパクトの大きなバイアウトディールだと思います。
ターゲットが小型フォーマットの実験店舗をオープンさせました。
場所はミネアポリスの大学街、面積は2万sqf(563坪)、7月23日がソフトオープンで、正式なグランドオープニングは27日です。
名称はターゲット・エクスプレス・・・
ウォルマート・エクスプレスと完全に被ってますね。
ひねりがなくて、ターゲットらしくないです。
こちらが店内ツアーの動画。
価格戦略が分からないので今の時点ではなんとも言い難いフォーマットだなと思います。
ウォルマート米国事業のCEO、ビル・サイモンの辞任が発表されました。
後任は中国事業部門CEOのグレッグ・フォラン。
昨年の11月に書いたとおりビル・サイモンの辞任は予想通りなのですが、後任には少々驚きました。
これが昨年の記事。
[ウォルマート] 次期CEOにダグ・マクミロンを指名
フォランはオーストラリア出身、ウールワースの上級役員を最後に2011年にウォルマートに移り、2012年に中国事業の責任者となっています。
入社して3年でウォルマート最大部門を任されるというわけで、想定外でした。
ちなみにこの間の上司が現CEOで当時は海外事業のCEOだったマクミロンです。
おそらくこの間にマクミロンがフォランを気に入ったということなのでしょう。
フォランのキャリアを見る限り、政府関係組織やメーカー出自のサイモンとの違いは、最初から小売業界にいる人だ、という点です。
ウォルマートが最初ではないですが、たたき上げではあります。
壁にぶつかっている米国事業を上向かせることができるのか、手腕に注目ですね。
スターバックスが年内に一部の店舗でアプリを使ったモバイルオーダーの実験を開始します。
お客は店舗に行く前にオーダーできるので、待ち時間を短縮できるというシステムですね。
全店水平展開をすでに前提としているようで、失敗するかもしれないといういわゆる実験とは異なるようです。
外食ではピザハットがアプリを使った注文システムをすでに導入してますが、もともと電話をかけて事前に注文するビジネスモデルで、それをアプリに置き換えただけなので、革新性はないですよね。
店舗でセルフで注文してすぐに食べるという、ファストフード系でははじめてじゃないでしょうか。
例えばiBeaconsとからめて、店舗の入り口を通ると感知して、それから注文を作り始める。
お客はカウンターでちょっと待つだけ。
これならレジで注文せずに、温かい商品を受け取れます。
ファストフード業界で普及して仕組みがこなれると、例えばスーパーマーケットが総菜でアプリ注文を事前に受け付ける、というようなことが可能になってくるのかもしれません。
この実験は将来性を感じます。
ただし売る側としては弱点があるんですが、この話はまた別の機会に。
今日はイギリスのニュースを。
テスコのCEOフィリップ・クラークが辞任し、ユニリーバのパーソナルケア部門トップのデイビッド・ルイスが後任となる人事が発表されました。
ルイスの着任は10月で、それ以降来年の1月までクラークはアドバイザーとして残るとのこと。
社外からCEOを雇うのは最初のことだそうです。
クラークがテリー・リーヒーの後を継いだのは3年半前のことでした。
ちょうどこの頃からテスコの業績が悪化しはじめたのですが、たぶん分かっていて経営交替したんでしょうね。
自分の能力ではここまで、とリーヒーが見切りを付けて、将来を後任に託したということだと思います。
でもクラークはそれに応えることができなかった。
リーヒーの後任として荷が重すぎたと言うことなんでしょうかね。
興味深いのは、小売業界ではなくメーカーから経営者を持ってくる点。
ホームデポがGEから経営者を持ってきて失敗した事実を思い出してしまいます。
小売とメーカーはビジネスの基本的な部分がかなり異なるので、簡単ではないです。
よくアメリカ的な"経営のプロ"が日本にも必要、なんて言葉をよく聞きますが、そんな甘いもんじゃないです。
レイバーの横の移動が激しいアメリカでさえも、どこに行っても経営できちゃうような専門家なんて、ほとんどいません。
ちなみにリーヒーがテスコを去ってから、リーヒーを支えた経営層のほとんどがやめちゃっているそうなので、人材的にテスコはけっこう厳しい状況にあるようです。
米アマゾンが電子書籍の定額サービスを開始しました。
月額は9.99ドル、書籍60万タイトルとオーディオブック1,000タイトルが対象で、アマゾン以外のモバイルデバイスでも利用可能。
電子書籍の定額サービスの開始はだいぶ前から既定路線で、いつはじめるのかという状況でした。
おそらく出版社との契約の調整に時間がかかったのでしょう。
大手出版社のアシェットがアマゾンと電子書籍のプライシングで現在もめていて、電子書籍は出版社にとってはまだまだ取り扱いづらい分野です。
これでエンターテインメントカテゴリーで、音楽と動画に書籍が加わったというわけですね。
最後のゲームはたぶんアマゾンファイヤーTVでやるだろうと思われ、これも時間の問題ではないかと思います。
CVSがフロリダに本拠を置くナバロ・ディスカウント・ファーマシーの買収を発表しました。
買収総額は未発表、買収後も店舗名は変えないで営業を続けるとのこと。
ナバロは33店舗で年商3億4,000万ドル、ヒスパニック商圏に特化したドラッグストアです。
CVSの規模からすると小さな企業で業績に対する影響度は低いでしょう。
アメリカのドラッグストアチェーンは3位のライトエイド(255億ドル)に次ぐのがキニードラッグ(8億2,900万ドル)で、それ以下はバーテルドラッグ(4億800万ドル)やこのナバロといった売上高500億ドル以下のチェーンのみとなってしまっています。おそらく5社ぐらいしか残っていないので、これを買収するというのは、寡占状態を通り越して超寡占状態へ向かっていると言えるのかもしれません。
ちなみに、調剤、HBC、雑貨というドラッグストアが扱っている商材そのものは、ウォルマート、ターゲット、コストコ、スーパーマーケット等々と激しく競合していて、業態は寡占ですが、ビジネスは寡占にはほど遠いとういうのがアメリカです。
アマゾンが無人機宅配のテスト飛行をFAA(連邦航空局)に公式申請しました。
同社がプライムエアーと呼ぶ無人機を使った宅配の構想を発表したのが昨年末のことでした。
時期が時期だけにあれは確実にメディアの注目を集める目的だったわけですが、構想自体ははったりなどではなく、アマゾンは真剣に検討しています。
ただ無人機の商用使用には規制がある。
当たり前ではありますが、市民の頭上を無人機が飛び回ることにはリスクがあって、規制なしというわけにはいかないわけです。
アマゾンの主張は、空港、軍事基地、人口密集地、といったリスクの高い場所から遠い地域で実験するから、実験を許可しろ、です。
FAAが許可するのかどうか。
個人的には、宅配トラックが行けないよう場所(山奥等)、採算が合わない場所(過疎地等)で、緊急を要するアイテムを運ぶには最適なのではないかと思っているんですが、どうでしょうか。
この1年ぐらいの間にネット販売で創業した企業によるリアル店舗の開発が続いています。
主なところで、Bonobos(メンズウェア)、Warby Parker(アイウェア)、そしてBirchbox(コスメ)の3社。
最新がBirchboxでNYマンハッタンにオープンしたばかりです。
ネット販売企業によるリアル店舗への進出は、諸刃の剣ではないかと思います。
アマゾンが好例ですが、姿が見えないからこそ創出できるイメージがあるわけです。
しかも100人いたら100種類のイメージがある。
リアルな店舗が目の前に表れると、そこでのイメージに固定されてしまいます。
一方、リアルな店舗があることによる安心感を消費者に与えることができるというメリットもある。
サービスやセキュリティ等々。
アマゾンが店を作るんじゃないかという噂が定期的に出ては消えをくり返しているのですが、おそらく作ることはないでしょう。
理由が見つかりません。
消費者がそれぞれ頭の中に描いているイメージを壊す必要はない。
でもできたら面白いだろうなとは思いますけどね。
CEOを探しているリテール企業が現時点で9社あると業界誌が報じていました。
気づかなかったのですが、言われてみるとなるほどそうだなと。
ターゲット
JCペニー
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ
ビービー・ストアズ
ボントン・ストアズ
ダラーゼネラル
アメリカン・アパレル
ゴードマンズ・ストアズ
LLビーン
当然人材不足に起因しているのですが、原因は2つでしょう。
1つめは人材開発がおざなりになりがちなこと。アメリカは人材の流動性が非常に高く、教育投資がしづらい環境があって、自社内で優秀なリーダーを育てきれないんでしょう。
2つめは行き過ぎた株主資本主義、投資家が短期的な結果を求めるため、経営者は解雇されやすく、短期決戦のリスク回避のため経営者の俸給は高騰し、短期的な利益確保を目的としたリストラによる人材流出が起きやすい。
まあ、人材の流動性が低く株主資本主義が途上にある日本でも人材は不足しているので、いずれにしても優秀な人材はそう簡単には見つからないというのは洋の東西を問いませんけどね。
日本の場合、優秀じゃなくてもとりあえずところてん式に順番に社内で社長に昇格させてしまう風習がありますから、経営者を探す企業がアメリカに比較すると少ないのかもしれません。
DVDレンタルのボリュームは6年連続で前年を下回っており、5年以上下降している市場で事業が安定したビジネスは過去40年間存在しないとして、レッドボックスを展開するアウターウォール社の格付けをランクダウン。
レッドボックスは小売店舗の入り口周辺に設置されるレンタルビデオの自動販売機ですね。
何回かここでも書いているのですが、一番古いのはこのあたりかなと。
[ブロックバスター] ビデオレンタルビジネスはどこへ行くのか?
レッドボックスの強みは1ドル/1泊(借りた日の翌日の21時まで)という安さと、セルフという気軽さと、小商圏リテーラーの出入り口という利便性という3つにあるのですが、とりわけやはり1ドルという安さが一番でしょうね。
一気に支持されて、実験の開始の2002年からおよそ10年間で4万2000ヶ所にまで成長しました。
このレッドボックスがブロックバスターを潰したと言っても過言ではないです。
ただ上記の昔のエントリーですでに行き先不透明と書いてあるように、ストリーミングに移行してゆく中でフィジカルなDVDレンタル市場の縮小は不可避で、レッドボックスも必ず壁に当たると予測されていて、これがそろそろ現実味を帯びてきたというわけです。
レッドボックスの頭上にいきなり暗雲が垂れ込めてきた、という感じですかね。
ちなみに日本でもどうかという話をよく相談されたりするのですが、100円が実現できるのかどうかがカギでしょう。
クローガーがネット販売企業を買収すると発表しましたあ。相手はヴィタコスト・コム(Vitacost.com) 、サプリメントを中心にして、ナチュラル系のビューティや食品も取り扱っている上場企業です。買収額は2億8,000万ドル。
ヴィタコストの創業は1994年、もともとサプリメントのカタログ販売だったのが1999年にネット販売を開始して、こちらが伸びて2009年に上場、ただそれ以来赤字を計上していて、投資家からの要請で買収相手を探していたという経緯があるようです。
この買収の面白さは、非食品主体のネット販売企業をスーパーマーケット企業が買うところにあります。
クローガーは非常に長い期間好調をキープし続けている優秀な企業ですが、その理由の一つが非食品です。
市場の大きな伸びが見込めない食品から外に向かっていってラインロビングしたところに、長い売上成長の理由の一つがある。
当然のことながらウォルマートという非食品出自の企業が食品を奪いはじめたことに対して、対抗手段として非食品を奪っていったというモチベーションもあったことでしょう。
食品オンリーで閉じてしまっている日本のスーパーマーケット業界との決定的な違いだと考えています。
ちなみにクローガーによるEコマースの取り組みは遅れていて、傘下のキングスーパーで実験しているのですが、芳しくないようです。
買収したハリスティーターも取り組んでいるのですが、そのノウハウを本体に取り込むということもいまのところやってません。
ヴィタコストを買収して、これがクローガーのEコマース戦略にどういう影響を与えるのか、注目したいところです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
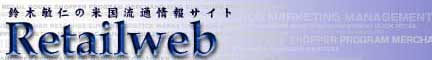



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS