JCペニーがセフォラと契約したのが2006年で、それ以来インストアショップは500店舗超となっています。
これに25店舗をさらに加えて拡大することを発表しました。
JCペニーはコスメが弱いんですよね。
だからざっくりとセフォラを店内に入れてしまう手を選んだ。
今回の拡大発表はこれがうまくいっていることを表しています。
セフォラ型のプレスティージビューティを売るセルフの専門店チェーンが日本に存在しないのが残念なのですが、例えばGMSあたりはセフォラのような店舗をテナントとして入れてしまうほうがいいのではないかと思ってます。
アマゾンが3年間実験していた法人向けのマーケットプレイスを、正式にスタートさせることが分かりました。
名称をアマゾン・サプライからアマゾン・ビジネスに変えて、サプライヤー数を大幅に増やし拡大するとしています。
これで影響を被るのは、ステープルズとコストコ(やサムズ)、といったところでしょうか。
法人は市場が大きいですから、ポテンシャルも大きい。
マーケットプレイスでまずは参入という点は、いかにもアマゾンらしいですね。
クローガーが英テスコ傘下のダンハンビーと合弁でアメリカに設立した企業がダンハンビーUSAで、これがクローガーのロイヤルティプログラムをアウトソーサーとして作り上げたという話はご存知の方も多いことでしょう。
設立は2003年、資本は50%ずつの折半でした。
このダンハンビーUSAの残りの資本の大半をクローガーが買収し、社名を84.51°に変更するという発表がありました。
現存するダンハンビーUSAが社屋や社員も含めてそのまま丸ごと新会社に移行するようです。
84.51°とうい社名の由来は本社の経度だそうです。
しゃれてますね。
わたしはてっきり台湾の85°のパクリかと思いました。
85°は一番美味しいコーヒーの温度だそうです。
ダンハンビー自体は残り社員数十名の企業となって、84.51°社に対してツールの使用料等を徴収するような企業として存続するようです。
ひょっとするとクローガー以外の小売企業のロイヤルティプログラムを請け負うということをするのかもしれませんが、詳しいことは分かりません。
このダンハンビーUSAの消滅は、テスコの業績悪化が関連しているのでしょうね
1月にはダンハンビーの売却を検討していることが明らかになっています。
一度ダンハンビーUSAの本社でいろいろ話を聞いたことがありますが、ここまでやっているのかと舌を巻くようなレベルでした。
クローガーも好業績の原因の一つだと言っていた時期がありました。
ただどこまで影響があったのかというとよく分かりません。
データ分析の結果を踏まえてアソートメントを改善したという情報もあったのですが、よくある話のレベルで、どこが凄いの?と肩すかしを食らったこともあります。
ちなみに84.51°はメーカーに対してデータ分析アウトプットを販売する企業として存続してゆくようです。
リストラを進めているP&Gがビューティブランドの一部の売却、または上場してのスピンオフを検討しているとメディアが報じました。
P&Gのビューティブランドというと、カバーガール、SKⅡ、オレイ、パンテーン等々いろいろあるのですが、フレグランスやヘアケアの可能性があると指摘されています。
ウェラの売却プランはすでに公式にリリースされていますね。
P&GはCEOアラン・ラフリーの下、現在リストラが進められているのですが、彼ががやっていることはアイテム数の削減です。
選択と集中ですね。
私の記憶では、最初にCEOになったときもブランドをいったん減らしたんじゃなかったかな。
今回彼がやっていることが高く評価されているのは、一度自分で作り上げたブランドポートフォリオを自分で分解している点にあります。
足すのは簡単だけど、引くのは難しい。
これを両方できる経営者はほとんどいないというわけです。
私も本当にそう思います。
地味な人なので特に日本ではあまり知られていませんが、ラフリーは名経営者と評されて良い人だと思っています。
ウォルマートがテキサス州やカリフォルニア州の5店舗をこの月曜日に突然閉鎖しました。理由は店内の改装、とくに下水の工事を実施するとしているのですが、事前通告がなかったことや、最低でも6ヶ月はかかるとしていて工期が長いこと、通常は営業しながら改装するものであること等々から、意図があるのではないかとメディアが話題にしています。
例えばロサンゼルス近郊の店舗も閉鎖されたのですが、食品労働組合が反ウォルマートキャンペーン時に店の前で真っ先にデモを実施したりして、組合寄りと目されている店舗なんですね。
つまり組合運動に対する対抗処置の可能性があるとメディアは見ているわけです。
もちろんウォルマートは否定しています。
ただこの企業には過去があります。
組合結成の動きがあると店を閉鎖してしまうという手法は、アメリカ国内では何回か取ってますが、確かカナダでもやっているはずです。
ハードなスタンスはほんとうにウォルマートらしくて、メディアの指摘も単なる憶測ではないような気がしています。
ターゲットがリリー・ピュリッツァーの廉価バージョンを期間限定で発売したところ、サイトがパンクして2時間不通となり、店頭でもあっと言う間に売り切れたというニュースが話題になっています。
リリー・ピュリッツァーはカジュアルでカラフルなデザインで有名ですが、流行ったのが30~40年前で古めの高級ブランドですね。
20年ほど前に創業者から企業がブランドを買収して復活させ、専門店やデパートメントストアで展開しているというのが現状です。
今回のような売れ方をするのは久しくなかったようで、ターゲットのマーケティング技術がまだ錆びていないということを見せつけた格好となりました。
マンハッタンでポップアップストアをオープンさせたりといつものターゲットらしいマーケティングを事前に展開したようで、その結果店頭でも朝6時からお客が並んであっという間に売り切れたそうです。
ただ問題はネットのパンク。
需要を読めなかったは言い訳にならない。
[ターゲット] ミッソーニの独占販売でサイトがダウン
同じ事をくり返しているわけです。
ターゲットはまだ大丈夫だということを証明しつつ、でもいまだにネットは弱点だということも証明してしまったのでした。
アマゾンが無人航空機(ドローン)を使った宅配の実現を模索していることはご存知のことと思います。
名称はアマゾン・プライム・エアーですね。
アメリカのFAAによる認可プロセスが非常に遅いためここでは動きが見えないのですが、実は規制が緩い海外ですでに実験をしています。
開発センターはイギリスとイスラエルに置き、テストフライトはカナダとインドで実施しているとのこと。
アメリカでこのまま遅延が続くと、導入されるとしたら最初は海外になるだろうとみられています。
さてこのドローン、トラックによるデリバリーよりもコストが安いという分析資料を読んで、軽い衝撃を覚えました。
2キロ程度の重さのパッケージとして、注文から30分以内の配達時間でコストは0.14ドル程度となるので、送料1ドルとしても1年ぐらいで損益分岐点を超えだろうと試算しています。
トラックによる配達インフラの構築にかかる投資コストよりも、ドローンによる配達インフラの方が低いというわけです。
試算のベースが不明なのですが、言われてみるとそうかもと。
圧倒的大多数の人たちは、無人機による宅配なんて・・・(笑)、で済ませていると思うのですが、実現の可能性は意外と高いのかもしれませんね。
2020年までに500億デバイスがネットにつながり(現在は150億デバイス)、今後10年間で1兆ドルの価値を創造するという分析レポートが発表されました。
レポートのスポンサーはDHLとシスコです。
1兆ドルの価値は、イノベーションによる売上増、資産の有効活用、サプライチェーンとロジスティックスの効率化、従業員の生産性の改善、店舗環境の改善、の5つの要因によるもので、それぞれの積み重ねで1兆ドルになる、というロジックですね。
スポンサーがロジ系なので、サプライチェーンとロジスティックスの効率化による恩恵が大きいと強調されているのですが、パレットやアイテムがネットにつながっていくという内容は興味を引きました。
アイテムについては、RFIDでアパレルなどの高荒利益アイテムは10年以内につながる可能性が高いですが、消耗品についてはどうなのかなとは思います。
でもパレットは確実につながるでしょうね。
トラックはもうつながっているわけですが、資料ではドライバーもつながるとあります。
サプライチェーン上で、アイテム、パレット、トラック、ドライバーがネットにつながる。
これで何かが起きるわけなんですが、何がどうなるのかは想像がつかない。
アマゾンとInternet of Things
このように想像を超えるイノベーションがこれからもたらされる可能性があると思っています。
先週ウォルグリーンが第2四半期の決算を発表、そのときに200店舗をクローズする予定であることを明らかにしました。
これは2017年までに達成しようとしているリストラの一環で、その他、組織の改編や情報インフラのアップデートが含まれています。
リストラの目標は15億ドルのコスト削減です。
企業統合は、重なっている組織やサプライチェーンの再編でコストを削減しないと意味がありませんし、それを統合前にうたいます。
これをきっちり実行することが肝要。
企業は大きくなると無駄が増えますから統合をきっかけにしてそういう無駄をばっさりと切っていく、逆に言うとばっさりと切るために統合する、とも言えますね。
そういう意味でウォルグリーンは統合後もやるべきことをきっちりやっていると言えるでしょう。
ちなみにウォルグリーンの店舗数は8,232店舗で、年間に3桁出店を続けていますから、200店舗の閉鎖は大きな数字というわけではありません。
もうひとつちなみに経営層はごっそりブーツになってしまったので、このリストラもすべてブーツ主導で行われているということは背景として理解しておきたいことだと思います。
FMI(食品マーケティング協会)がクレジットカード会社に対して、決済システムのEMV対応への期限の延長を要請しました。
今年の10月だったものを来年としたいというのがFMIの意向で、理由は対応しきれていない企業たくさん残っているから。
法的問題が生じますから、小売側としては公的に認めてもらわないと困るわけです。
一方のクレジットカード企業は延長を認めていないようで、軋轢が生じています。
ウォルマートはシステムの変更は終わっていて金融側からの要請に応じているのですが、EMVに対しては否定的なスタンスで、「これがハッキング対策になるとは思えない、ジョークだ」と公的に発言しています。
このニュースでわかることはアメリカの小売企業とクレジット企業は相変わらず敵対しているということですね。
データ漏えいへの対策はいまだにクリアになっていません。
昨日アマゾンがアマゾン・ダッシュ・ボタンという、ボタン一つで商品を注文できてしまうデバイスを導入したという記事を書きました。
3/16には2lementryというIoT関連の企業を買収したという記事をエントリーしました。
そして、この2つはくっついてしまうということに気づきました・・・
例えば洗濯機にボタン機能をあらかじめ組み込んでしまう。
洗剤がなくなったらボタンを押して注文終了。
例えば冷蔵庫に、卵用ボタン、ミルク用ボタン、オレンジジュース用ボタン。
洗浄便座のコントロールパネルにトイレットペーパー用ボタン。
機械がない場合のみボタンを使う。
バスルームや洗面台のあたりに、ヘアケア、ひげそり、ボディソープ等々のボタンを並べておく。
実は家電に注文ボタンを組み込むという話は、アマゾンはもう取り組んでいるんです。
名称はDash Replenishment Service。
家の中のモノがIoT化でどんどんネットにつながっていくと、こういうことになるというわけなんですねえ。
アマゾン、恐るべし・・・
アマゾンがまた新しいプログラムを投入しました。
名称はアマゾン・ダッシュ・ボタン、小さなデバイスについているボタンを押すと注文が完了するというアイディアです。
ブランドごとにデバイスがあって、例えば洗剤のタイドのデバイスを洗濯機にでもつけておいて、なくなりそうになったら押して注文できるという仕組み。
アマゾンのサイトで見る限り多数の大手メーカーが参加していて、アイテム数は180ぐらいあるようです。
面倒なコモディティの繰り返し購買のハードルをなくすことが目的なのですが、発想があまりにもユニークで驚きました。
これ、成功するのかどうかは分かりませんが、とにかく新しい何かを絶えず投入して挑戦するアマゾンには学ぶべき点が多いと思っています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
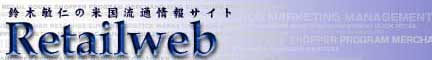



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS