ウォールストリートジャーナル紙がおもしろい記事を載せていました。タイトルは「売上消滅の謎」、売上が下がっている理由はデジタル本へのシフトと言われるが、店頭のマーチャンダイジングにも理由があるのではないか、どちらが本当なのかよく分からない、という内容です。
バーンズ&ノーブルはここ数年店頭の書籍の品揃えをどんんどん絞ってまして、空いたスペースにボードゲームや玩具を代替として置いています。
これによってさらに客離れが起きているのではないか、ひょっとしたら在庫を増やせば売上が伸びるのではないか。
ということを関係者のインタビューなどを交えながら書いてます。
もっともよく分かっているのはリテーラー自身のはずなんですが、でもいま市場はすごいスピードで動いていますから、実はあまり分かってないのかもしれませんね。
ちなみに昨年度の既存店成長率は-3.4%、今年度はこれが二倍程度になると予測していて、同社の業績は悪化中です。
アルディがロサンゼルスへの進出を検討しているようです。
郊外に本社兼配送センターのロケハンをしており、自治体に書類を提出していて、これがメディアに漏れた模様。
アルディは不動産探しの初期段階であることを認めています。
センター建設から入るとなるとまだしばらく先のことになりそうですが、ロサンゼルスにアルディがお目見えする日がどうやら確実に来るようですね。
バーンズ&ノーブルが第4四半期と通年の業績を発表したのですが、あわせてヌック事業の戦略を転換しタブレット端末から撤退することを明らかにしました。
ヌック事業の通年の売上高は7億7,600万ドルで16.8%減、デバイス売上高は減ったがコンテンツ売上高は16.2%増、ただしコンテンツはデバイス不調の影響を受けて第4四半期に8.9%減でした。
この結果により、電子ブックの販売は継続するが、タブレット端末からは撤退することを決めたというわけですね。
資料を読み込むに、赤字でも売り続けてシェアを増やすという資金力に欠けているというのが撤退の理由のようです。
つまり逆に言うと、アマゾンはたぶん赤字か利益なしで売り続ける余裕があるということになります。
アマゾンは検索推奨エンジンやフルフィルメントの技術が業界標準よりも高いとされてますが、その土台となっているのが潤沢なキャッシュです。
投資できなければ技術も進化させられません。
この潤沢なキャッシュの元になっているのは...最近私が立てていた一つの仮説が正しいと言うこと分かりまして、キャッシュリッチな理由が判明しました。
普通の小売モデルではないですね、アマゾンは。
これについては最近セミナーでは話し始めているんですが、どこかで書くかもしれません。
バーンズ&ノーブルは書籍チェーンで普通のリテールモデルですから、普通に対抗して勝てるわけがない。
ヌックはマイクロソフトが買うという話がありましたが、デバイスからの撤退で可能性はかなり低くなったんじゃないでしょうかね。
連結の業績も良くないですし、けっこう大変なところに来ていると思います。
ベストバイが店内にミニ倉庫スペースを作り、ネット販売で売れた商品を店舗から発送する取り組みを開始するそうです。
資料には既述がないのですが、倉庫には店頭在庫商品以外の商品をおいて、店頭商品と合わせてアイテム数を増やし、ネット販売に対応するということなんでしょうね。
ネット上では欠品しているのに店頭には商品がある、こういう問題を解決するためだと同社幹部がコメントしています。
ベストバイは広い売り場をもてあましていますから、空いているスペースを有効活用するという意味もあるのでしょう。
ネットと店頭を分けず一つに統合した状態をオムニチャネルと表現することがありますが、このオムニチャネルの本質は在庫問題です。
ネット販売用の配送センターと店頭の在庫、価格、販促をシンクさせる。
これは簡単なようで難しい。
ネットで在庫があって注文を受けたが、店員が棚に行ったら売れた直後だった。
店頭ピックアップにするとこういう課題が生じますね。
ベストバイの取り組み開始は遅きに失したという気がします。
メンズウェアハウスの創業経営者ジョージ・ジマーが突然退任して話題になっているのですが、退任と言うよりも解雇という表現が適当なようですね。
取締役会が職を解いたというのが正しいようです。
日本だとクーデターなんて表現されるんでしょうか。
メンズウェアハウスはジョージ・ジマーによって40年ほど前に創業されたメンズアパレルの専門店チェーンです。
スーツやワイシャツなどフォーマルな衣料がメーンで、日本語では紳士服チェーンになるでしょう。
特徴はジマーが広告塔となってきたことにあります。
有名なコマーシャルがありまして、おそらく知らないアメリカ人はいないんじゃないでしょうか。
解雇された理由は会長職にあるジマーが現CEOと意見で衝突し、取締役会がCEO側に立ったということになります。
それと資料によると、ジマーのイメージが非常に濃いわけですが、ベビーブーマーにはアピールしてきたがこれからの消費を担うミレニアム世代にアピールしないため、消えてもらわないと困るというマーケティング上の理由もあるようです。
日本で騒がれているシニアシフトという観点からは、ジマーが先頭に立つのが良いのでしょうが。
アメリカの流通業界は次の消費を担うミレニアムに焦点が移っていまして、日本の流通業界とは対照的です。
アルバートソンズがロイヤルティ・マーケティングをやめます。
スーパーバリュから売却されて3ヶ月、この際だから効果がなくて無駄にお金を垂れ流しているプログラムはさっさとやめてしまおうということなのでしょうね。
以下、同社による中止するための説明文を意訳抜粋します。
「...特別な店舗カードを持っているお客様に特別な価格を提供してきました。しかしカードはもはやそれほど特別なものではなくなってしまいました。いまや誰もが持っています。だからカードをやめる決断を下しました...あらゆるすべての人にすばらしい買い物経験を提供するのが我々の仕事で、そしてこれにはすべてのお客様に低価格を提供することも含まれています」
こんな記事をエントリーしましたね。
【ロイヤルティプログラムのアクティブ比率は44% 】
ハイローとは本質的に不公平価格政策で、対極にあるのがあらゆるお客に公平に低価格を提供するEDLP、となります。
ハイローばりばりのアルバートソンズがEDLP化するとは思えませんが、引用文はこのあたりを説明していますよね。
たぶんアルバートソンズの売上高は、カードをやめてから最低でも1年間は売上が落ちるでしょう。
でも上場してませんから、資本を持っている投資企業さえ合意してくれれば問題はない。
その上で、ハイロー戦略の組み直しをするんでしょうね。
目的と手段をはき違えている企業は、アルバートソンズのようにさっさとやめてしまうべきだと私は思います。
オーチャード・サプライ・ハードウェアが連邦破産法11条を申請し破綻しました。資産総額4億4100万ドルに対して負債総額は4億8,000万ドル。
現時点では、全91店舗中の60店舗に対してロウズが2億500万ドルで買収提案、8店舗で清算のための在庫処分セールスを裁判所が許可、22店舗が許可待ち、という状況です。
在庫処分セールスを請け負う清算企業(リクィデーター)はこれから入札で決め、いつものヒルコとゴードンが第一候補として名乗りを上げているようです。
ロウズの買収提案も最終決定ではなく、清算か売却かを天秤にかけて最もリターンが高い方を裁判所が選ぶことになります。
オーチャード・サプライ・ハードウェアはもともとシアーズホールディングス傘下でしたが、2011年末にスピンオフされて単独上場企業となりました。
シアーズホールディングスは上場益を得て、一方破綻によってババを引いてしまった株主が一杯いるというわけで、結果として投資家ランパートは不良資産を見事に売り抜いたということになります。
現在出張中のためエントリーが滞っておりますが、まとめということで3つアップします。
【ロン・バークルがフレッシュ&イージー買収交渉か】
小売企業への投資で財をなしたロン・バークルがフレッシュ&イージー買収でテスコと交渉しているという記事を経済誌が掲載しました。情報ソースからのネタですね。当事者はノーコメントです。
ただ私の頭の中に買収企業(または人)としてロン・バークルは存在しなかったので、なるほどそういう可能性もあったかと気づかされました。
しかも店舗名はワイルドオーツにすることで検討しているとしていて、これもまたすごいアイディアだなと驚きました。
バークルがパートナーとして選択しているのが前セブンイレブンCEOのジム・キーズで、この人がワイルドオーツという名称の使用権を持っている模様。想定している新フォーマットがオーガニックメーンの小型スーパーだとしたら、これもまた面白いなあと思います。
【セイフウェイがカナダ事業を売却】
セイフウェイがカナダ事業を現地のソビーズに売却することを発表しました。総額は58億カナダドル。
カナダのセイフウェイは223店舗、工場12ヶ所を所有しており、昨年度の売上高は67億カナダドルで決して小さい規模ではありません。営業利益も出ている。
メディアによると、売却額は高めだそう。
セイフウェイは現在米国内の業績が良くないため本国内に集中したいという動機があり、ここに高めのオファーがあったので乗ったということみたいですね。ソビーズとしては今後の競合激化に備えて儲けの出ている事業を高めで買ったということになるのでしょう。
ただセイフウェイはブラックホークを上場でスピンオフさせてますし、利益源を失うので、今後を楽観視はできない状況だと思います。
【Eコマース系の技術開発企業をウォルマートが買収】
ウォルマートがInkiruというEコマース系の企業を買収することを発表しました。先月はOneOpsとTasty Labsという会社を買っていて、立て続けということになります。
これ、企業を買うのではなく、技術を買っているわけですが、このあたりに日本の流通業界はあまり注目していないんじゃないですかねえ。
@WalmartLabsの動きを注視しているとEコマースで何が必要なのか見えてくると思っています。
ちなみにEコマースの技術を自前でやろうとしている小売企業は日本にいないんじゃないでしょうか。この分野でウォルマートはどんどん手の届かないところに進んでしまっているように感じています。
西友がすぐそばにいるわけだから、他人事じゃあないんですけどね。
ウォルマートは本日株主総会を開催しています。
これから新しい情報が出てくると思うのですが、資料を読み込むのには時間がかかるので、とりあえずメディアが出している速報を。
ネイバーフードマーケットの出店を加速するようです。
今年と来年の新店予定数は80~100、ただしスーパーセンター並の投資リターンに近づいたら出店数を上方修正する可能性がある、としています。
もともとこのフォーマットへの注力は公言していたことなので、その確認ということになりますね。
ただ、この小型店舗が巨艦ウォルマートの売上高成長にどれだけ貢献するのかは未知数で、今後を見守るしかありません。
アマゾンが生鮮のデリバリーをロサンゼルスで開始しました。数ヶ月前から噂が立ち、昨日は水曜日か木曜日にはオープンするというメディア記事が出たりして、私もGoogle+に噂として書いたりしていたのですが、本日のメディアの記事でオフィシャルに開業したことが分かりました。
ただし私が自分の住所で調べてみたところデリバリー圏外となっていて、ロサンゼルスでもまだカバー地域は限定しているようですね。
どうやらハリウッドのような人口密集地からはじめているようです。
シアトルでも少しずつ広げてゆくということをやりましたらか、ここでも同じ手法なのでしょう。
アマゾン(というよりもジェフ・ベゾス)は、必要最低限の情報以外は外部にいっさい語らない主義なのでどういうモデルなのかよく分からないのですが、どうやらこの生鮮はロスリーダーとして利用しているようなんですね。粗利の取れるハードを一緒に買ってくれと。
これは、例えばドラッグストアにとっての生鮮のようなもので、業界ではまあよくある戦法ではあるのですが、フレッシュダイレクトやピーポッドのように食品だけでビジネスを成立させている企業にとってはたまったものではないですよね。
実はちょっと理由があってアマゾンの財務内容を分析しているのですが、通常のリテールモデルとは乖離しているところがありまして、おもしろいなあと感心しているところです。
ちなみにセンターの技術とか物流を俎上に上げる人が多いですが、アマゾンの本当の強さはそこではないと私は思ってます。
ターゲットは昨年の夏頃からビューティ売場に黒服を着た専任の担当者を配する実験を一部の店でやってきたのですが、200店舗に拡大することを明らかにしました。
名称はビューティ・コンシェルジェ。
iPadを持たせて情報提供する模様。
ただしメークのようなハードなサービスはないようです。
実際ロサンゼルスで見たことがあるのですが、メークをする特別な場所を設置することはなく、回遊しているだけでした。
アメリカのマスビューティはセルフが基本、ドラッグストアのように担当者を置く業態もありますが普通の店員の域を出ることはなく万引き監視と陳列管理が主業務だろうと私は考えています。
コンサルティング販売をしているシーンを今まで見たことがないので。
ファッションに強いターゲットはビューティも強く、スペシャリストを配する試みは悪くないでしょう。
ただ本当に必要なのかは疑問という意見もありますね。
売上増に貢献するのかどうかは、私の意見では五分五分といったところで、成功事例になるかどうかは現時点では分からないとしか言いようがありません。
ちなみに数年前、ブーツがビューティ担当者を派遣する実験をしていたのですが、すぐにやめてしまいましたね。
ウォルマートが生鮮強化プランを発表しました。
・中間業者を可能な限り排除し、産地を近場にして物流距離を短縮する。
・鮮度管理技術を上げるための店員教育システムを導入する。
・外部業者を雇って店頭で抜き打ち鮮度チェックを実施する。
・商品に満足しないお客に対しては無条件で返金する。
唐突になぜいま生鮮なのかがよく分からないのですが、ウォルマートという企業は"全カテゴリーで競合に必ず勝つ"、という文化を持っているので、"次は生鮮だろう"というような感じで選ばれたのかもしれないですね。
ウォルマートは全米最大の生鮮販売企業ですが、スーパーセンターが3000店舗を超えていて、この店舗数を持った競合スーパーマーケットは存在しませんから、自然に一番になってしまいますし、2位以下を大幅に引き離しての1位ということになります。
しかしながら、価格を主軸に据えるウォルマートですから生鮮売場はそれなりです。鮮度を主軸に据える日本の食品スーパーから見るとかなり貧弱でしょう。
今回のイニシアチブもディスカウントストアという枠組みを外すことはないでしょうから、日頃鮮度を重視している方たちにはたいしたものではないと思います。
それとこれはよくある話なのですが、「商品に満足しないお客に対しては無条件で返金する」というようなルールは標準化するのが難しく、店舗によって対応が異なることが往々にしてありまして、字面通りに受け取ってはいけませんね。
まあ現場で何が起きているかなんて分かりませんから、このイニシアチブは凄いなんて言う日本の業界人は少なからずいそうな感じはします。
学ぶべきは、強化分野を絶えず選択して集中的に取り組む点でしょうか。
とにかくウォルマートは止まることがない企業です。
コロクゥイ(Colloquy)というマーケティング企業が10年以上ロイヤルティ・マーケティングの市場調査を実施しています。
月曜日に発表されたレポートによると、昨年の総登録者数は26億5,000で2010年から27%増、一世帯当たりのプログラム数は21.9で18.4%増だそう。
このうちアクティブなプログラムは44%で4.3%ダウン。
業界別だとグローサリーストアが1%ダウン、コンビニが21%ダウン、となっています。
簡単に言うと、登録している人は増えているが、実際に使っているプログラムは減っている、と言うことになりますね。
しかし、世帯当たり22というのは多いですね。
リテール、ホテル、飛行機等々いろいろな業界が利用していますから、合わせるとそのぐらいになるんでしょうが。
日本ではFSP、ポイント、ID-POSとか言われますが、アメリカではロイヤルティマーケティングと言います。
この名称に成否のカギがあるんですよ。
ロイヤル、つまり熱心なファンを作ることを目的としたマーケティングであって、ポイントバックとか、購買履歴の分析等はすべて手段に過ぎません。
つまり日本は手段が目的化しているんですね。
たくさんある販促のただの一手法に過ぎなくなってます。
だからどの企業も苦労しているというわけです。
実はアメリカでも同じで、けっきょくこの目的意識を持っていない企業が多いからダメで、だからアクティブ比率が減っているんです。
ちなみにポイントシステムはハイローの中でも麻薬性が最も強く、いちどはじめると簡単にはやめられなくなります。
ただの販促の一手法に過ぎず、他にも販促手法が一杯あるわけですから、ロイヤルティマーケティングの手段として使うのでなければやらないのが正しいと考えてます。
研修のコーディネートで現在ワシントンDCに滞在中です。
店舗を視察して回る中で印象に残った陳列を一つ。ウォルマートがメモリアルデー用に作った花のPDQです。
花は箱の中に梱包されていたものと推測、水を入れるお皿も付いていて、組み立てた後にそこに水を入れて花をさしておく構造になってます。
製造場所はコロンビア、おそらくコロンビアで花の調達、PDQの製造、梱包、まで済ませて、物流して店舗に入荷したのでしょう。
陳列されていたのは6箱、ネイバーフッドマーケットも含めて4000店舗として、2万箱以上を仕入れて展開したのではないかなと。
メモリアルデーまでの数日間というわずかな期間のみの販促プログラムというわけですが、素晴らしいですね。
作業負荷を可能な限り下げようとするパッションと、わずかな期間の販促のために生鮮を海外から仕入れてしまう調達力の、2つをひしひしと感じたのでした。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
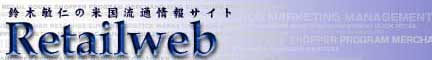






最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS