ウォルマートがギフトカードのエクスチェンジの実験をはじめました。
他社のギフトカードをウォルマートのギフトカードと交換するサービスです。
ギフトカードとは日本で言うところの商品券、エクスチェンジとは簡単に言えば日本の金券ショップですね。
アメリカには紙の商品券はほぼ存在せず、主流はPOS対応のプリペイドカードです。
使用されないギフトカードを現金や他のギフトカードに換えるニーズは、ギフトカード市場が急成長するにつれて高まっていて、専門のサイトがすでにいくつか営業しています。
そのうちのCardCash社がウォルマートとパートナーを組みました。
ざっと見る限り、CardCashの完全請け負いで、手数料をいくらかウォルマートに支払うという仕組みでしょう。
実験と言っていますがウォルマートに大きなリスクは無さそうなので、継続ビジネスになるんじゃないかと思います。
ウォルマート2014の最近のブログ記事
昨年よりもかなり回復スピードが速くなったような気がします。
前倒しで分散した事による混雑の緩和と、慣れと、二つ理由があるんでしょうね。
写真はアパレル売場、これからこれを元に戻す作業が待ってます。
チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー(日本の商品部長)のダンカン・マクノートンが辞任すると報じられています。
歳末商戦がまさに始まろうとしているときですから、タイミングとしてはすごいですね。
理由は不明なのですが、周辺環境はこんな感じです。
-
米国事業CEOのビル・サイモンの後継とみられていたのだが、サイモン辞任後に後釜に座ったのは中国事業担当だったグレッグ・フォランだった。
-
ここ数年米国事業の業績は芳しくない。
-
マクノートン辞任後にCMOを置かず、商品部をフォラン直轄とする。
憶測ですが、フォランと確執があったように感じます。
日本ならぐっとこらえてしまうように思うんですけどね。
結局アメリカはレイバーの流動性が高く他へ移っていけばいいので、こらえる必要が無いということなんだなあと。
そもそも高給もらってますから、次がなくても十分に蓄えがある、というのもあるんでしょうけどね。
研修のコーディネートでシカゴからベントンビルに着いたところです。
シカゴの気温は日中でもマイナス8度ぐらいで、冷凍庫の中で店舗を見て回っているような感じでした。
さて、写真はシカゴでのウォルマートでの一コマ。
プライスカードに表示されている価格と、端末上のマスター価格のチェックをしてました。
アメリカでは電子棚札がまったく普及していないのですが、電子棚札への投資額と、こういった手作業による人件費とをはかりにかけて、前者を選択しないというわけです。
ROIにシビアになることが肝要です。
ウォルマート、ウォルマート・コム、アマゾンの価格を比較する調査をカンター・リテールというコンサルティング会社が毎年実施しています。
今年で3年目。
今年の結果は、アマゾンはウォルマート・スーパーセンターよりも12%高く、ウォルマート・コムよりも17%高い、でした。
ということで、今年はウォルマート・コムに軍配が上がりました。
私の記憶では、昨年まではウォルマート・スーパーセンターが一番安かったはずで、ウォルマートがネットの価格を下げて強化している感じがしますね。
ネット販売は店舗を持たないからリアル販売よりも価格を安くできる、というのが一般的に信じられているセオリーです。
でもビジネスモデルで低価格を実現しているウォルマートには、こういった世の中の机上の論理は通用しないというわけです。
ウォルマートが2万アイテムの値下げプロモーションを11月1日から開始することを発表しました。
加えてネット販売ではギフトの売れ筋100アイテムと50ドル以上の買い物で送料無料の歳末キャンペーンを実施します。
一方アマゾンは同じく11月1日からプロモーションアイテムに"ブラックフライデー"というラベルをつけて、こちらも歳末商戦をスタートさせるようです。
毎日2アイテムを選んでアピールする"今日のディール"を12月22日まで実施するなど、いくつかの企画を投入する模様。
たぶん多くの企業が明日から歳末企画を店頭に並べはじめると思います。
歳末商戦のスタート時期は年々早まっているのですが、たぶん11月1日が限界なのでしょうね。
消費者が歳末モードに切り替わるのはハロウィンが終わってからですから。
売場がどんどん賑やかになっていくので、消費者にとっては楽しい時期の始まりといったところです。
ネット上の売価をトラックする専門企業の360piと金融会社のウェルズファーゴが、アマゾンとウォルマートやターゲットといった大手ディスカウントストアによるネット売価を年間通して調査し、その結果をメディアが報じているのですが、ほとんどのケースでディスカウントストアの方がアマゾンよりも安いという結果が出たそうです。
これは去年の記事です。
ウォルマートvsアマゾン、プライスリーダーはウォルマート
この昨年の記事で書いたように、アマゾンやEコマース企業はリアル小売企業のように店舗を持たない分コストが低く、だから安く売ることができるという論があります。
でもそれは机上の空論で、実はそうでもないということです。
単純に販管費率で比較すると、アマゾンの26.2%にウォルマートが19.2%ですから、ウォルマートに軍配が上がることになります。
荒利益率もアマゾン27.2%に対してウォルマート24.8%ですから、こちらもウォルマートの勝ち。
ただアマゾンは将来の投資優先で利益を無視しコストをかけているので販売管理費率で単純比較は無理がありますし、カテゴリー構成もかなり違うので荒利益率で単純比較することもできません。
リアル小売企業が価格で勝っている理由の一つとして技術が向上が挙げられています。
競合企業の価格を常時モニターしてこちらの価格を動かすダイナミックプライシングですね。
アマゾンは毎日最大で4,000万アイテムの価格を変えていると見られているのですが(年末のピーク時で最大8,000万アイテム)、1つのアイテムを1日に何度も動かしたりしますから、回数ベースだともっと数字が大きくなるでしょう。
リアル小売企業もこれに対抗する技術を持ち始めたということです。
目に付きやすいのでデリバリー分野ばかりが取り上げられがちですが、実はこういうところでも激しいつばぜり合いを繰り広げているんですね。
ウォルマートが恒例の投資家向けカンファレンスを水曜日に開催しました。
今年の業績予測を下方修正したり、来年の設備投資額の縮小などなどいろいろ出てますが、このあたりはおそらくあちこちでもう書かれていることなのでここではおいて、時期を合わせて各地でデモが発生し逮捕者が出るに至っています。
目的は賃金水準の向上で、毎年のことなので珍しくはないのですが・・・カンファレンスでメディアがウォルマートを取り上げる日を狙ってデモをするところに、プロ臭さを感じてしまって鼻白んでしまうのは私だけでしょうか。
デモのうしろには食品労働組合がいます。
食品労働組合の交渉相手はスーパーマーケット企業ということになるわけですが、しかし対ウォルマート運動の場合はそのうしろにスーパーマーケット企業がいるとみられています。つまりいつも戦う相手と、対ウォルマートでは共闘するわけですね。
賃金を上げることが経費増につながって、最終的には競争力を弱めることになりますから。
これに対してダグ・マクミロンが全従業員を最低賃金より高くすると言っているようです。
現在連邦で定められた最低賃金は7.25ドルですが、州によって高く設定することも可能で、カリフォルニアは9ドルです。
例えば7.26ドルにすることもできるわけで、マクミロンのコメントがどこまで実行するかは分からないのですが、こういう話題が出るたびに想起するのがマクネアー理論です。
会社は大きくなればなるほど経費増のプレッシャーが働き、組織肥大して弱体化し、これを倒す新興企業が生まれ、この新興企業が大企業になり・・・をくり返すというあれです。
ウォルマートはこの理論を証明する企業になるのか、はたまた理論を破綻させるのか。
ちなみに連結ベースでウォルマートの販売管理費率はここ数年19%程度で推移しているのですが、20年前は15%でしたから、経費は明らかに上昇しています。
ウォルマートがインスタグラムの創業者で現CEOのケビン・シストロムを外部取締役として迎えると発表しました。
シストロムは30才のエンジニアで、2010年にインスタグラムを創業、2012年に社員13人の時点でFacebookに10億ドルで企業を売却した人物です。
ウォルマートにとっては15人目の取締役で、テクノロジー・Eコマース担当委員会に加わるとのこと。
2012年に当時グーグルのバイスプレジデントだったマリッサ・マイヤーを外部取締役としてノミネートして驚かせましたが、当時マイヤーは36才、今回のシストロムは30才ですから、さらに若い。
しかもFacebookのザッカーバーグではなくて、買収された方のシストロムを選んだ点に、衝撃を受けました。
日本の大手企業の取締役はシニア集団になりがちですからねえ。
世界最大の小売企業が外部取締役として30才のエンジニアを選んだという点に我々は何事かを感じなければならないでしょう。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
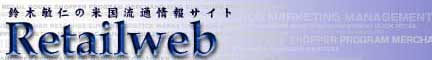



最近のトラックバック
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS