大手メーカーさんの米国研修が無事終了しました。
HBCの売り方の変化、ドラッグストア業態の変革の方向性、などをテーマとして、店舗視察、ゲストスピーカーを招いてのセミナー、ディスカッション、を重ねながら思考を進めました。
皆さん、お疲れ様でした!
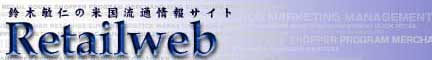 |
|
|
大手メーカーさんの米国研修が無事終了しました。
HBCの売り方の変化、ドラッグストア業態の変革の方向性、などをテーマとして、店舗視察、ゲストスピーカーを招いてのセミナー、ディスカッション、を重ねながら思考を進めました。
皆さん、お疲れ様でした!
アメリカ流通eニュース
日本から来る研修グループから必ず聞かれる質問の一つが万引きである。外国人を中心とした窃盗団による被害に頭を悩ましている流通人が日本では少なくないのだが、アメリカの売場は日本と比較すると万引き対策が甘く見えるようで、どう対処しているのか疑問が湧くようだ。
所得によって住み分ける傾向が強いアメリカの場合、低所得層エリアに出店する店舗では対策を十分すぎるほど取っていたりするのだが、そういう危険なエリアに視察で行くことはあまりないから甘く見えるのだろう。
カナダのトロントで低所得層エリアにあるドラッグストアに行ったのだが、中~高価格帯の化粧品がすべて鍵付きの什器に入っていて驚いた。おそらくあれでは売れ方はがた落ちなのだろうが、万引きされるよりはましということだと推測できて、そういう売場を見れば日本からの人たちも納得するのだろう。
<これ以降の内容に興味のある方は、アメリカ流通eニュース(有料)をご購読下さい。>
ステープルズがプロトタイプを小型化することを明らかにしました。現行の18,000sqf(507坪)から15,500~16,000sqf(437~450坪)へ縮小します。
2000年のプロトタイプが24,000sqf(676坪)だそうなので、単純計算ですが10年間で25%減らしたことになります。
オフィス用品のディスカウンターは、オフィスデポ、オフィスマックスともに調子が良くありません。景気の悪化が直撃、オフィス用品の節約、失業者の増加でそもそも使う人が減ってしまった、ネット販売の成長、などなどで業績がふるいません。
それとやはり、ウォルマートやターゲットがきっちり売ってますからね。
競合は同業内だけではありません。
業績の良くない他の二社、オフィスデポとオフィスマックスは合併すべきだという主張がウォール街にあるのですが、間違っていないように思います。
三社ももはや必要ないというわけです。
10年以上前でしたか、ステープルズがオフィスデポを買収しようとしてFTCに差し止め食らったことがあるのですが、経済環境が変わりましたので、今回はたぶんスムーズにいくことでしょう。
アメリカは、大型化の時代は明らかに終わりましたね。
これからはしばらく小型店の開発が主流になりそうに感じてます。
<追記>
本日より某大手メーカーさんの研修で出張です。ボストン→トロント→ニューヨーク。ニュースのエントリーが減るかもしれませんがご容赦ください。
昨日フレッシュ&イージーがサンフランシスコに一号店をオープンさせました。
ローカル紙が写真を載せてます。
1st Fresh & Easy market opens in S.F.
フレッシュ&イージーのサイトを見るに、ナパなど郊外も含むような広い意味でのサンフランシスコ地域(グレーター・サンフランシスコ)とすると開店予定はすでに21店舗になってます。
サクラメントエリアには15店舗、合計すると37店舗をオープンさせる計画をすでに持っていることになります。
実験うんぬんではなくて、最初っから絨毯爆撃してしまうわけですね。
すべてロサンゼルス郊外の配送センターがカバーする。
どこかの時点でサンフランシスコ地域に配送センターをオープンさせて切り替えることになるわけです。
まあこうみると、フレッシュ&イージーがアメリカから撤退するなんてそぶりはみじんも感じることはできません。
投資家向けのカンファレンスで共同CEOのウォルター・ロブが、アメリカ国内だけでこれから1,000店舗をオープンさせることが可能だとコメントしました。
またカナダでは現在の6店舗を35店舗へ、イギリスの店舗はキャッシュフローがプラスになったそうです。
強気のコメントと、証券会社が同社の株の格付けを上げたこともあって、株価が急上昇しました。
このさらに1,000店舗というのはにわかには信じがたい数字です。
高価格帯なので出店場所を選ぶフォーマッであることと、商圏の大きさを考えると、簡単ではないでしょうね。
ちなみに現在の店舗数は300です。
高齢化が進むと健康志向が高まることが予測できますから、市場の変化も想定しているのかもしれません。ただだとしたら、価格帯をもう少々下げる必要があるんじゃないでしょうかね。
2001年に現職の店員と元店員が最初の訴訟を起こして、それ以来集団訴訟として適切かどうかで争われてきた問題で、米連邦最高裁判所が集団訴訟としては認められないという判断を下しました。
このケースの難しさについては3月にエントリーしています。
[ウォルマート] 性差別訴訟の集団訴訟化に対する最高裁の審理開始
結局裁判所はシステマチックに差別が起こっているとするには無理があるし、それをすべての女性店員にあてはめるのも無理があると判断したわけです。
もし集団訴訟になったら大変なペナルティを払うポテンシャルがありましたから、これでウォルマートは一息でしょう。
ただ資料を読むに弁護士がエリア別に訴訟を起こすというようなことを言っているので、訴訟自体がなくなるわけではありません。とりわけウォルマートのような巨大な企業は狙われやすいですから、ウォルマートにとって訴訟問題は終わることのない課題ということになります。
ニューヨークのターゲットの店員が組合加入の投票を実施、137vs85で非加入が決まったというニュースがありました。
組合はUnited Food and Commercial Workers Union、ターゲットが不法に店員を脅したとして再投票を実施するよう当局に要求するとしています。
もちろんターゲットは否定。
組合問題はウォルマートが俎上に上がることが日本では多いと思うのですが、ターゲットも組合結成を許しておらず、けっこうあちこちで火花を散らしています。
ここ数ヶ月、食品労働組合の動きが活発でして、組合が補助してできた組織がウォルマート本社前でデモやったり、メイシーズではストライキ寸前までいったり、ロサンゼルスでも大手スーパーマーケット企業と組合の軋轢がかなり高まったりしています。
組合幹部がけっこういいサラリーを稼いでいるという話を聞いたときに、ああ組合もビジネスなんだなと理解し納得したことがあります。
なんでも組合員数が最盛期の120万人(1983)から70万人に減っているそうで、おそらく組合員を増やさないと組織が維持できないのでしょうね。
アメリカ流通eニュース
ベストバイが売場の一部をサブリースすることを検討していることをローカル紙が報じた。不動産ブローカーに発送されたチラシによると、南カリフォルニア46店舗の4,000~15,000sqf(112~423坪)程度のスペースをテナントに貸し出すという。
アメリカでは80年代から90年代にかけて店舗の大型が進んだ。牽引したのがディスカウントストアとスーパーマーケット、とりわけディスカウントストアの店舗の形状が大きな箱のようなのでビッグボックスと呼ばれたものである。
このビッグボックス時代が終わったという論調が大勢を占め始めている。前々回のレポートでとりあげたが自治体の税収が落ちているのも、大きな"ハコモノ"市場が縮小し始めているからに他ならないのである。
<これ以降の内容に興味のある方は、アメリカ流通eニュース(有料)をご購読下さい。>
テキサスのHEBがP&Gとコラボでメンズオンリーの売場を実験しています。
調べていたら動画が出てきたので、メモがわりにアップしておきます。集合させたアイテム数は530。
アメリカのメンズビューティは出足が遅かったのですが、ここ5年ぐらいに一気に変わりました。それまでは日本の方が先を行っていたように思うのですが、今は商品ラインアップ的にも売場的にもアメリカの方がいいものを作り始めましたように思います。
今日は外食ネタです。
クリスピークリームのCEOが株主総会で現状とこれからの見込みについて語っています。
過去のミスマネジメントでガタガタになっていた経営内容が努力によってようやく利益を出せるようになり、独り立ちできるようになってきた、これからは将来に向けた取り組みを始めたい、そのカギの一つはコーヒー、一つはベーグルやマフィンと言った非ドーナッツ商品である。
(非ドーナッツ=non-doughnut products、直訳しましたが、英語の他の表現だとペイストリー、日本語だと菓子パンといったところでしょうか)
といったところが要約です。
クリスピークリームの失敗については、4年前にこんなエントリーを書いてます。
クリスピークリームが日本上陸
ロサンゼルスに来たときは並びましたよ。
でも、近所のパン屋さんのドーナツの方がちょっと高いけどおいしいということを知ったときに、なるほどそういうビジネスなのかとはたと気づいたわけです。
製造工程を見ることができる、作りたてをサンプリングできる(作りたては何でもおいしい)、だから楽しい、そして安い、これがカギなんですが、でもここまででした。
そしてスタバのような秀逸なマーケティングを展開することなかったので、"そこまで"というビジネスをカバーすることができませんでした。
だから、ドーナツだけでは無理なので、コーヒーや非ドーナッツ商品を投入するのでしょうね。
ただいったん離れた客を戻すのは、新たにお客を獲得するよりも難しい。
経営者の手腕が問われます。
しかしアバクロやギャップもそうだけど、アメリカでダメになったら海外へ、という戦略が取れるアメリカ企業はある意味うらやましいところがありますよね。
国内事業の責任者ビル・サイモンが投資企業主催のカンファレンスでスピーチしまして、小型店舗の戦略について語りました。
ウォルマートマーケット(旧ネイバーフッドマーケット)については、来年の1月までに90~100店舗、2012年中に300店舗を増やすそう。もともと今年の新店数は40店舗でしたので、大幅な予定数の増加ということになります。
現在の店舗数は185店舗
増やす理由はROIがスーパーセンター並みだからと説明しているのですが、いままでスーパーセンターよりもROIが低いので増やしてこなかったわけなので、いきなり同じだと言われても困るものがありますね。
ウォルマートエクスプレスは年内に15~20店舗をオープンさせてテスト。本社近くにすでに2店舗目がオープン、昨日ノースカロライナに3店舗がオープンし、7月にはシカゴに4店舗目が開店します。
この4店舗目が大都市のアーバンにありまして、今後の出店戦略を考えるとこの店舗の成功がカギを握ることになります。
エクスプレスについてはどういう価格戦略を取るのか知りたいところです。
EDLPにするんでしょうかね。
アップルストアの拡大を支えたロン・ジョンソンがアップル社をやめて、JCペニーの次期CEOに就任する人事が発表されました。
現CEOのマイク・アルマンの退任は10月末で、11月1日よりロン・ジョンソンがJCペニーのトップとなります。
ロン・ジョンソンはアップルストアをゼロからスタートし300店舗まで成長させた人なのですが、単なるショールームではなく、アップルそのものを表現する店舗の開発に成功したという意味で功労者と言えます。
業界でも非常に評価が高い。
ただたぶんアップルではこれ以上昇進はないだろう思い、他社での可能性を考えたのでしょうね。
アップルの前職はターゲットでマーチャンダイジングの上級副社長、ハーバードのMBAを持っており優秀な人材です。
アップルストアの後任はまだ決まっていない模様。
優秀な責任者が抜けて今後どうなるのか、注目を集めています。
NRF(National Retail Federation、全米小売連盟)が"Organized Retail Crime Survey 2011"という調査結果を発表しました。
Organized Crimeは直訳しても組織犯罪、日本とアメリカで表現の仕方がきっちりシンクロしていますね。
「アメリカでも組織犯罪のようなものはあるのですか? 日本では中国人などの外人がグループで行う組織犯罪が多くて困っています」、と質問されることが多いのですが、アメリカでもこれは悩みの種です。
調査対象は大手小売企業129社。
・過去12ヶ月間に組織犯罪の被害に遭った企業の比率は94.5%、前年の89.5%から6%上昇。
・3分の2が組織犯罪は増える傾向にあると回答。
・原因としては、店員数の削減、ネットなど盗品をたやすく販売できる環境、経済環境の3つを指摘。
また今年から初めてコンテナ単位の被害を調査、49.6%が過去1年間に被害にあったと回答しています。
コンテナ単位とはつまり物流用のトレーラーのことでして、これはかなり規模の大きな犯罪ということになります。
・小売配送センターから店舗への途中:57.4%
・メーカーから小売配送センターへの途中:39.7%
・店舗間移動の途中:10.3%
・配送センター内:22.1%
・荷受け時:17.6%
アメリカも悩みは同じです。
ヨーロッパのローカル紙が報じたようで、イギリスだけで80店舗を開店させるとしていたのですが、拡大を延期する模様。ベストバイはノーコメントです。
イギリスでの1号店のオープンは昨年4月のことなのですが、昨年末の時点で6店舗までしか増えていません。
明言はないのですが、うまく行っていないようですすね。
ホールフーズもイギリスに出ているのですが、あまりうまくいっていないと聞いています。
イギリスからはテスコがアメリカに出ていますが、まだ黒字化するには至っていません。
アメリカとイギリスは同じ英語圏なので我々からすると簡単なんじゃないかと思うのですが、実は文化が結構違うので、簡単ではないようです。
アメリカ流通eニュース
アップルの店舗オペレーションの責任者、ロン・ジョンソンがアップルをやめてJCペニーのCEOに就任することが発表された。11月1日からトップに就任する予定である。
アップルストアを開発段階からてがけ、326店舗、年商98億ドルにまで育てた業界評価の非常に高い人で、そのため発表直後にJCペニーの株価が跳ね上がっている。
アップルストアの一号店の開店は2001年、2004年には年商10億ドル(およそ1000億円)を突破、2007年には四半期ベースで10億ドルを超え、小売業界で史上最速の成長を続けていると言われている。この成長の基礎を作りオペレーションを支えてきた人の移籍なので注目を浴びているというわけなのである。
<これ以降の内容に興味のある方は、アメリカ流通eニュース(有料)をご購読下さい。>
アクティビスト型の投資家、ウィリアム・アックマンがファミリーダラーの株式を買い集め、8.9%まで取得し最大の株主になったことが明らかになりました。
随分前からファミリーダラーにラブコールを送っていたのですが、本腰を入れたようです。
気になったので調べたのですがCEOのハワード・レビンの比率は3%ぐらいなので、創業一族を超えた比率を所有したわけですね。
もちろん株には優先株などいろいろ種類がありまして、大株主になったからといって会社を自由にできるというわけではありませんが。
アックマンが投資家向けのカンファレンスで、ファミリーダラーについてこう表現しています。
"It's a high return on capital business. They spend their money intelligently."
(資本ビジネスとしてハイリターンだ、彼らはお金を知的に使っている)
ファミリーダラーの店舗は一見するとつまらない店でして、素通りしてしまう日本の業界人も多いことでしょう。
しかしながら投資価値があるということはそれだけ儲かっていることを意味していているわけですよね。
上場している以上、投資家からこう言われない企業は何かがおかしいと反省しなければなりません。
またダラーゼネラル、ダラーツリー、ファミリーダラー、さらに加えるとビッグロッツやチューズデーモーニング、こういった企業群の売場を見て何かをピンと感じるように感性を磨く必要があるでしょう。
ちなみにファミリーダラーにはバイアウトのオファーが他の投資企業から来ていて、これと勝負をするためにアックマンは株を買い増したように思います。
資本をめぐる駆け引きは経営陣としてはいい迷惑ですが、でも決して悪いことではないし、対処が面倒ですね。
ギャップのCEOグレン・マーフィが投資家向けカンファレンスでこらからの店舗戦略を明らかにしました。
◇今後2年間でギャップ200店舗を閉鎖する。
◇ギャップ・アウトレットを50~60店舗オープンさせて250店舗とする。
◇バナナリパブリック・アウトレットを40店舗オープンさせて150店舗とする。
総店舗数はおよそ900ですから全体の2割以上を減らすというわけで、さらりとニュースは流れてますが、実は結構大きな縮小戦略ではないかなと思います。
そのかわりアウトレットを増やす。
アウトレットモデルの投資に対するリターンが高いのと、消費者間に低価格志向が強いからだと説明しています。
でもこれは結構リスキーというか、ギャップのイメージを変えてしまうのではないかと危惧しますよね。
強い本体があって、その上で本体をサポートする存在なのがアウトレットであるはずなのですが、どうもアウトレットの方が主語になってしまっているような気がするのは私だけでしょうか。
ギャップは相変わらず大変そうだなあというのが感想です。
どの企業が一番ロープライスイメージが強いのかという調査でアルディが一番となりました。
(調査したのはMarket Force社、N数は6,100人)
アルディ、コストコ、ジャイアントフーズ、HEB、クローガー、マイヤー、パブリックス、セイフウェイ、ショップライト、ウォルマート、の10社をまずリストアップし、各社について、価格、クレンリネス、サービス、品質、立地、レジ、といった項目でランク付けしてもらうという手法を取っています。
おそらく調査に参加した人が住んでいる地域に出店している企業を選んだのでしょうね。
価格では、アルディ、ウォルマート、コストコが上位三社で、アルディが他の二社をおさえて1位でした。
アルディは全米レベルでは知名度はまったくない企業です。
基本的に広告宣伝もほとんどしません。
でもこうやって選ばれてしまうということは、価格競争力が非常に強いからに他なりません。
アルディの強さを垣間見た気がしてエントリーしました。
マサチューセッツ州に本拠を置くローカルチェーン、ビッグY(61店舗)がグルーポンの実験を始めました。
最初の実験はShellfish Grill Pack(甲殻類シーフードのパック・・・ロブスターテール、ハマグリ、イガイ等)で、39.99ドルを40%引きの24ドルで販売するそう。
システムの概要が正確には分からないのですが、グルーポンサイトでまず購入し、それがFSPデータに転送されて、レジで自動的に割り引かれるという仕組みのようです。
紙に印刷する必要がない、またはスマートフォンを利用する必要がないという点が、今までのグルーポンの仕組みとは違っています。
この実験、その成否にはみんな注目していることでしょうね。
スーパーマーケットで取り扱われている商品群に親和性があるのかどうか。
モバイル決済でもFSPカードが絡んでいますし、FSPカードの存在価値が急に高まってきたような感じです。
(個人的にはあんまり重宝してないんですけどね・・・)
アメリカ流通eニュース
アマゾンがアーカンソー州居住のユーザーに提供しているアフィリエートプログラムを中止とした。理由は州が今年の初頭に法制化した新たな規制だ。
アメリカでは、ネット販売業者は自らのオフィスが存在しない州においては消費税を徴収する義務を負わない。消費者が税金申告時に自ら申告しなければならないのである。ただしこれをちゃんと実行している消費者は限定されており、実質的には消費税フリーとなっているのだ。
自らのオフィスとは、本社以外に配送センターも含んでいる。アメリカでネット販売やカタログ販売で買い物をしたことのある人はご存じかもしれないが、トータルを計算するときに~州在住の人は消費財~%加算という項目が必ずあり、加算する州にはその企業のなんらかのオフィスが存在するのである。
このオフィスにアフィリエートも含ませようとするのがアーカーソン州の新たな規制である。アフィリエートに広告費としてコミッションを支払っていると言うことは彼らもアマゾンのオフィスであることと同等だとしたわけだ。
アマゾンはこれに対抗するためにプログラムを中止したのである。アフィリエートよりも消費者を選択したと言い換えても良いかもしれない。実は同じ事を数ヶ月前にシカゴでも実行しておりアマゾンはこの規制に対する対決姿勢を示しているのだが、他州でも同じ動きがあるためアフィリエート撤退は今後も続くことだろう。
<これ以降の内容に興味のある方は、アメリカ流通eニュース(有料)をご購読下さい。>
先週の金曜日にウォルマートが株主総会を開きました。
いつも通りのお祭り型の総会。
どちらかというとウォルマート社員が世界から集まってシュプレヒコールを上げる場となっていて、株主と密なやりとりをする場ではなくなっています。
もともとは、投資家が田舎まで来てくれなかったのでお祭りをやることで興味を引くことが目的だったんですけどね。
ちなみに投資家を招いてのカンファレンスは秋口に別途開催されています。
今年の目玉は俳優のウィル・スミスの登場で、また歌手が何人か出てコンサートも挿入されていました。
さて、CEOのデュークがスピーチして基本戦略の話をしているのですが、細かいことはメルマガにでも書くとして、掲げた5つのプライオリティだけ記しておきます。
◇新規顧客、新店、そして買収によって、成長する
◇コストを低く押さえ、節約分をお客に還元する
◇グローバル・インターネット・ビジネスを構築する
◇人材を開発する、とくに女性とマイノリティにフォーカスをあてる
◇サステナビリティへの取り組みを拡大する
取り立てて目新しいものはありません。
興味を引いたのは"次世代の消費者"という表現で、新たに顕在化してきた消費者、または買い方を強調していた点です。
スマートフォンとソーシャルメディアで世界とつながっているのが"次世代の消費者"で、我々はその新たな消費者に対してスィートスポットにいると力説してます。
それと、ウォルマートエキスプレスの1号店が総会に合わせてベントンビル近郊にオープンしています。
この件についても別途書きたいと思っています。
シアーズがオート用品ブランドのダイハードを、ドーシー・インターナショナルという懐中電灯と電池のメーカーにライセンス供与しました。ドーシーはダイハードブランドの商品を小売企業に販売することが可能となります。
これがシアーズの考えていることなんですよね。
家電のケンモア、ハードウェアのクラフツマン、オート用品のダイハードを、他社で売りたい。ただしブランドのライセンス供与で商品そのものを製造し販売するというわけではない。
すでにクラフツマンの一部はエースハードウェアで販売しているそうなので、この戦略は少しずつ拡大しつつあるといったところです。
シアーズは衣料売場をテナント貸ししたいみたいなんですね。
ブランドを他社で売り、衣料売場は貸してしまい・・・
この企業にシアーズという店舗は必要なのだろうか?
CB Richard Ellisという不動産会社が、世界の大都市の商業家賃のランクを作っています。こういうランクがあると言うことを始めて知りました。
1、ニューヨーク:$1,900
2、香港:$1,697
3、シドニー:$1,301
4、ロンドン:$909
5、チューリッヒ:$829
6、東京:807
(Global Retail MarketView)
数値は今年の第1四半期、単位はスクェアフィート、その国で最も高いプライムロケーションの家賃を参考としているようです。
例えばニューヨークは5番街、ロンドンはウェストエンド、といった感じです。日本は銀座でしょうかね。
もちろんこういう各国の比較は為替の影響を受けますからこのランクを見て一概に理解することはできないのですが、東京が以外に安いというのは発見でした。我々日本人は東京は世界で一番高いというようなイメージを持ってるんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
全体として家賃は前年同時期に対して1.9%増、年間では3.8%増だそうです。
これもまた、景気の悪化で下落しているものと思っていたのですが、上昇しているというのは意外でした。
高所得層は景気の悪化の影響をあまり受けおらず、ラグジュアリー市場の調子はすでに戻っているのですが、そのせいなのかもしれませんね。
グーグルが非接触型の決済システムを開発することを発表しました。NFC(近距離無線通信技術)を搭載したスマートフォンを利用、シティバンクと提携し同社のマスターカードが導入している読み取り機のペイパスに対応する。
パイロットテストに参加するのはメイシーズ、アメリカンイーグル・アウトフィッターズ、ウォルグリーン、外食のサブウェイなどで、今夏にも実験が始まるそうです。
日本のお財布ケータイみたいなものですが、なにが違うのかというと、スマートフォンによる決済システムであることとと、通信キャリアでも金融機関でもないグーグルというシステム開発企業が中心となって開発が進んでいることでしょう。
すでに最初から各小売企業のFSP(またはロイヤルティマーケティング)を取り込むことや、グーグルオファー(グーグル版のグルーポン)などと統合することを明言しており、お財布ケータイとはちょっと違ったアプローチを取っています。
アメリカでは非接触型の決済システムがまったく普及していないのですが、グーグルによる今回のが取り組みがはじめの一歩になるのかもしれません。
細かいことはメルマガに書こうと思っています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |


最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS