携帯キャリアやアプリ開発企業がスマホのロケーションデータをマーケターに売って儲けていることは近年よく知られた事実となっていますが、ニューヨーク市議会でこれを規制する条例が審議されていて、可決されるとNY市が全米初のケースになるとメディアが報じました。
消費者にオプトイン、つまり選択肢を提供することが求められて、資料によると、一人一日につき1000~10,000ドルの罰則規定が設けられているそうです。
ロケーションデータと一言で言いますが、実はいろいろあって、今回俎上に上がっているのはモバイルのみです。
テレビ、家、スマートスピーカー、車も、その人がそこにいるのかどうかというロケーション情報の中に組み込まれていて、先進的なマーケターはこれを組み合わせて加工してマネタイズしています。
もちろんモバイルデータの価値が今のところ最も大きく、利用しているマーケターも多い。
これが欠落することで影響を被る会社は少なくないことでしょう。
ジオマーケティングは今が旬な手法で、各社が試行錯誤をしているところです。
日本はまだ規制の動きが出るところまで行っていないのでしばらくは続けられるでしょうが、アメリカではこういう動きもあるということは知っておいて損はないでしょう。
マーケティングの最近のブログ記事
メイシーズが共通ポイントサービスのプレンティからの脱退を発表しました。
おそらくプレンティは業界をまたいだ共通ポイントサービスとしてはアメリカ唯一ではないかと思います。
プレンティは2015年にアメックスが核になって発足したものですが、今年の初頭までにHulu、ネイションワイド、エンタープライズ、アラモ、エクスペディア、AT&Tが抜け、サイトを見る限り残るは7社だけとなり、存続に黄信号がともりました。
日本では共通ポイントが流行ってますが、アメリカではそもそもポイントシステムそのものが販促の主流になっていません。
なので、共通ポイントシステムが広く普及する土壌がありません。
ポイントを溜めるのは日本人の習性のようです。
たぶん戦後から行動経済成長時にかけて国を挙げて貯蓄を奨励して、それが文化になってしまったからなんでしょうね。
ちなみにポイントシステム=ロイヤルティプログラムと理解する人が少なくないですが、双方は別物です。
ポイントシステムは販促の一手法に過ぎません。
このあたりは書くと長くなるので、また別の機会に。
昨日アカデミー賞の授賞式が開催されました。
ウォルマートがこれをはじめてスポンサーしたのですが、コマーシャルの作り方が面白いので取り上げます。
テーマは、Behind every receipt, there's a great story、"すべてのレシートには素敵なストーリーがある"、レシートに載っている6つアイテムを必ず使って60秒間のショートフィルムを作ることが条件で、それ以外については自由、著名な監督3人に作成を依頼しました。
以下に3つの作品を参考までに貼り付けましたが、これが昨日の夜に流れたわけです。
ついでで舞台裏のショートフィルムも載せておきました。
制約なしという点が面白いですね。
ウォルマートとしてはキャッチフレーズの、Save Life Live Better、のLive Betterを強調しようとしたようです。
つまり価格サイドではなくて品質サイド、またはイメージ作りを主眼に置いた。
注文付けるとどうしても価格サイドになってしまうから、口出しをやめた方が面白いのができると思ったんでしょう。
それとアカデミー賞のコマーシャルですから、ある程度の品質と面白さがないと本体に負けてしましますからね。
ウォルマートの意図通りに、ウォルマートらしくないCMに仕上がっているんじゃないでしょうか。
アカデミー賞のイメージとウォルマートは合わないという批判もあるようですが、ふだんウォルマートで買っていない人にもメッセージが届いたとしておおむね好意的な反応が多いようです。
たぶん相当な費用がかかっていると思うのですが、企業規模が巨大ですからこのぐらいは許容範囲なのでしょう。
The Gift' a film by Antoine Fuqua
"Bananas Town" by Seth Rogen and Evan Goldberg
Lost & Found' a film by Marc Forster
Go behind the scenes as 4 award-winning directors create films based on a single Walmart receipt
ホールフーズがロイヤルティプログラムの実験をこの夏からダラスエリアの店舗に拡大することが明らかとなりました。
2014年からフィラデルフィア周辺の11店舗で実験していたもので、今回の拡大でさらに12店舗が加わることになります。
この12店舗に加えて、先週オープンした365でもロイヤルティプログラムをやってました。
おそらくこれから増えるであろう365はすべて導入するんじゃないでしょうか。
ダラスへの拡大と365での導入、それと経営陣のコメントを読むに、同社のロイヤルティプログラムの全店舗展開は近いように思います。
ロイヤルティプログラム(またはID-POS)は、他社との差別化要因がなくなってしまい、競合がコモディティ化したときに有効な価格戦略です。
航空業界ではじまったのも、今も全盛なのも、これが理由です。
つまりホールフーズのロイヤルティプログラム参入は、差別化が難しくなってきたということを暗にほのめかしているようなものなのです。
既存店も伸びなくなってきましたし、しょうがないのでしょうが、値下げ販促すら一切やらなかった昔の強いホールフーズを思い起こすと、とうとうそういうときが来たのかという感慨を持ってしまうのは、たぶん私だけなのかもしれませんね。。。
写真は365で実施しているロイヤルティプログラムのPOPです。
デパートメントストアのロード&テイラーが、インスタグラムにポストしたコンテンツについて、広告であることを記載していなかったとしてFTCから勧告されていた問題で、FTCと和解したというニュースが流れました。
昨年の春のキャンペーンで、ネット上でよく知られたファッション・インフルエンサー50人を雇い、有料でインスタグラム上に記事を書かせました。
このキャンペーンで使われた記事すべてに広告だという記載がなかった、というのがFTCによる勧告の理由です。
資料によると、こういった違反に対するペナルティは、初回は罰金なし、2回目からは1つの違反に対して1日16,000ドルの罰金だそうです。
ロード&テイラーは初回だったので勧告で終わったのですが、もしこれが2回目だったらたぶんミリオン単位で罰金が発生していたのでしょう。
この問題はこれから頻発することになるだろうと業界関係者が指摘しています。
グレーな記事ってかなり存在しますから。
今回の勧告は見せしめ的な意味合いがあるのでしょうね。
ターゲットがNYマンハッタンに歳末用のポップアップストアをオープンさせたのですが、オープニングまでの店内の様子を撮影したインターバル動画を公開しています。
バズらせる目的でこういう店内動画を公開するのは常道手段となってきました。
とくにポップアップストアは広告目的の店舗なので、こういう動画をカップリングさせるのは大切でしょう。
ただ気にかかるのは閲覧数の少なさですね・・・
ターゲットクラスの企業ならばもう一桁上げたいところです。
ネット販売のキャッチフレーズです。
ウォルマート: Anytime, Anywhere(いつでも、どこでも)
7&I: オムニ7
違いが一目瞭然かと。
キャッチフレーズやプログラム名は誰が見ても感覚的にすぐ分かるものにするべきです。
ロイヤルティプログラムに一度加入し、そのままやめずに続ける理由についての調査です(Colloquy社)。
分かりやすいこと:81%
自分に関係性の高いリワードやオファーがもらえること:75%
自分のライフスタイルや個人的な嗜好をサポートしてくれること:54%
リワードを早くもらえるいろいろな方法があること:50%
スマホのアプリがあること:48%
リワードとはポイントとは限らないのですが、分かりやすくポイントに読み替えたとして、日本では上位に入るであろう"たくさんポイント(またはリワード)がもらえる"が入っていません。
これが示唆していることは、アメリカの小売企業はポイントに重きを置いていないのではないかということです。そのため消費者も参加し続けるモチベーションとしてのポイントの位置づけが低い。
さらに深読みすると、アメリカの小売企業はポイントに偏ると泥沼にはまるということが分かっていて意図的に回避しているのではないかということです。
一方の日本はポイントに完全に偏ってしまっていますね。
ロイヤルティプログラムとID-POSと、日米名称が違いますが、本質も違ってしまっているんじゃないかと最近思い始めてます。
アップルがWWDC 2015で決済システムのアップルペイに、リテーラーによるロイヤルティプログラムのカードを組み込むと発表しました。
この直後に参加発表したのがコールズとウェッグマンズで、この秋から利用可能になるとしています。
資料を読むに、店舗カードを登録しておくと、アップルペイで支払いするのと同時に店舗カードによる割引が適用されるようですね。
そうなるとお客としては店舗カードを見せて、支払ってという、2つの作業を1つに集約できてしまうので、とても便利ということになります。
アップルペイに参加する大手チェーンストがなかなか増えないのですが、ロイヤルティプログラムをからめるとメリットが大きくなります。
MCXによるカレントCがなかなか登場しない状況で、アップルペイが先に普及してしまうんでしょうかね。
ちなみにコールズはMCX参加企業で、他のモバイル決済を導入しないことがMCXの参加条件だったので、コールズがアップルペイ導入を決めたと言うことは、条件が緩んだか抜け道があるのか、なのだろうと思います。
クローガーが英テスコ傘下のダンハンビーと合弁でアメリカに設立した企業がダンハンビーUSAで、これがクローガーのロイヤルティプログラムをアウトソーサーとして作り上げたという話はご存知の方も多いことでしょう。
設立は2003年、資本は50%ずつの折半でした。
このダンハンビーUSAの残りの資本の大半をクローガーが買収し、社名を84.51°に変更するという発表がありました。
現存するダンハンビーUSAが社屋や社員も含めてそのまま丸ごと新会社に移行するようです。
84.51°とうい社名の由来は本社の経度だそうです。
しゃれてますね。
わたしはてっきり台湾の85°のパクリかと思いました。
85°は一番美味しいコーヒーの温度だそうです。
ダンハンビー自体は残り社員数十名の企業となって、84.51°社に対してツールの使用料等を徴収するような企業として存続するようです。
ひょっとするとクローガー以外の小売企業のロイヤルティプログラムを請け負うということをするのかもしれませんが、詳しいことは分かりません。
このダンハンビーUSAの消滅は、テスコの業績悪化が関連しているのでしょうね
1月にはダンハンビーの売却を検討していることが明らかになっています。
一度ダンハンビーUSAの本社でいろいろ話を聞いたことがありますが、ここまでやっているのかと舌を巻くようなレベルでした。
クローガーも好業績の原因の一つだと言っていた時期がありました。
ただどこまで影響があったのかというとよく分かりません。
データ分析の結果を踏まえてアソートメントを改善したという情報もあったのですが、よくある話のレベルで、どこが凄いの?と肩すかしを食らったこともあります。
ちなみに84.51°はメーカーに対してデータ分析アウトプットを販売する企業として存続してゆくようです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
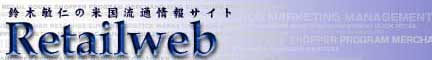



最近のトラックバック
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS