Institutional Shareholder Servicesという、委任状の投票についてのアドバイスを機関投資家向けに提供する大手コンサルティング企業がアメリカには存在します。経営サイドから独立したガバナンス機能を取締役会に期待するアメリカ型株主資本主義に特徴的なビジネスですね。
この企業がターゲットの取締役の選任について、10人の内の7人の改選非承認をアドバイスしていることが分かりました。
理由はデータ漏洩、システム保守について十分な監督を怠ったとしています。
ターゲットがCEOのグレッグ・スタインヘイフェルを解雇したときにほんとどのメディアは当然ながら彼の責任について書いていたのですが、実はたった一つだけ取締役会の責任に言及していた記事がありました。この視点はすごいなと思いメルマガに書いたのですが、プロのコンサルティング企業が同じ意見を持っているということを知り愁眉が開かれました。
ついでながら資料によると、経営とは独立した取締役会直属の監査役ポジションを設置する企業がアメリカには増えているそうです。この人が取締役会に必要な情報を経営サイドから収集するというわけで、これもまたアメリカらしい職務だなと。5年前にはほんとんどの企業は採用していなかったそうです。
機関投資企業がアドバイスに従って反対投票すると取締役が解任されることになるのですが、果たしてどうなるのか。
株主総会は6月11日に開催されます。
ターゲットが同日宅配の実験を開始すると発表しました。
ミネアポリス、ボストン、マイアミの三商圏で、配送料は10ドルを予定。
また年内に店舗からの発送を開始するとのこと、136店舗を発送デポとするそうです。
別件で、リブリファイという電子書籍サービス企業と提携することを発表しています。
8.99ドルの定額で推奨書籍を読める、他の電子書籍は10~20%で買える、独自のソーシャルプラットフォームで書棚の共有ができる、といったサービスを提供する企業だそうです。
ターゲットがようやくEコマースで動き出しました。
完全に乗り遅れているんですが、他社もみな手探りでノウハウを積み重ねている段階なので、アマゾンやウォルマートに追いつくのは難しいにしても、その他企業の団子レースに追いつくのはそう難しいことではないでしょうね。
コストコがシアトルでタバコの販売を中止すると発表しました。
ただし1店舗のみ。
資料を読んで知ったのですがコストコはタバコの販売を少しずつやめていて、ワシントン州29店舗で売っているのはすでに9店舗のみだそう。
今回はそのうちの1店舗から撤去し残りは8店舗になる、ということですね。
タバコに関してはCVSケアマークが中止を宣言して以来、複数の州のお役所が大手小売企業に対してCVSに追随して売るのをやめろという要請をしています。
コストコはそのプレッシャーでやめるのではなく、単純に売上が下がっているからと説明していますね。
一般消費者ではなく法人によるビジネスユースの仕入れの売上高が高く、タバコは9割だそうなので、周辺のビジネスオーナーの需要次第ということなのでしょう。
まあこういう嗜好品というものは、買いたい人はどこにでも買いに行くものでしょうから、大手がやめたところで喫煙率が下がるということはまずないでしょう。
それとダラーゼネラルのように昨年からタバコの販売を開始して既存店の伸びに貢献しているなんてことを言ってる企業がありまして、どこかがやめれば、どこかがはじめるだけなんだと思います。
ギャップが第1四半期の業績を発表したのですが、とある記事の書き方に興味が引かれました。
「海外も含めた連結で、ネット販売の売上高は13.0%増えたが、店舗が足を引っ張って、総売上高は1.2%増にとどまった」
つまりネットは好調だがリアルは不調で、トータルするとフラット、という意味になります。
まだ表現として定着してませんし、これから定着するのかどうかも分かりませんが、ウェッブルーミングという言葉があります。
店頭で商品を確認しネットで買うのがショールーミングですが、その逆に、ネットで商品を確認して店頭で買うのがウェブルーミング。
日本だとOtoOとかいう難しい表現を使うのですが、ショールーミングとの対比という意味ではこのウェブルーミングの方が分かりやすいですね。
調査では、ウェブルーミングする人の比率の方がショールーミングよりも多い。
さてそう考えると、リアル店舗とネット販売の売上高に線引きする意味があるのか、と言うことになってくるわけですね。
"ネットを強化している!"、"ネットはこんなに伸びている"ということを説明するために分ける必要はあるのでしょうが。
これを突き詰めると、オムニチャネルになる、ということですよね。
ギャップの記事は両方を分けて書いていて、そしてこれからも便宜的に分けた数値が出てくるのが一般なのでしょうが、本質的には双方は密接に絡んでいて分ける意味は薄いのではないか、というようなことを考えているところです。
ペッツ用品ディスカウントストアチェーンのペットコが、中国製トリーツの販売を年内に停止すると発表しました。
トリーツはご褒美用に使うペットフードで、とくにビーフジャーキータイプが問題になっているようですね。
資料によると、食べさせたら病気になったという苦情が、FDA(食品医薬品局)に対して2007年頃から寄せられはじめて、苦情数は4,800件、死亡例も1,000件を超えているそうです。ただ因果関係がまだはっきりしていなくて、FDAは現在も調査中としています。
ペットコの販売中止はこの消費者の苦情をベースにしたものということになります。
競合のペッツマートもこれから追随するかもしれません。
このペットフード問題、日本ではあまり聞かないですよね。
アメリカ人の過剰反応なのか、実はほんとうに危険なのか、真相はいまのところ不明です。
食品の安全性に対する考え方は、メディアがどう騒いだか、が大きく左右してしまうところがありまして、日米を絶えず比較する仕事をしていると、いったい何が本当に安全なのか分からなくなってしまうことがあります。
ウォルマートが第1四半期の業績を発表しました。
売上高が0.8%増、最終利益高が5%減で、増収減益、米国ウォルマートの既存店成長率はフラット、でした。
予測を下回った模様。
また今期の今後の予測もネガティブでした。
良くなかったのでメディアを賑わしているのですが、それはおいて、気になったのは悪天候を理由の一つに挙げていることでした。
天候は小売の売り上げを左右する大きな要因の一つです。
ちょうど同じくメイシーズも業績を発表したのですが、良くなかった理由として天候を挙げていました。
一致してます。
ですから確かに間違いはない。
ただ大きな要因だけに理由として使いやすいんですよね。
昨年も天候を理由としていたこともあって、ああ、またか、と。
それと今後の予測を下げていることも気になる。
天候はもはや関係ないですから。
総店舗数の大半を占め始めた成熟し天井を打ったスーパーセンターを、どうさらに伸ばすのか。
大変なんだろうなと思います。
5/6のニュースなのですが見逃していました。オフィスデポがこれから2年間で400店舗をクローズすると発表しました。
最低でも400店舗、と書いてあるので、数字は増えるのかもしれません。3月末の時点で1,900店舗だそうなので全体の20%強にあたります。
ステープルズが225店舗閉めると言ってますから、トータルすると625店舗。
オフィス専門のチェーン店舗が一気にシュリンクすることになりますね。
この業態、やられてしまった要因は2つです。
1つ目はデジタル化、紙が売れなくなってしまい、周辺商材の市場も縮小してしまった。
キャビネットとか、ファイルフォルダとか、そういう商品群ですね。
2つ目はもちろんネット販売、私自身も最近はオフィス用品を店舗で買わなくなってしまいました。ほとんどアマゾン。
景気の悪化を挙げる人もいますが、この2つが大半だと思ってます。
何回も書いてますが、時代の変化をほんとうに感じます。
ウォルマートが店舗や配送センターで実施している太陽光発電プロジェクトを、2013年を基準として2020年までに2倍にすると発表しました。
2020年までにグローバルベースで70億キロワット/時をリニューアルエネルギーで調達する目標の一環。
先週オバマ大統領が資金調達と環境イニシアチブを目的としてカリフォルニアを訪問、金曜日にマウンテンビュー(サンフランシスコ郊外)のウォルマートを訪問して店内でスピーチをしました。
ウォルマートによる新たな取り組みの発表はこれに合わせたものですね。
この店舗の電力消費量の14.5%がソーラーパネルによるもので、だからこの店舗が選ばれたようです。
もちろん他にもプロジェクトがあって、すべてをトータルして2020年に10億ドルのエネルギーの節約を実現するとしています。
ウォルマートはアメリカで太陽光エネルギーを最も使用している企業です。
下から見えないので気づきづらいのですが、ウォルマート店舗の屋上にはソーラーパネルがぎっしり並んでいるんですね。
写真はウォルマートのHPから拾ってきたもので、ロサンゼルス近郊の店舗です。
アマゾンがニューヨークとロサンゼルスで日曜宅配を開始したのは昨年の11月でした。
この対象都市を15加えて17都市に拡大すると発表しました。
オースチン、シンシナチ、ダラスといった大都市ですね。
日曜宅配を請け負っている宅配サプライヤ-はUSPS(アメリカ合衆国郵便公社)です。
政府管掌の公的機関で、ご多分に漏れず業績が良くない。
ただ最近実感としてUSPSによるネット商品の宅配が増えてきていて、頑張ってるんだろうなという印象が強い。
日曜宅配も再建の一環なんでしょうね。
11月の開始時点で日曜日宅配を請け負っているのはアマゾンだけだとUSPSは回答しています。
ひょっとすると宅配チャージを若干高く設定しているのかもしれませんね。
だから他社は二の足を踏んでいる可能性がある。
日曜宅配は仕事が休みで受け取れる確率が高くなるので、"ネット販売の受け渡し"というボトルネックを広げる役割を果たします。
広がるといいんですけどね。
宅配の競合がきびしい日本では当たり前かもしれませんが、アメリカの宅配事情はまだまだ貧困です。
ちなみに資料によるとネット販売トップ500社中の宅配を請け負っているクライアント数で、USPSは105社(前年98社)、UPSが176社(前年161社)、FedEx144社(前年137社)、だそうです。
ここ数日のアメリカのメディアは、ウォルマートのネット販売売上高の伸び率がアマゾンの伸び率を上回ったという記事で埋まってます。
ウォルマートが30%伸びて100億ドル(2014/1/31末)、アマゾンが21.9%伸びて744億ドル(2013/12/31末)。
Eコマースに特化した業界メディアがリリースしてこれに一般メディアが飛びついたのですが、この数値自体はだいぶ前に分かっていたことで、ただ"伸びが上回った"という見方は私もしていなかったので、なるほどと。
アマゾンは巨大な企業となって伸び率が年々鈍化してますが、ウォルマートはまだこれからですので、この状態はまだ当分続くでしょう。
ただウォルマートが売上をきっちり伸ばしているという点が重要ですね。
アメリカのEコマースへの取り組みでメイシーズが一番だという見方をしている業界人が日本には多いようですが、ほんとうはウォルマートです。
さて今日のお題は伸び率ではなくてウォルマートによる買収。
Adchemyという検索エンジンに特化した企業を買収しました。@WalmartLabsが発足以来これで12社目です。
このAdchemyは、例えば"軽い重さのラップトップ"と検索窓に打ち込んだ場合に、"軽い重さ"という単語に反応するのではなく、重量500グラム以下のラップトップを表示する、という技術を開発している企業だそうです。
この買収は奥が深い。
私は検索推奨エンジンの技術は極めて重要だと考えています。
ネット販売には前方機能(購入ボタンを押すまで)と後方機能(購入ボタンが押されてから商品が届くまで)の2つがあり、双方は等しく重要で、前者はとくに検索推奨エンジンの善し悪しが多くを左右すると私は考えています。
ウォルマートは昨年ポラリスと呼ぶ自前で開発した検索推奨エンジンを投入しており、今回の買収はこれを強化するためですね。
アマゾンやFacebookは自前で開発しつつ弱いところは買収で補っていくということを継続してますが、ウォルマートがやっていることはこれと同じ、ネット企業と同じレベルだと思います。
ちなみに自前の検索エンジンを持っている小売企業は、アマゾンとウォルマートだけじゃないでしょうか。
あとはおそらくアウトソースしているはずです。
ベストバイが強化を発表してますが、自前とするかどうかは現時点では不明。
アマゾンのホームページの1ページ目は、いかにノイズを減らすかということを考え続けて作り込まれているのですが、それでも買うときにはまず最初に検索窓に単語を打ち込んでしまうという購買行動を考えてみれば、検索推奨機能がいかに大事かということが分かると思います。
日本の小売業界はフルフィルメントに偏りすぎてます。
言ってみれば店頭を強化せずにバックルームばかりを強化しているんですね。
それと、Eコマース関連企業買収のニュースを日本の流通業界では寡聞にして聞きません。
もう追いつけないんじゃないかと心配が募るばかりです。
ターゲットのCEOグレッグ・スタインヘイフェルがCEOを辞任しました。
後継は決まっておらず、CFOのジョン・マリガンが暫定CEOとなり、これから後任を探すとしています。
突然の辞任に各紙ともに大きく取り上げているのですが、理由として挙げられているのは、データ漏洩、カナダ事業の赤字、それと本体の業績悪化の3つ。
データ漏洩については投資を怠ってきた責任、業績の悪化についてはEコマースの立ち後れが指摘されています。
ただデータ漏洩問題が出てくる前からターゲットの売場が陳腐化してきているのを感じていたのと、陳腐化そのものはEコマースとは関係ないと思うので、業績悪化の本質的な理由はマーチャンダイジングにあるというのが私の見方です。
ターゲットは前任のボブ・アーリックが大きく飛躍させた企業です。
このアーリックの片腕で、分身とまで言われていたのがスタインヘイフェルでして、懸念材料というものがほとんどなく後継としてCEOになった人なんですけどね。
この人がCEOになってから売場のダイナミズムが失われたと私は感じていました。
問題は次のCEOですね。
ウォルマートは後継者がいつも必ず見えている会社なのですが、ターゲットにはそれがない。
まあステインフェイフェルがこんなに早くやめるなんて誰も想定していなかったというのもあるんでしょうが、でもリスクは必ずヘッジしておく必要はあります。
外から経営者を持ってくると、ターゲットという企業が変わってしまうかもしれない。
ターゲットに大きな転機がやってきたように思います。
ウォルマートがネット販売商品を引き渡すデポ型施設の実験を開始するためにベントンビル周辺で土地を確保し、市にビジネスに関する書類を提出したことをローカル紙が報じました。今年初頭の証券アナリストミーティングでほのめかしていた取り組みで、実際に動き始めたことになります。
このデポで買い物はできず、倉庫形式で商品を在庫し、ドライブスルー形式で商品を渡すためだけの機能を持った施設です。
数多くあるネット販売のボトルネックのうち、商品の引き渡しは大きな障害の一つです。
ウォルマートは宅配以外に、水平展開している店舗ピックアップに加えて、実験としてロッカーや、デンバーでのドライブスルー(業界用語でカーブサイド)など、複数の実験を平行して実施しています。
この実験にこのデポがこれから加わるというわけです。
引き渡す目的だけではなく、小型のフルフィルメントセンターを兼ねてしまうというのもありでしょうね。
おそらく都市部に作ることになるので面積を大きく取ることはできないでしょうから、例えば近隣商圏に向けて非食品のグロサリーだけここから発送するFCとしての機能も持たせる。
このデポ型、実験しているのは私の知る限りではピーポッドだけです。
またZoomin Marketというこのデポに特化したモデルが登場しています。
成否に要注目ですね。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
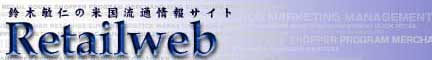



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS