ウォルマートが2009年にマンハッタンにオープンさせたファッション専用のオフィスを閉鎖します。期日は来年の2月1日、機能はベントンビルの本社に移して、本社にある衣料&ホームファニシング部門に統合するとのこと。
このオフィス、衣料をてこ入れするためにオープンさせたもので、調達、デザイン、商品開発といった機能を担っていたのですが、目的は衣料をよりトレンディーにしようというもので、当時の改革の一環でした。
マンハッタンというトレンドの中心地でマーチャンダイジングすれば変わるだろうと目論んだわけです。
ただ実際に変わったんだけど、売れなかった。
ウォルマートの客層がトレンドの最先端を望んでいなかったというわけですね。
同社は戦略を大転換して、今は以前の基本に立ち返ろうとしています。
衣料もベーシック中心とする、そのためマンハッタンのオフィスを閉鎖するというわけです。
つまり今回のこのオフィスの閉鎖は、戦略変更の象徴のようなものと言えるわけです。
今日のWSJ誌が記事の中で小さく触れていたUSDAによる予測数値です。
今年の食品価格のインフレ率が3.5~4.5%となりそうで、昨年の0.8%を大きく上回り、2008年の5.5%に次ぐ上げ幅になるだろうと。
この数値はやはり大きいですよね。
消費環境が悪いので単純に売価を上げるわけにもいかず、パッケージを小さくするとか、メーカーも含めてみな知恵を絞っているわけですが、簡単にはいかないというのが現状です。
もうすでに歳末商戦に突入しているのですが、今年もけっこう難しいシーズンになりそうな感じですね。
ウォルマートが歳末商戦に向けて積極的な価格戦略を導入します。11月1日から12月25日までにウォルマートで購入した商品に関して、プロモーション価格も含めて他社で同じ商品が安く売られていた場合、差額をギフトカードで返金するというものです。
ただし例外があります。
ブラックフライデー用の販促価格、期間切れの販促価格、ネット販売の価格、在庫一掃セールの価格、等々。
先日のアナリストカンファレンスでウォルマートは、これから数年かけて荒利益率と販売管理費率を下げる、すべて生産性ループを回すことによる改善のよるもので、サプライヤー支援や経済の好転といった外部要因にはいっさい頼らない、と明言していました。
これによって価格を下げて行くというわけです。
プロジェクトインパクトの失敗から、価格に徹底的にこだわる取り組み姿勢に方向転換しているのですが、今回のプライスマッチングもその取り組みの一環ということになります。
ニューズウィーク誌がAmerica's Greenest Companiesというランキングをリリースしました。
こういうランキングがあるということを初めて知ったのですが、けっこう面白いですねえ。
小売業界に絞ってみると・・・
8位:オフィスデポ
17位:ステープルズ
19位:ベストバイ
52位:ウォルマート
58位:コールズ
64位:JCペニー
74位:ホームデポ
95位:シアーズホールディング
106位:ホールフーズ
149位:スーパーバリュ
取り組みの大きさやリリースされるニュースなどを見る限りウォルマートが業界を引っ張っている印象が強いのですが、実際はオフィスデポが1番なんですね
意外でした。
それと本来最もグリーンでなければならないホールフーズが結構下の方にいるのも興味を引きます。
売上高大手という観点から見た場合、ウォルグリーンのランクの低さが目立ってます。
また日用必需品メーカーだと、P&G108位、クラフト253位の順位が低いです。
もう一つ、グローバルランクというのがあるのですが、ランクされた日本の企業全48社中、イオン162位、セブン236位と小売業界では二社がランクインしてます。
頑張っているんじゃないでしょうか。
一方日用必需品メーカーだとキリンの474位だけで、味の素とかアサヒビールといった他の大手メーカの名前がない。
エコを吹聴している必需品メーカーは少なくないですが、実際は小売大手二社の後塵を拝しているわけです。
まあこういうランキングはメソドロジー(計算の尺度)によって結果がかなり変わってくるので一概には言えないんですけどね。
バーンズ&ノーブルはすでにサイトで書籍以外のカテゴリーを販売しているのですが、これを拡大する予定であることが分かりました。
ホームプロダクツ、家電、アート&クラフト、玩具&ゲーム、ベビーの5つを新たなカテゴリーとして新設、100万アイテム以上を追加します。
ただし直営ではなくて実際には別企業が販売するマーケットプレイス形式となります。
目的は書籍のみに依存するいまのビジネスモデルを変えることにあるようですね。
とりあえずやってみるということなんでしょうが、しかし時すでに遅しかという印象が強いですね。おそらくリスクをあまり取らない形式だろうと思うのですが、ローリスク・ローリターンですしね。
Global retail Theft Barometerと呼ぶ店頭犯罪の調査結果がリリースされました(スポンサーはチェックポイントシステム)。
主な数字をピックアップすると・・・
・2011年の被害の総額は417億ドル(売上高の1.6%)
・つかまった従業員の総数は69万7,000人、一人当たり平均額は$1,764.76。
・客による万引きは1,700万件、1件当たりの平均額は$373.64。
・不明ロスの最も大きなカテゴリーはアパレル、次いでHBC。
・ドラッグストアが狙われやすい、理由は規模が小さいので大型店舗のようなセキュリティ強化ができないこと。
まだ2011年は終わっていないのに2011年の数値となっている意味がよく分からないのですが、とりあえず細かいことはおきます。
統計上、店員による犯罪額が大きく、いちおう内部犯行と外部犯行を分けていますが、しかし内部と外部の犯行は線引きが難しいことが指摘されてます。
つまり、店員が手引きして外部犯罪者が関与するような場合、線引きはできませんよね。
内部犯行の数値が大きいと言う話は知らない人が聞くと驚くのですが、小売業界の内部の方ならよく分かっていることだと思います。
いたちごっこのようなところがありまして、小売側も犯罪者側も、双方ともに年々技術を上げていきますから、特効薬が存在しない点が悩ましいところです。
先週の木曜日にギャップが株主総会で出店戦略を発表、米国内の189店舗を2013年末までに閉鎖する予定であることが分かりました。現在の店舗数の21%に相当します。
同社は2007年からリストラに取り組んでいるのですが、この年から2010年にかけて、店舗面積で10%、店舗数で34%の削減を目標にしているとのこと。
2007年の2013店舗から来年末には700店舗になります
感覚として、モール内に出店するファッション系の専門店チェーンの店舗数は全米で700~800店舗ぐらいが一つのピークだと思ってます。なので普通の大手チェーンのレベルに戻るというような印象を個人的には持ちますね。
とにかくまずは縮小均衡しようということなのだと思うのですが、課題は相変わらず商品政策とマーケティングにありますよね。店舗に入っても、ワクワクするような楽しさを感じることがすっかりなくなってしまいました。
これはファッションリテールには不可欠な要素です。
ギャップに過去の栄光が再び戻ることがあるのでしょうか・・・。
アマゾンが商品引き渡し用のロッカーを実験するそうです。
ロッカーは小売の店舗内に設置し、6桁の暗証番号をお客に提供し開閉してもらって商品を引き渡す。
7月にこういう記事をエントリーしました。
セブンイレブンでの商品引き渡しの実験開始
セブンイレブンに加えてライトエイドにも設置するそうで、私が書いていたとおり取り組み相手を増やしたようです。
それとロッカーを使う点が日本のコンビニ受け渡しとの相違点でしょうか。セキュリティを考慮したのかもしれません。
あとはスーパーマーケットに設置すれば使えるようになるかもしれませんね。
取り組む小売企業が増えると便利になるかもしれませんが、しかしアマゾンとの競合問題もあるので限界もありそうですね。
ウォルマートは、ネイバーフッドマーケットをウォルマート・マーケットへとネーミングを変更すると言っていました。
ところが、リリースに出てくる名称はネイバーフッドマーケットと昔のままで、アナリスト・カンファレンスでも同じくオリジナルの名称を使っていたので、いったいどっちが正しいのだろうと思っていたんですね。
今日、オープンしたばかりの店舗を訪問して、ウォルマート・マーケットが正しいのだということを確認しました。
この店、面積は62,800sqf(約1,800坪)で今までのプロトタイプよりもかなり大きいのですが、店内の部門構成を見て、なるほどこういうことかと納得しました。
いくつかタイプを作って、出店に柔軟性を持たせるのでしょうねえ。
最近のスーパーセンターは白色のゴンドラを使っているのですが、この店は黒を使っていて、西友に迷い込んだような気分になりましたよ。
ウォルマートがプロジェクトインパクトに失敗して、現在は過去への回帰モードにあるということをご存じの方も多いことでしょう。
減らした販促スペースを戻そうとしているのですが、陳列什器を処理してしまい、すべてをすぐに過去と同じ状態には戻せないという悩みを抱えています。
写真はエンドの横につけるサイドキック(ウォルマート用語)なのですが、この什器も失ってしまったため、ほとんどの店舗では、何らかの販促はやってはいるのですが標準化されておらずみんなバラバラという状況です。
このダラスの店舗はおそらく偶然いくつか残っていたんでしょうね。
サイドキックはおそらく新たな標準タイプがこれから導入されることでしょう。
どんな形式になるのか楽しみいています。
ちなみにエンドの横のプロモーションスペースも標準化すべし、これが私の持論です。
 99センツオンリーストアのバイアウトが決まりました。買収に合意したのは投資企業と年金組織、総額は16億ドルです。
99センツオンリーストアのバイアウトが決まりました。買収に合意したのは投資企業と年金組織、総額は16億ドルです。
これから株主の承認を経て正式に買収が成立します。
99センツオンリーにはいままで何度か買収オファーがあり、しかし株主に拒否されて買収が成立しなかった経緯があるのですが、今回は買収提案額が高めなので決まるんじゃないでしょうか。
この企業、10年ぐらい前までは店舗で勢いを感じたものなのですが、最近は力強さをめっきり感じなくなってしまいました。創業社長が退いて娘婿が経営をはじめてからオペレーションパワーが弱くなったように思ってます。
しばらく投資企業の傘下にいて、資産の整理をして企業価値を上げて、ひょっとするとその間に経営者が代わり、どこかにすべて売却して創業一族はお金を手にして退く、というシナリオなんじゃないでしょうかね。
<追記>
明日より研修のコーディネートで出張となるためアップデートがまばらとなりますがご容赦ください。時間があれば、店舗の情報でも載せたいと思っています。
カリフォルニア州においてセルフレジしか置かない店でお酒を売ることができないとする規制が成立しました。来年の1月1日より販売が不可能となります。
お酒を売りたければ必ずフルサービスのレジを最低一つ設置しなければなりません。
この規制、フレッシュ&イージーを狙い撃ちするものであります。
セルフレジのみでお酒を売っているリテーラーはフレッシュ&イージーだけですから。
実は規制化に向けて後ろ盾となって強くプッシュしたのがUFCW(食品労働者組合)でして、なぜかというと、フレッシュ&イージーが非組合企業だからなんです。
UFCWは、ウォルマート、ターゲット、コストコ等の組合化を認めない大手企業に対してあらゆる手を使って攻撃をかける組織で、例えばウォルマートに対するアンチ運動が有名ですが、今回はお酒を武器にしてフレッシュ&イージーを狙い撃ちして成功したというわけです。
セルフレジとは言うものの必ず担当者が一人いて、酒をスキャンするとその店員が年齢確認するまで買えない仕組みになっているので、セルフレジでもほぼ問題ないと思います。
それとフルレジを最低一つ置くことを条件としているのですが、"セルフレジでお酒を買う"という購買行動はいずれにしても可能なわけで、フルレジが必要だとする意味がどこにあるのかよく分からない。
"フルレジのキャッシャーがセルフレジに目を光らせる"ということかもしれないけど、それならば、セルフでも担当者が一人いるわけだから何も変わりませんよね。
アメリカの酒規制は古い時代を引っ張っていてもともと不合理な点が多いのですが、ここに組合が絡むとさらに不合理になるということでしょうかね。
まあ消費者としてはいずれにしてもレジを通らなければならないのでそれほど大きな不都合はないのですが、フレッシュ&イージーはちょっと大変ですね。1月1日に向けて、フルレジを設置し、キャッシャーを雇わなければなりません。
何か抜け穴でも見つけない限り、コストアップは避けられない状況となりました。
テスコが第2四半期の決算を発表し、その中で米国事業についてコメント、フレッシュ&イージーの赤字が減って来年度中の黒字化は予定通りだそうです。
半期で売上高は4億7050万ドルで前年比23.1%増、赤字は1億1300万ドルで昨年同時期の1億5100万ドルから改善されました。
"これからの半年が非常に大きい、どれだけ売上を伸ばし赤字を削減できるか。自信を持っているが、この6ヶ月間がカギだ"(フィリップ・クラーク)
ここまで言明してダメになるということはまずないと思うので、フレッシュ&イージーは軌道に乗り始めていると思って間違いないように思います。
画像はリモデルフォーマットに導入されたインストアベーカリーです。
フレッシュ&イージーのインストアベーカーリー
パンのインストア加工って肉や魚と比較すると作業工数が少なく、熟練を必要としないから導入したのでしょうね。
ベストバイがナプスターを競合のラプソディに売却することを発表しました。売却額は明らかになっていません。
ベストバイは2008年に1億2100万ドルでナプスターを買収、音楽のデジタルサービスを自ら強化しようとしたのですが、リアル店舗やネット販売サイトとの相乗効果を上げることができませんでした。
推定では現在の登録者数は20~30万人で、買収時の70万人から大きくお客を減らしてしまったようです。
なぜ伸ばせなかったのかという点について説明した資料がないのですが、買収した時点がピークだった、ベストバイにマネジメント能力がなかった、ラプソディやSpotifyといった競合が増えてしまった、といった理由が考えられます。
とくに広告収入を土台とした無料サービスを提供しているSpotifyなど新たなビジネスモデルの台頭が、かなり影響を及ぼしているような印象です。
エンターテイメントカテゴリー(音楽、映画、ゲーム、書籍)は今激動のまっただ中にあるということを実感するニュースです。
8月末期末のコストコが決算を発表、同時に年間の会員費を値上げすることを明らかにしました。
値上げは11月1日から、値上げ幅は10%(50ドル会員が55ドル、100ドル会員が110ドル)です。
値上げする理由は、原価が上昇している環境で、商品売価を値上げせず現状を維持するためには会員費を値上げせざるを得ない、とのこと。
コストコの値上げは5年ぶりだそうです。
競合のBJ'sは年初に45ドルから50ドルへ値上げしているのですが、一方サムズは40ドルを5年以上維持しています。
このコストコの値上げがどう影響を及ぼすのか、実に興味深いです。
コストコはサムズに比べて一店舗当たりおおよそ1.5倍ほど売上高が高い。マーチャンダイジングがそれだけ魅力的なわけです。
しかしお客はこれからその魅力と15ドルの差をてんびんにかけて行くことになりますよね。
10%程度なら乗り換えは起きないと踏んでいるコストコの読みがあたるのか否か。
今後の推移を見守りましょう。
ターゲットCMOのマイケル・フランシスがJCペニーへ移籍することが明らかになりました。
ターゲットのマーケティング技術は非常に高く、メーカー並みかまたはそれ以上の水準を誇っているのですが、これを支えていたのがフランシスでした。
なので、ちょっと驚いたのですが、これ、おそらくアップルからJCペニーに移ったロン・ジョンソンが引っ張ったんでしょうねえ。
ロン・ジョンソンは元ターゲットのマーケティング担当の上級副社長ですから。
JCペニーのマーケティングが変わるかもしれません。
<追記>
ただいま研修コーディネート中です。明日と明後日、エントリーができないかもしれませんがご容赦ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
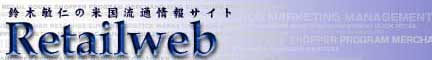






最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS