ネット販売で買われた商品の宅配に店舗に来ているお客を活用するアイディアをウォルマートが検討していることをメディアが報じています。
ウォルマートはデリバリーコスト削減のためにネット販売によるオーダー商品を店舗から発送する実験を25店舗で実施しています。発送元をデリバリー先に近づけようという試みで、店舗を持たないアマゾンに対するアドバンテージを狙っています。
今年中に50店舗に拡大予定で、将来的にはさらに広げてゆくとしているのですが、ここで宅配業者を使わず、店舗に来ているお客を募って買い物の帰りに配達してもらいさらにコスト削減をはかってみようというコンセプトです。
TaskRabbitの宅配版、Zipmentsの店舗版、といったイメージのようですね
こういう場合、デリバリーを請け負う人による万引きや遅配を心配するのが普通だと思うのですが、それよりも最大の課題はデリバリーする人のライセンスや保険をどうするかだそう。
地域によっては宅配業者にライセンスが必要だったり、商用商品の宅配には保険加入を義務づける規制があったりするからです。
ウォルマートの担当者は、まだコンセプト段階なので実施するのかどうかは現時点では分からないとしているのですが、こういうことを検討すると言うこと自体、ウォルマートらしいというか。
イノベーションを起こすには、こういう斬新なコンセプトの積み重ねが必要になります。
考えてみたら、日本の小売企業にR&D的発想って乏しいですよね。
大手企業だけでも良いのでR&D部門があっても良いのではないでしょうか。
JCペニーが売上減に歯止めをかけるために値下げ販促を復活させることはすでに先月発表されていたのですが、今月から実際に始まりました。
具体的にはプライベートブランドで価格販促を実施するとのことで、例えば現在5ドルで販売されているTシャツを6ドルとして、価格販促用の粗利を確保するとしています。
これから数週間でプライスタグの付け替えを終えるそうです。
これでお客は満足するのでしょうかね。
もしそうだとしたら、価格販促漬けという麻薬性は、売る側だけではなく、買う側にもあるということの証左となります。
EDLPを理解できないお客に問題があると言うよりも、その価値を伝えきれていないJCペニー側に問題があると考えるのが正しいのだろうと思うのですが、ハイローからEDLPへの切り替えは非常に難しいという事実をJCペニーの事例は我々に例示しています。
フォーチュン誌が恒例のWorld's Most Admired Companies(世界で最も賞賛される企業)を公開しているので共有しておきます。
1:アップル
2:Google
3:アマゾン
4:コカコーラ
5:スターバックス
6:IBM
7:サウスウェスト・エアライン
8:バークシャー・ハザウェイ
9:ウォルト・ディズニー
10:フェデックス
以下、小売企業を抜き出します。
16:ノードストロム
19:ホーズフーズ・マーケット
22:ターゲット
23:コストコ
27:ウォルマート
45:ホームデポ
今回のポイントは、アマゾンが10位以内に入って小売業界トップになったこと、ここ数年上位にいたウォルマートがランクを下げたこと、といったところでしょう。
50社中に小売企業は7社、比率にすると14%。
いわゆるCPGと呼ばれる消費財メーカーは7社なので、小売業界の方が評価が高いということいなりますね。
いつもならがアメリカにおける小売業界の価値というものを感じます。
2月にウォルマートがiPhoneアプリを利用してのセルフスキャンの実験を開始したと言う記事をエントリーしましたが、実は昨年末頃からアトランタやベントンビルといった他地域でも実験していて、これを拡大する予定であることが分かりました。
拡大するのは、ダラス、ヒューストン、オースチン、ポートランド、フェニックスで、トータルでおよそ200店舗程度になるとのこと。
iPhoneのアプリを利用してのセルフスキャンを実験
仕組みを読めば分かるとおり、結局これはセルフレジを延長するコンセプトに過ぎませんよね。
お客がセルフレジでスキャンするという作業を、買い物中にシフトさせているだけです。
そしてお客の所有物としてのスマホをスキャンデバイスとして利用する。
ウォルマートによる新たな投資のほとんどはアプリの開発だけですから、これからさらに拡大する可能性は高いでしょう。
また他企業が採用する可能性も高いのではないかと思っています。
ターゲットがキッチンウェアを売るネット販売企業を二社買収しました。
CHEFS CatalogとCooking.comの二社で、買収後に統合して一つとし、傘下企業として運営するとしています。
しばらく独立ブランドとして取り扱いつつ、どこかの時点でターゲット内のブランドとして取り込んでしまうのでしょう。
ネット販売はリアルな小売ビジネスとはパラダイムが異なるので、なかなか成長させづらいですよね。
なので、固定客をすでにつかんでいるネット販売企業をリアルリテーラーが買収してしまうのは戦略としては有効だと思います。
ホールフーズがヘルシーライフをテーマとしたリゾートホテルを開発し実験するようです。
USAトゥデイ紙が独占記事として報じています。
場所は本社のあるオースチン、オープニングはこれから三年以内、運営委託先としてホテルチェーンと交渉中。
宿泊客の逗留中にヘルシーなライフスタイルを学んでもらう、がコンセプトだそうです。
CEOのジョン・マッキーは、成功するかどうかは分からないが、うまくいったら増やすかもしれない、とコメントしています。
いかにもホールフーズらしいアイディアですよね。
既成の常識にととらわれずにトライアルを繰り返すのがホールフーズです。
しかしアメリカの小売企業がホテル開発に乗り出すというのは非常に珍しい。
少なくとも私は記憶にありません。
完成が楽しみです。
<追記>
10日ほどの予定で東京に滞在中です。
16日の土曜日にドラッグストアショーに行く予定です。業界人はすいている金曜日に訪問するそうなのですが、残念がらアポが入っており、時間を作れる土曜日としました。14時頃から15時頃を目安として花王さんのブースにいるつもりです。もしこのブログをお読みで土曜日に行く予定のある方はぜひお越しください。
アメリカではなくイギリスのネタなのですが、興味を引いたので。英アズダが倒産したHMV買収で交渉していると地元紙が報じたようです。
アメリカ資本のサルベージ企業、ヒルコが買収で動いているので、競札になるのかもしれません。予想買収額は5,000万ポンド。
物件に興味があるのかと思ったら、そうでもなくて、エンターテイメント部門の強化に利用する可能性が高い模様。
おそらく売場にHMVという名称をつけて、"店舗内店舗"とするのでしょう。
売上が落ちたHMV店舗をどうするのかは不明です。
なるほどこういう目的の買収もあるのかと興味を引いたのですが、もう一つ、ウォルマートも各国それぞれいろいろな戦略があるなとあらためて感じ入ったのでした。
十把一絡げにはできませんね。
JCペニーが2,200人のレイオフを発表しました。
本社人員約1,000人をカットしたという記事をすでに昨年中にエントリーしているのですが、今回出た資料によると昨年解雇されたトータルの人員数は4桁では済んでおらず5桁、1万9,000人にのぼるようです。
ちなみに今回は店舗が中心で、全1,100店舗の10%にあたる110店舗の店員が減らされます。
売上が大幅に落ちているので併せるように人員も削減しているというわけで、言ってみれば縮小均衡しようとしているような印象ですね。
JCペニーの苦戦が続いています。
ターゲットは昨年からコスメの対面販売をシカゴエリアの28店舗で実験しているのですが、実験地域を拡大することを発表しました。
どの地域に何店舗かは不明。
アメリカのコスメ市場はデパートの対面販売(プレスティージ)と、それ以外のセルフ販売(マス)の二極に分化していて、マス市場は完全セルフです。
ウォルグリーンのようにコスメに売場担当者を置く企業も存在しますが、対面でコンサルテーションしながら売る機能を担っているわけではないので、セルフと言って間違いない。
こういう市場で対面の実験をするというのは、ある意味画期的なんです
マスビューティが強いターゲットだからこそという感じですね。
数年前にブーツが一部の店で対面やってたのですが、やめてしまいました。
またロサンゼルスのアーバンエリアの店舗で対面担当者を置いていますね。資料だとシカゴで実験となっているのですが、ロサンゼルスでもやっているのではないかと思います。
こういう人件費が追加で必要となる取り組みの場合、アメリカの小売企業は非常にシビアに生産性やリターンを見極めようとしますので、成否は注目できるでしょう。
ちなみにターゲットによる対面サービスの取り組みとしてはもう一つ、ベストバイのギークスクワッドをデンバーの20店舗で実験中で、これもカンザスシティの20店舗に拡大することが分かっています。
グーグルが同日宅配の実験を開始しました。名称はグーグル・ショッピング・エクスプレス、ローカルの中小小売企業が対象で、グーグルが宅配業者をアレンジし、ローカル店舗で商品をピックアップし購入者にその日に届けるというサービスです。
場所はサンフランシスコ、実験期間は最低一ヶ月となっています。まだ実験の初期段階でお客がいくら支払うのかといった正式な価格設定は未定。
資料によるとグーグルはマーケットプレイス(楽天のような場所貸し型のネット販売)に参入したいのだそうですね。
グーグルで検索し、アマゾンの商品が表示され、アマゾンで購入、これによってグーグルにはクリックによる広告費が入ってきたわけですが、最近の消費者は最初にアマゾンで検索してしまうそうで、グーグルの商売が減じてきた。
だから自らがマーケットプレイスを運営してしまいたい、というのがその理由です。
決済システムから宅配のアレンジへと、グーグルがどんどんEコマースに進出してきています。
米国事業トップのビル・サイモンが金融機関主催のカンファレンスでスピーチ、6万sqf(1700坪)以下の小型フォーマットの出店を加速させるとコメントしました。
年内に115店舗の予定で、このフォーマットの店舗の出店ペースとして過去最大となるそう。
またネイバーフッドマーケットは2016年までに500店舗を目標としています。
ウォルマートは6万sqf以下を小型フォーマットとひとくくりで定義していて、115のうち何店舗がエクスプレスになるのかは言明していません。
この小型店、私が見る限りゾーニングやレイアウト、カテゴリーのアソートメントの厚さが各店舗けっこう異なっていて、フォーマットを統一することによるオペレーションの効率化というものを求めていないように感じています。
たぶん居抜きが多くなるため店形が統一できないことと、周辺商圏のニーズや競合環境がすべて異なるためだろうと推測しているのですが、ある意味日本的とも言えて面白いなと思っています。
研修のコーディネートが終わり通常業務に戻りました。少しずつ追いついていこうと思います。
まずベストバイから
買収を画策していた創業者のリチャード・シュルツが締め切りまでに買収オファーをしなかたため、バイアウトはご破算になりました。
バイアウトに必要なおよそ80億ドルが調達できなかったということになります。
ただし全株式を買うのではなく一部を買うといった別のオファーをする可能性は残っている模様。
ベストバイにとって、上場企業として営業を継続した方が良いのか、それとも非上場となった方が良かったのか。
いまのベストバイにシュルツという求心力のある創業者が再び必要なのかもしれないし、再建に長けた現CEOの手腕に賭ける方が良いのかもしれない。
どちらが良かったのかは今後の業績次第ということになるわけですが、新CEOのお手並み拝見といったところですね。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
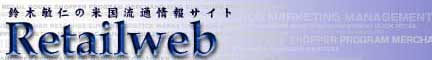




最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS