クローガーのCEO、デイビッド・ディロンによるアナリストカンファレンスでの発言です。
「宅配がすべてに一気に置き換わると決めてかかるには早すぎる」
ネット販売を好む人がいるというは理解しているが、買い物に外出する、店舗に行って地域の顔見知りと交流する、といったことを好む人がまだたくさんいる、ということを説明して、ネット販売を強調したがるアナリストを牽制しています。
儲かるのかどうかも重視すべきだということも言っています。
食品がネット販売でどうなるのかという議論はいままさに百出といった趣を呈しています。
時代は来るという意見と、まだ早計だという意見。
ディロンは明らかに後者ということになりますが、ただ自らが属するベビーブーマーの見方であって、ミレニアム世代が果たしてそうなのかというと、まだよく分からないというのが実情なのではないかと思います。
また現時点では、という但し書きが必要で、これからの進化でさらに使いやすくなったら普及が進むのかもしれません。
まあ少なくとも食品や日用雑貨のネット販売化のスピードは家電等のカテゴリーと比べると遅いだろうということは言えると思っています。
2012 Global Brand Simplicity Index、というランキングがあります。
直訳すると「ブランドの簡素さランキング」とでもなりますが、つまりブランドが伝えているメッセージ性のシンプルさで順位を付けたものですね。
グローバルがメインですが、アメリカのランクもあって、そこから小売企業を抜き出すと以下の通りとなります。
1、アマゾン
2、パブリックス
3、ザッポス
4、H&M
5、ターゲット
6、クローガー
7、イケア
8、トレーダージョーズ
9、ビクトリアズ・シークレット
10、ギャップ
こういうところにパブリックスが顔を出しているところが興味深い。
店を見る限りでは決して突出した新しい何かをやっているスーパーマーケットではないんですが、だから凄いんですよね、この企業は。
私は「シンプル」信奉者です。
シンプルにすることは、複雑にすることよりも難しい。
日本の小売企業はとにかく、複雑に、複雑に、へと進んでいく傾向が強いですよね。
ポイント制などはその最たるものだと思ってます。
今回取り上げたのはランクに入っている企業云々ではなく、こういうランキングがあること自体に注目したいからです。
シアーズがランズエンドとシアーズオートセンターの売却の検討を始めたとメディアが報じました。
「広範囲な戦略見直しの一環」となっているので、他にもいろいろありそうですね。
シアーズは店舗の切り売りをして運転資金を捻出しています。
リース契約が切れるときに更改するかどうか見直し、見込みの他立たない店舗は売却、としているのですが、黒字店舗もケースによっては売却しているようです。
結局のところ、ランパートは極めて低価格で買収しているので(おそらく不動産価値のみ)、ダメなら売って元を取れば良いということなんでしょうね。
どこまで縮まって均衡するのか、興味はこの一点です。
ターゲットカナダが11月に33店舗をオープンさせます。
11月13日に31店舗同時オープン、11月22日に2店舗で、合計33店舗。
ターゲットはカナダで2013年末までに124店舗をオープンさせる予定で、これで目標店舗数に達する模様。
ターゲットは年末に大量出店をよくやります。
ターゲットに限らず、この時期に出店を集中させる企業は少なくありません。
伝わってくる情報によると、カナダのターゲットは当初言われていたほどお客が入っていないようですね。
カナダ人はアメリカをよく知ってますから当然ターゲットの知名度も高く、海外企業というハードルはないだろうと見られていたんですが。
私が見る限りアメリカとほとんど同じマーチャンダイジングなのですが、これから修正をかけていくのかもしれません。
ドラッグホールセラー大手のマッケソンがドイツの同業セレシオを買収することで合意したと発表しました。
総額はドルベースで84億ドルという大型買収で、もし規制当局や株主の許可が出て買収が成立すると、双方合わせて20カ国にまたがる年商1,500億ドル(1ドル100円換算で15兆円)という巨大な企業が誕生することになります。
製薬メーカーのグローバル化が進行する中で、ホールセラーも軌を一にしてグローバル化を急ぎ始めました。
ウォルグリーン、アライアンス・ブーツ、アメリソース・バーゲンという連合結成も影響を及ぼしているのかもしれません。
資料によると市場としての狙いはアジア、特に中国のようなのですが、欧米企業の巨大化がどう影響するのか。
また日本への影響はあるのかどうか。
興味は尽きませんね。
サーベラスがセイフウェイのバイアウトに動いているとロイターが報じました。
セイフウェイは動きを承知していてゴールドマンサックスを雇ってオプションを検討しているとも報じています。
当然セイフウェイはノーコメント。
バイアウトされるということは株価が低いのかと思い調べてみましたが、いまは過去52週の最高値で、PEも19あるので安くはないですね。
サーベラスの思惑はおそらく傘下にあるアルバートソンズとのシナジー効果でしょう。
市場に重なりが少ないのでFTCの介入の可能性も低そうです。
ドミニックスの売却を決めたセイフウェイですが、買う相手を決める前に自身が狙われているというわけです。
セイフウェイは80年代にKKRに買収されて業績を立て直した歴史があり、こういう話にはよく慣れた企業ではあります。
アマゾンが宅配料無料となる最低購買額を25ドルから35ドルに値上げしました。
ほぼ10年ぶりの値上げとのことです。
おもしろいのは、プレスリリースには出ていないこと。
値上げのようなネタは書かないんでしょうね。
静かに値上げし、お客はふと気づくまだだまっている、といったところでしょう。
この35ドルという金額は、実は決して高いものではなく、例えばウォルマートは50ドル買わないとフリーにはなりません。
でもベストバイやバーンズ&ノーブルは25ドルがミニマムなので、競争力を持っているとは言いがたい。
プライムへ誘導するためと憶測されているのですが、どうなんでしょう。
アマゾンはおそらく創業以来、送料は赤字とする戦略をとってきているのですが、この戦略に何らかの変更があったのかどうか。
基本的にアマゾンは戦略戦術について語らない企業なので、真実はいまのところ分かりません。
ちなみに日本はではセンター在庫商品はすべて送料無料ですが、これは送料をロスリーダーとしてシェアを拡大しようとする日本のみにユニークな戦略です。
アマゾンの肩を持つわけではないですが、つまりいまは安かろうと高かろうとアマゾンでどんどん買った方がお得ということになります。
どこかの時点でミニマムオーダーが設定されるでしょうね。
既存店のパーキングスペースにガソリンスタンドを設置する実験を開始しました。
場所はアラバマ州、店舗は大型のダラーゼネラルマーケット、ベンダーを利用しての実験で、一年間の実験後にベンダーと共同で結果を査定して水平展開するかどうかを決めるそうです。
ダラーゼネラルはコンビニエンス性を競合の武器にしたフォーマットですから、ガソリンは整合性があるんじゃないでしょうか。
成否を握るのは価格ですが、おそらく原価に近い売価を設定することでしょう。
アメリカではウォルマートやコストコ、スーパーマーケットがガソリンスタンドを併設させていて、低価格で売るため、競合する体力のないガソリンスタンド事業者が撤退に追い込まれるのを実際に目の当たりにしていまして、そういう事例がありますから、ダラーゼネラルも軌道に乗せてしまう気がしますね。
先週は一週間小売企業の研修コーディネートで記事を書いている時間が取れず、エントリーができませんでした。
言い訳がましいですが、一日店を見て歩くと体力をかなり消耗し、エントリーする気力がなくなってしまうのですね。
申し訳ありません。
さてこの店舗視察中に、ニトリの米国進出1号店(店舗名はAki-Home、2店舗同時オープン)を見てきました。
ちょうど行く予定だった著名なショッピングセンターへの進出で、行程を無理に変えることもなく行くことができたのですが、ということはこれから日本の流通視察グループがどんどん行くことになるのでしょうね。
ユニクロもそうですが、このアメリカで日本企業には頑張って欲しいと強く思います。
いろいろ考えることがあったのですが、ここでは3つだけ。
1つめはPBを売るという茨の道。
ざっと見る限りPB比率が非常に高い。
売上を伸ばすにはNBメーカーの力を借りるのが王道なのですが、それをしないということは自らがPBをマーケティングしなければならず、ハードルは高いと言わざるを得ない。
当然のことながらAki-Homeもニトリもアメリカでは知名度ゼロ。
フレッシュ&イージーはPB比率50%強で、200店舗まで増やして、でもだめだった。
あのテスコでさえ挫折したわけで...
ゼロからブランドを売って行くには、有能なマーケティング担当者を雇い、広告代理店を上手に利用して、相当インパクトのあるブランディング活動を継続する必要があるでしょうね。
既存の店舗がすでにブランディング活動となっている日本とは状況が違いますから。
2つめは日本語パッケージの日本の商品が置かれていること(一番下の写真)。
アメリカ向け商品がこの大切なグランドオープニングに間に合わなかったのだとしたら、担当者は切腹ものかと。
もしあれをアメリカ人に売るというのなら、それはそれで凄いことではあります。
3つめは撤退戦略を決めているのかどうか。
テスコはアメリカ進出前に総投資額を決め、これを公言し、その額に達する前に撤退を決めました。
いわば、事前に決めたことに則って、粛々と撤退する、ということになります。
このあたりは証券アナリストや機関投資家に確認して欲しい事項ですね。
海外事業を成功させるというのは極めて難しいことで、ファミマやオートバックスといった日本企業に限らず、カルフール、テスコ、ベストバイ、ホールフーズ等々、大多数の企業が成功させていません。
ましてや今回のニトリのように買収ではなくゼロからとなると、コストコやイケアなどごくわずかしかいません。
その間に、星の数ほどの企業が失敗しているわけです。
確率から言うならば、ここでニトリが成功すると言うことは宝くじがあたると公言するようなもので、私にはとても言い切る勇気はない。
ですからもしニトリが米国事業を成功させることができたらなら、歴史に残る金字塔になることでしょう。
日本人の大好きな「おもてなしの精神で」という数値化できない抽象的な表現を米国戦略で使わないことを祈っています。
ダラーゼネラルが1万1,000店舗、ファミリーダラーが8,000店舗と、両チェーンストアが相次いで区切りを超えました。
ダラーゼネラルは10月5日にテネシー州、ファミリダラーは10月10日にサウスカロライナ州で、双方ともに店舗前でセレモニーを実施したようですね。
両方合わせて1万9,000店舗で、2万店舗の大台を超えるのは時間の問題でしょう。
この二社はまだまだ伸びるだろうというのが大方の予測なのですが、ただウォルマートが小型フォーマットの強化を始めたりして競合状況が強まってきており、そろそろスローダウンするのではという憶測も出始めていますね。
証券アナリストによる、合併した方がいいんじゃないかという論評すら出ています。
まあ投機的な意見ではあるのですが、そろそろ風向きが変わるかもしれないという視点を持ちながら見る必要があるのかなと思っています。
昨日のエントリーでセイフウェイがシカゴから全店閉鎖で撤退すると書きましたが、売却による撤退となるようなので、訂正します。
丸ごと売れないので、切り売りしてゆくようです。
さて表題の件、デパートメントストアのニーマンマーカスがオムニチャネルプロジェクトに1億ドルを投ずると発表しました。
"全ブランドとチャネルに横断的なマーチャンダイジングプラットフォームを数年かけて構築する"とのこと。
1億ドルは日本円でおよそ100億円ですね。
何をどうするのか現時点では不明ですが、事例として参考になると思うので、これから追ってみたいと思っています。
セイフウェイがシカゴのドミニックスを全店閉鎖すると発表しました。
店舗数は72店舗、時期は来年早々とのこと。
セイフウェイがドミニックスを買収したのは1998年で買収額は12億ドルでした。
ところが買収後の組織運営に失敗し人材がごっそりと抜けて業績が悪化、2003年頃に売却を決定したのですが売り先が見つからず、そのまま塩漬けとなっていました。
噂ではセイフウェイによる資金の投入がなければほぼ倒産状態とも言われていて、店舗を見る限りいつも閑散としていてそうかもしれないなと感じていたものです。
15年かけて投資をゼロにしてしまったというわけですね。
セイフウェイはカナダ事業を売却したばかりですが、おそらくこれで相殺ということなのでしょう。
ドミニックスが抜けて、これからシカゴ商圏がどうなるか楽しみです。
10%程度のシェアは持っているはずなので、これをどこが吸収するのかという話となります。
セイフウェイの資産整理、残るはテキサスのランドールズですね。
こちらはウォルマートにやられているようで、いまも赤字のはずです。
ウォルマートがインドでのジョイントベンチャーを解消すると発表しました。
現地のバーティとの50%の出資比率で事業を展開、キャッシュ&キャリーを20ヶ所まで増やしているのですが、バーティの持ち分を買い取って100%子会社化するそうです。
理由は現時点ではよく分からないですね。資料を読んでいるのですが、はっきりと書いていない。
インドは外資による小売事業参入を規制していたのですが、昨年51%の出資比率ならOKと規制を緩和しています。ウォルマートがキャッシュ&キャリーとしているのは小売がダメだったからで、これは大きな方針転換なのですが、まだ一社も申請していないそうです。
表面的には規制は緩和されたけど、何か障壁が残っているのでしょうね。
それとキャッシュ&キャリーなら100%外資でもOKになったようです。
だから合弁解消、というわけでもないようで、よく分かりません。
メディアによると、意見衝突のような理由ではないので、今後規制環境が変わったら再び合弁に戻るかもしれないと書かれています。
いずれにしても、ウォルマートのスタンスは粘り強いですね。
結局のところ、米国内や他の海外事業でちゃんと利益を出し続けてますから、長期に事業を継続することができるというわけです。
テスコがアメリカや日本から撤退したことの本質は、英国内が傾きはじめて、赤字事業を長期的な投資案件として持ちつづけることができなくなったからですから。
本日も先週のニュースから。
アマゾンが歳末の臨時雇用予定数を発表、昨年対比で40%増えて7万人となることが分かりました。
ウォルマートが5万5,000人、ターゲットが7万人、トイザらスが4万5,000人、コールズが5万人という数字が公表されてまして、比較するとアマゾンの7万という数値はやはり多いということが分かります。
昨年対比で40%増ですから業績アップを見込んでいるわけで、今年も高い売上高成長を記録しそうな感じです。
先週一週間出張でエントリーが滞りました。
少しずつ追いついていきます。
ウォルマートがネット販売専用のセンターを2つ新設すると発表しました。
1つは今月中にテキサス州にオープンし、次は来年中に東海岸のペンシルベニア州にオープンするとのこと。
現状では1ヶ所しか持っていないようなので、トータルで3つにするということですね。
ウォルマートはネット販売の売上高がグローバルベースで年内にも100億ドルを超えると予測しているのですが、1ドル100円換算で1兆円ですから、すでに相当な規模となっていることが分かります。トータル連結売上高4692億ドルに対して小さな比率に過ぎないという表現が使われることが多いのですが、しかし分母が桁外れに大きいからそう見えるだけで、実際はすでに大きなネット販売企業です。
それが今までセンター1つで済ませることができた理由は既存の店舗を使ってきたからでしょうね。
ウォルマートはアマゾンへの対抗手段として、既存の店舗ネットワークを最大限に利用することにプライオリティを置いているので、店舗使用は戦略として間違っていないと思います。
ただそのためコスト高になっているようで、それを解消するためにはやはり専用のセンターが必要だ、ということなのだと思います。
ウォルマートはパレット単位の物流に長けてますが、アイテム単位のフルフィルメントにノウハウがない。
これをこれからいかに獲得してアマゾンに追いつくかといったところだと思います。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
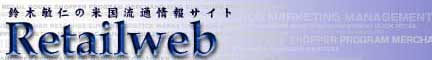





最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS