アマゾンが第4四半期と通年の決算を発表したのですが、2015年度の売上高が1,070億ドルとなって、とうとう1,000億ドルの大台に乗りました。
日本で言うならば10兆円ですね。
創業20年目の快挙となります。
ウォルマートが1,000億を超えたのは創業35年目のことでした。
という損益上の話はニュースになっているので皆さんご存知のことと思います。
実はこの企業の場合、注目すべきはキャッシュフローなんですね。
ジェフ・ベゾスは損益よりもCFを重視する人です。
2015年度末のフリーCFは158億9,000万ドルで前年比9%増。
赤字だろうと何だろうと、この企業が強い理由の源泉がこれです。
参考までにウォルマートの2014年度末のフリーCFは91億3,500万ドル、アマゾンに負けてます・・・
@WalmartLabsがOneOpsと呼ぶプラットフォームをオープンソースとして公開しました。
OneOpsは、「a cloud management and application lifecycle management platform」、クロスクラウド対応で、アプリケーションを継続的にマネジメントすることを実現するプラットフォーム、と説明されています。
IT系素人の我々には分かりづらいのですが、日本語での説明はここが一番分かりやすいかもしれません。
クロスクラウド対応の"PaaS 2.0"「OneOps」がOSSで公開される
このOneOpsは2013年に買収で手に入れたプラットフォームで、自分自身でも使用しているようですね。
アマゾンのクラウドサービスAWSに対して、クラウドをまたいで使える仕組みをオープンに提供してしまうことで対抗しようとしている、とでも言えばいいのでしょうか。
ウォルマートのEコマースのレベルの高さを実感できる事例ではないかと思います。
アマゾン・ダッシュボタンの発展型、アマゾン・ダッシュ・リプレニッシュメント・サービス(DRS)を組み込んだ商品の販売がはじまりました。
ブラザーのプリンター、GEの食洗機、Gメイトスマートの血糖値モニターの3つが最初で、これからどんどん商品が増えていきます。
まずブラザーのプリンターの説明ページはこちら。
Amazon Dash Replenishment for Brother printers
それからDRSそのものの説明ページはこちら。
Amazon Dash Replenishment
要するに生活消費財にセンサーをつけて、消費量をモニターし、一定レベル以下になったらアマゾンに自動で注文が入るというコンセプトです。
モノがネットにつながっていくIoTの典型例ですね。
アマゾンによる囲い込み戦略の進化が止まりません。
大きなニュースなので日本でもすでに報じられていますが、ウォルマートが社員の待遇の改善を公的にリリースしました。
2月20日から時給制社員120万人超の最低時給を7.25ドルから10ドルへと引き上げます。
ただしエントリーレベル(つまり小売で働いたことのないような初心者等)の新人は9ドルからとなります。
また12月31日の時点で働いていた人は最低2%の昇給や、新たな福利厚生プランなどが含まれています。
この結果、時給社員の平均賃金はフルタイマー13.38ドル、パートタイマー10.58ドルとなるそう。
一日に引き上げる賃上げとしては過去最大規模と言っているのですが、アメリカだけではなくグローバルでみても確実に最大でしょう。
賃上げにより平均賃金はフルタイマー13.38ドル、パートタイマー10.58ドルとなるそうです。
ウォルマートはたたくと目立つのでスケープゴートになりやすく、賃金が低いと批判されがちなのですが、実はターゲットもけっこう低いと指摘されているんですよね。
まったく話題になりませんが、ダラーゼネラルやダラーツリーあたりはもっと低いはずです。
今回の賃上げは批判に対応してというよりも、最低時給を10ドルレベルに引き上げる動きが全米にあって、事実カリフォルニア州を筆頭に10ドルへとする州が増えてきていて、不可避とみて真っ先に上げてしまったというのが真相だろうと思っています。
10ドルは現在のレートで1,200円弱。
東京の最低時給が907円。
今の為替レートで日本と比較すると、アメリカはけっこう高いんです。
JCペニーが白物家電の販売を実験すると発表しました。
開始は2月1日から、店舗はサンアントニオ、サンディエゴ、タンパの3店舗だそうです。
JCペニーが白物家電から撤退したのは1983年のことなので、実に30年ぶり以上を経て復活ということになりますね。
もともとJCペニーはシアーズと同じゼネラル・マーチャンダイズ・ストア(GMS)業態で白物家電を売っていたのですが、80年代にかけて非食品から撤退し、デパートメントストアへと変革したのでした。
JCペニーはホームデポから移ってきたマービン・エリソンがCEOとして再建努力をしているのですが、業績が上向いているんですよね。
エリソンはホームデポで、不採算店舗の業績をどんどん改善して一気に出世した人で、次のCEO候補とも言われていたのですが、商品部系のグレッグ・メニアが2014年にCEOに昇格し、昨年初頭にペニーに移ってしまった経緯があります。
ホームデポというハードな世界で手腕を発揮した人が、ファッションリテーラーでどうだろうと思っていたのですが、今のところ業態というハードルは関係なく能力を発揮しているわけで、優秀な人なんだろうなと思います。
JCペニーのサイトで検索されるトップカテゴリーに白物家電が入っていて、これが実験のきっかけだとしています。
エリソンにとってはホームデポ時代に経験があって、特性が分かっているというのもあるんでしょうね。
ホームファッション部門の売上が落ちていて、カバーするためという目的もあるようです。
アメリカ人がJCペニーで再び白物家電を買うのかどうか、実験結果が楽しみですね。
アマゾンの中国の子会社がFederal Maritime Commission(FMC、連邦海運委員会)に登録したとシアトルの地元紙が報じました。
子会社名はBeijing Century Joyo Courier Service Co(通称はアマゾンチャイナ)、FMCは海外との海上通商を規制する政府組織。
おそらくアマゾンは中国との海上輸送において、フレイト・フォワーダーを自分でやるのではないかと見られています。
アマゾンはいつも通りノーコメント。
フォワーダーは輸送手段を持たず、複数の荷主の貨物を集約してまとめて航空会社や海運会社と契約するアウトソーサーです。
トレーラーを買い、飛行機リースの交渉中という話と組み合わせると、行こうとしている道が見えてくるのではないかと。
陸海空のすべてのサプライチェーンで自社オペレーションか、またはそれに近いものを目指す。
海外から消費者まで一気通貫というわけけです。
ウォルマートが269店舗の閉店を発表しました。
詳細は以下の通り。
【アメリカ】154店舗
ウォルマートエクスプレス:102店
スーパーセンター:12店舗
ネイバーフッドマーケット:23店舗
ディスカウントストア:6店舗
サムズクラブ:4店舗
【海外】115店舗
ブラジル:60店舗
その他の南米:55店舗
アメリカ国内に関しては、要は小型フォーマットをやめるということです。
実験を開始したのが2011年なので、5年が当初に決めていた実験期間だったのでしょうね。
結局、現状の物流に小型店舗を組み込むための解が見つからなかったということなのだと思います。
ベントンビルで実験しているコンビニはどうするのかな?
ファミリーダラーCEOのハワード・レヴィンが1/15付けで退任し、COOのゲイリー・フィルビンが昇格することが発表されました。
ダラーツリーによるファミリーダラー買収後、統合を円滑に進める目的で残留していたレヴィンですが、主要な作業が終わったと言うことのようですね。
ファミリーダラーは1959年にハワード・レヴィンの父親のレオン・レヴィンによって創業された企業で、家族経営でした。
しかし買収されてハワード・レヴィンが去り、ダラーツリー出身のゲイリー・フィルビンがCEOとなることで、組織がダラーツリー色へと一気に変わることになります。
ファミリーダラーがこれからどう変革していくのか注目ですね。
アマゾンがフランスの宅配企業を第1四半期中に買収する予定だと、シアトルの地元紙が報じました。
企業名はColis Prive、昨年すでに25%の株を取得していて、残りの75%の株を買収して傘下に組み込むとしています。
Colis Priveという企業は私は知らないのですが、規模は大きくないようです。これからこのレベルの企業をどんどん買収して増やしていって、将来的にはFedExやUPSといった大手宅配企業並みのレベルになってしまうのではないかという見方がアナリストに出ています。
飛行機のリースを検討しているらしいですからあり得ない話ではないし、そもそもアマゾンはFedExの買収を検討したこともあると聞いています。
FedExの技術が粗く買わない方が良いと判断したそう。
この宅配、日本ではどうするつもりなんでしょうね。
いつか買収に踏み込むときが来るのかもしれません。
アップルのアプリの売上高が年間で200億ドルを超えたとメディアが報じています。
これは昨年エントリー。
[アップル] アプリの年商が100億ドル超え
1年間の増加率が100%・・・相変わらず凄い勢いですね。
ただ伸びは鈍化しているようです。
さて昨年のエントリーに書いたように、これを売上高だけで見るのは片手落ちです。
重要なのはキャッシュフロー。
前年の2倍ということは、8億6,300万ドル×2=17億2,600万ドル以上が無利子の運転資金となっているわけですね。
1ドル=120円換算で2,000億円近い。
ただ商品を作っているメーカーとは異質な財務スキームを実現しており、これが同社の強さの一つであります。
アマゾンのマーケットプレイスもスキームは同じで、損益上は赤字でも破綻しない理由がこれです。
アマゾンが決算に先立って昨年と年末のビジネスの状況をリリースしました。
・サイバーマンデーの注文数は2,300万以上(前年比40%増)
・2015年のFBA(Fullfilment by Amazon)によるグローバルの発送総個数は10億アイテム(前年比50%増)
・FBAを使ってのプライムメンバー向けの即日宅配は750都市以上に拡大
これを見る限りアマゾンの好調は相変わらずと言うことができるでしょう。
ただし同社は、というよりもジェフ・ベゾスは内情について多くを語らない秘密主義者でして、都合の良い数値のみ公開しているとも言えます。
アマゾンの決算期末は年末でしてあと一ヶ月もすれば昨年の数値が分かるのですが、おそらく売上高成長率は20%以上となるはずで、このリリースを見るまでもなくアマゾンの業績は相変わらずではあります。
明けましておめでとうございます。
今年もRetailwebをご愛顧ください。
さて年始ということでまずデータからスタートします。
・昨年の米小売業界の予測総売上高は4兆8,000億ドルで対前年比3.3%増、これは全世界の5分の1強にあたる。
・そのうちの7.1%をEコマースが占めていて、2019年には9.8%になるだろう。
・開発途上国の成長率が高いので世界に占めるアメリカの消費額のシェアは減少傾向が続くだろう。
・西ヨーロッパのEC比率は7.5%、アジアのEC比率は10.2%だった。
(eMarketer)
いまのところ予測数値しか出ていませんが、歳末商戦はプラス、ECは相変わらず伸びている、という論調が多く、昨年のアメリカの消費状況はまずまだったといったところのようです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

ソリューションを売れ!

このブログのフィードを取得
[フィードとは]
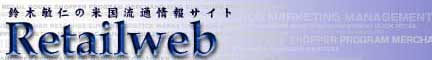



最近のトラックバック
from トイザラス
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from 英語新聞ウォールストリートジャーナル(WSJ)から見た起業・ビジネスのヒント
from デジタルな広告たち
from ファッション流通ブログde業界関心事
from ファッション流通ブログde業界関心事
from kitten using XOOPS
from 行け行け!LAビジネスウォッチャーズ
from kitten using XOOPS